慶應義塾大学教授の細谷雄一氏が、冷戦後の30年間を支配した「楽観主義」の前提が崩壊したと語る。民主主義、新自由主義、グローバリゼーションへの反発が世界を動かす新たな原理となり、ナショナリズムとポピュリズムが台頭する中で、日本が取るべきグランドストラテジーを考察する。
「進歩」の前提が崩壊した時代
冷戦終結後の約30年間は、民主主義、新自由主義、グローバリゼーションの拡大という楽観的な前提に基づいていた。
しかし、現在はこの3つの前提が崩壊しつつある。「今我々見てるのはその3つが当たり前が壊れてるということ」だと細谷氏は指摘する。
「グローバルカの拡大に対する強力な反発がアイデオロギーとして出てきてる」のだ。これが、トランプ政権やロシアのウクライナ侵攻、そして中国の行動を支える要因となっている。
この30年間で、先進国の低所得者層は豊かになった実感がない。「我々は裏切られて犠牲者なんだというその怒り」が、ヨーロッパでは極右の台頭、アメリカではトランプ政権の台頭に結びついた。日本においても、これまでくすぶっていたこの怒りが、いよいよ政治行動に結びつくようになってきたのだ。
ナショナリズムとポピュリズムが世界を動かす
人々が利己的になり、政治への関心を失うことで、「デマゴーグ(煽動者)」が現れる。公共の善ではなく、個人の利益や収入に関心が向かうことで、民主主義の公共精神が崩壊しつつある。この流れは、「かつての個人主義から手段主義的なコミュニティが重要だ」という思考への移行も示している。
デジタル技術の発展は、国家が国民を安価にコントロールすることを可能にした。中国は監視ツールやデバイスを輸出し、権威主義的な指導者が国民を統制しやすくなっている。
細谷氏は、日本においても、政府への不信感が募れば陰謀論が広がり、民主主義が機能不全に陥るリスクがあると警告する。
新自由主義の衰退は、人々が失った家族や地域共同体といった「コミュニティ」の再興への動きに繋がると予測される。しかし、市場で解決できない人々の「心」や「アイデンティティ」の問題を、経済原理を無視した「国民の感情に基づいた政策」が拡大する可能性がある。
グローバリズムの衰退に伴い、国家が壁を作る動きが強まり、世界的な合意形成が困難になる。その中で、「クアッド」や「オーカス」のような少数の国々による「ミニラテラリズム」の枠組みが強化されるだろう。
日本の特殊性と日米同盟の未来
日本は、アメリカやヨーロッパと異なり、社会の分断が進んでいないとされてきた。しかし、今回の参議院選挙で、日本も例外ではなくなりつつあるという認識が海外で広まった。
日本は「国際化し開かれた社会」を維持しつつ、社会の分断を加速させない舵取りが重要だ。
過去5〜10年、「日本は多くの局面で自由民主義諸国のリーダー」として役割を果たしてきた。安倍晋三元総理が掲げた「自由で開かれたインド太平洋」構想は、世界に最も浸透した日本の外交戦略だ。
しかし、細谷氏は、日米同盟の「黄金時代」が終わりを迎え、新たな形に移行しつつあると語る。日米同盟の「魂」を込めてきたアミテージ氏やナイ氏のような「アライアンス・マネージャー」が育ちにくくなっているためだ。
アメリカは今後、「前方展開」から、「オフショア・バランシング」へ移行する可能性が高い。「日本の防衛力自体を大幅に強化しなきゃいけない」時代が来るのだ。
新しい「物語」の必要性
国民を統合し、方向性を示すためには「物語」が必要だ。しかし、「日本政治にはその物語がない」と細谷氏は警鐘を鳴らす。
トランプやプーチンの成功は、物語を紡ぐ才能のある人材に支えられている。日本も、良質な政治を可能にするため、国民が共感できる「新しい物語」を紡ぎ、発信していく必要がある。
自民党の長期政権は稀な成功例だったが、信頼できる代替政党が育たなかった。その結果、「維新や参政党のような自民党右側へのオルタナティブ模索」に繋がった。
良質な国家介入と、経済原理の良質な部分を組み合わせることで、日本経済のダイナミズムを取り戻すことができる。はたして、日本は社会の分断を乗り越え、民主主義の健全性を維持することができるだろうか――。

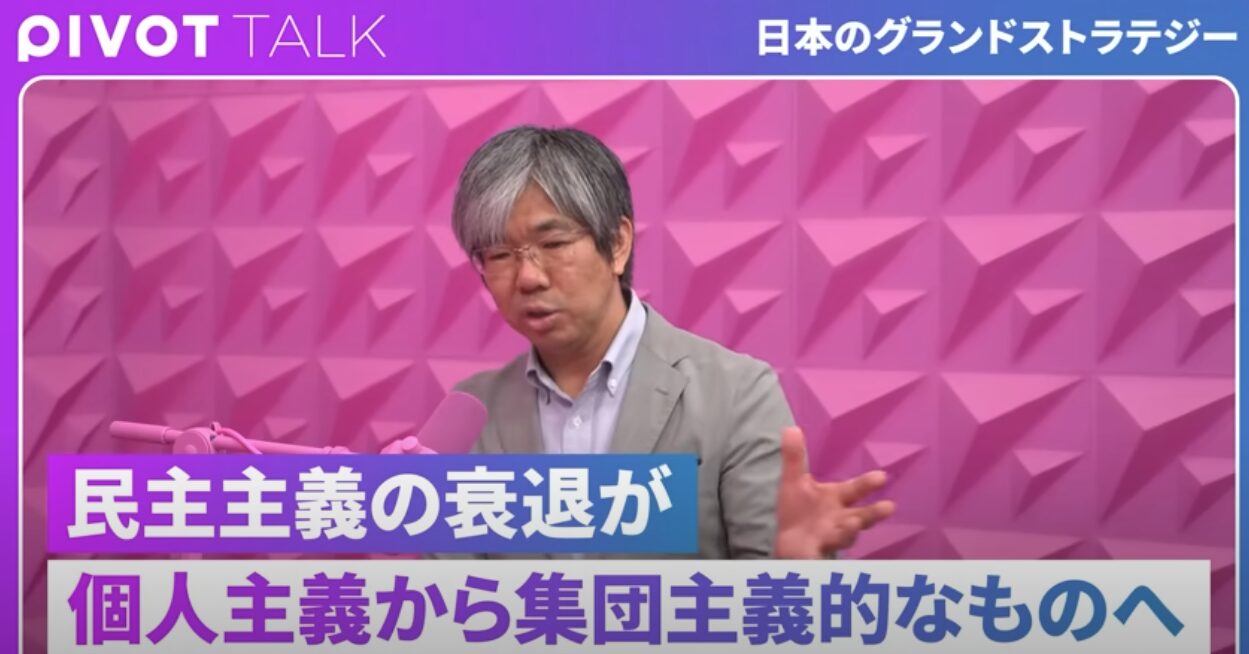


コメント