評論家の與那覇潤氏が、現代社会に蔓延する「専門家信仰」と、それに伴う「キャンセルカルチャー」の危険性について警鐘を鳴らした。特に新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、それまでメディアに登場しなかった「専門家」が突如として脚光を浴び、「大学の先生の肩書きを持つ人は『私専門家です、正しい判断はこれです』って言ったらみんな信じようみたいなものすごくこう学者を権威化する流れ」が生まれたと指摘。これにより、人々が情報を吟味することなく専門家の意見を鵜呑みにし、「自分が他の人を叩く道具に使う人が圧倒的に増えてしまう」という「思考停止社会」の現状を浮き彫りにした。
「専門家ブーム」が招いた吟味能力の欠如
與那覇氏は、コロナ禍における「専門家ブーム」の到来は、それまで「全くメディアで注目されてなかった。見たことない」人々が突如として専門家として登場したことに起因すると述べた。この状況下で、一般の人々は「その人がどの程度本当にそのテーマを専門にしてるのか、どういった業績があるのか、そこに例えばこういう方法論で研究していればいいの偏りはないのかみたいに吟味できない人が『いや、専門家はこう言ってるじゃないか』と。に100%鵜呑みしていきなり信じちゃう」傾向が強まったと指摘する。
その結果、「本人が信じるだけならまだしも、『だから違うこと言ってるやつはダメなんだ』と。例えばそのコロナに関して言うと『専門家が自粛しろっつってるじゃないか』と。……『こいつらはこうネットでバッシングして叩くべき』みたいな。そういう振る舞いをする」人々が急増したとし、専門家の意見が他者を攻撃する道具として悪用された実態を浮き彫りにした。與那覇氏は、「専門家って名乗ってる人が出てきたらすぐ鵜呑みにするんじゃなくて、ま、1回疑った方がむしろいい」と、情報リテラシーの重要性を訴えた。
学術界の「ピアレビュー」機能不全
学術界には、学者同士が互いの研究内容をチェックし、品質を保証する「ピアレビュー」という仕組みが「建前としてはやってることになってる」と與那覇氏は説明する。しかし、コロナやウクライナ戦争、パレスチナ紛争といった進行中の問題において、「『私専門家なんです』っていう風に言って出てきた人が後から見ると『え、あれ違ったんじゃないの言ってたことが』っていう風に、それが炎上に発展したりとかね。そういうことってよく起きてます」と指摘。にもかかわらず、学術界内部で「この人の言ってたことのここはすごくいいことだったと。でもここはちょっとグレーゾーンだし、これはやっぱり反省がいるんじゃないかみたいに。例えばそういうシンポジウム、例えばご本人も読んで、ご本人も信頼できるこの人がチェックしてくれるんだったら『なるほど納得できますね。あなたはしっかりした人だから』っていう研究仲間を呼んでやってる例ってあるかっていうとないでしょ」と、学術共同体による適切な「総括」が行われていない現状を批判した。
與那覇氏は、このような議論の場を設けることは「学者の評判を回復させるすごくいいイベントになる」にもかかわらず行われないのは、「普段からしてないからだ。できない」からだと厳しく指摘した。
「言いっぱなし」専門家の危険性──主張の「副作用」への無配慮
メディアに登場する専門家には、「私の言ってることが正しいんだから私の言うことだけ聞けタイプ」と、「別にいじられたっていいじゃないの」というタイプの二種類が存在すると與那覇氏は分析する。コロナ禍では、「本来はメディアとかエンタメとかと1番遠い」はずの前者のタイプが、社会のパニックと「これが正解。これを信じろ。これを疑うな」というニーズによって表に出てきてしまったことが「最悪になる」状況を生み出したと述べた。
一般市民に向けて発信する専門家は、「自分の主張の副作用を考えることなのだ」と強調した。「俺がこういうことを大けの場でで言ったらこういう副作用が起きえるな」という配慮を欠く「言いっぱなし」の専門家が、社会に悪影響を及ぼしていると警鐘を鳴らした。
専門家の「一般人化」と「安易なレッテル貼り」の末路
ウクライナ戦争を例に、「ロシアはダメウクライナを応援」といった単純な二元論や、SNSで国旗のシンボルマークをつけるといった行動は、専門家が「普通の人レベルになっちゃった」状態であると批判した。専門家が自分の専門知識を「資本主義で商品売る時の方法」や「このブランドの服着てればあなたかっこいいってなりますよ」といった「フォーマットに自分の専門を流し込む」ことは、「ビジネスであっても学術じゃない」と断じた。
コロナワクチンに関する議論では、「コロナワクチンについて疑問を呈するやつはやばいやつだよと。そういうこと言うと『お前は非科学的』っていう風になんかネットで叩かれるよみたいな空気を作っちゃったことは否定できない」とし、専門家が「安易な手段に手を染めた」結果、妥当な疑問を持つ人まで「反ワクチン」というレッテルを貼られたと指摘した。その結果、「『ワク信(ワクチン信者)』や『ウ信(ウクライナ信者)』みたいなこう別の略語ができる」といった「必ずしっぺ返しってものはある」という因果応報が起きていると述べた。
「コンプライアンスを守りながら逸脱したい」社会の闇
與那覇氏は、専門家への過剰な信頼と、一方での過剰なバッシング(キャンセルカルチャー)は「表裏一体の全く一体の現象だ」と分析する。その根底には、「答えが見えない世界だからこそ言ってほしい」という欲求と、「安全に人を叩きたい」「本来なら認められないタイプの自分の欲求を発散する」という欲望があると指摘した。
現代の日本社会では、「コンプライアンスを守りながら逸脱したいっていう欲求が日本にはめちゃくちゃ溢れてる」と述べた。本来なら抑えるべき暴力性や攻撃性が、「これは正しい発散の仕方だから責められませんよ」という「免罪符」のもとに顕在化しているとし、「私専門家の主張に沿ってるんでこの暴力は正しい暴力なんです」という論理で「ネットリンチ」を行う人々が増加している現状を憂いた。専門家が「逸脱願望にお墨付きを与えちゃう」存在になることは「アウトな存在なのだ」と強く警告した。
與那覇氏が提示する現代社会の課題は、専門家と社会の間に失われた信頼関係の深刻さを浮き彫りにしている。はたして、学術共同体が「私たちはそういうルールでやってます」というガイドラインを明確にし、専門家が自身の発言の「副作用を自覚」し、安易な「逸脱願望にお墨付きを与えちゃう」存在とならないように振る舞うことで、この「思考停止社会」から脱却できるだろうか――。
【メディア問題】専門家信仰が招く「思考停止社会」/議論風エンタメは社会の役に立っているのか?(評論家 與那覇潤)【ニュースの争点】


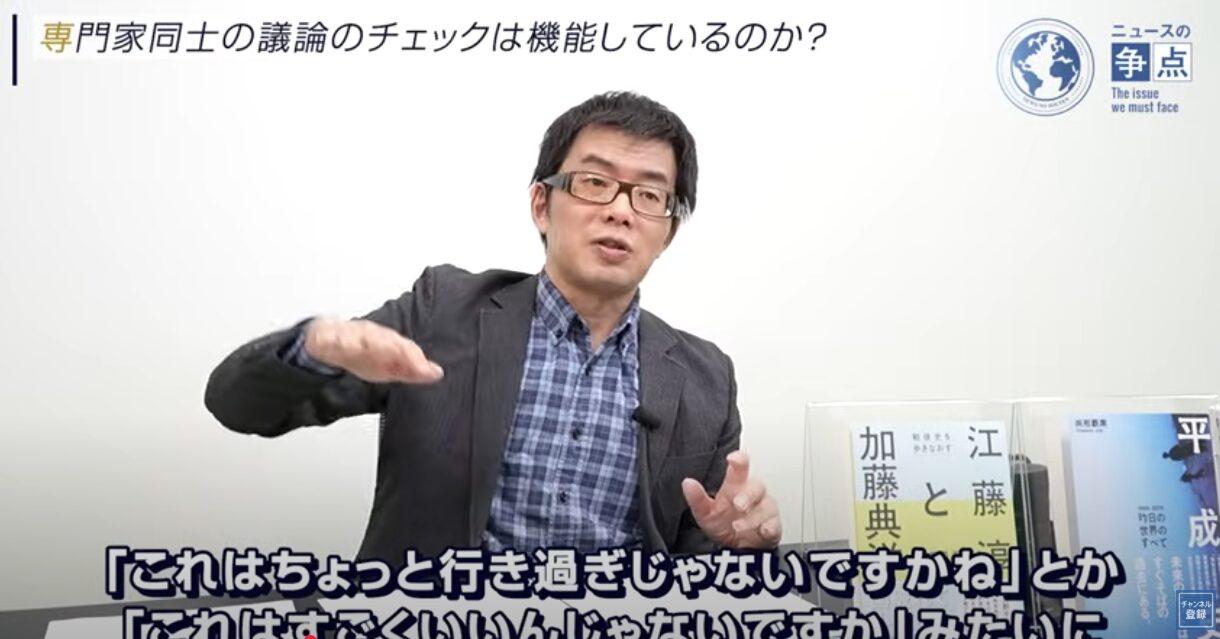


コメント