国際ジャーナリストの山田敏弘氏が、日本が「脅威に晒されており、非常に弱い状態にある」と警鐘を鳴らす。近年、中国によるスパイ活動が世界中で活発化しており、特に日本の政治家や企業が狙われている現状を指摘。スパイの具体的な活動内容から、日本の法整備の遅れが「スパイ天国」と呼ばれる所以であること、そして国際協力における損失、さらに中国の巧妙な手口と、渡航時のリスクについても詳細に解説した。
「スパイ天国」日本が抱える脅威の現状
国際ジャーナリストの山田敏弘氏は、現在の日本が「脅威に晒されており、非常に弱い状態にある」と強い危機感を表明する。特に近年、「中国による活動が近年多く」見られ、世界中で「政治家を育成しようとする動き」が活発化しているという。日本の現役国会議員の秘書の中にも「怪しい人物がいる」ことがあり、彼らが「握られている可能性」も示唆された。
スパイの主な仕事は「情報収集」である。これは表向きの情報だけでなく、「イベントの裏で起きていることやその過程、関係者の目的などを事前に、または事後に調べること」も含まれる。プロのスパイは「莫大な予算と最新のテクノロジーを駆使して情報収集を行う」存在だ。
スパイ活動の至上命令は、「ばれないように情報を盗んだり、影響工作をしたり、作戦を遂行する」ことだ。そのため、映画のような派手なイメージとは異なり、実際に会ったスパイの多くは「地味な人たち」だという。殺害や銃撃といった目立つ行為は警察の介入を招き、「注目を集めるため、基本的には行われません」。しかし、ロシアやイスラエルのモサドのような組織では、情報収集や影響工作のために必要であれば、「邪魔な人物を排除することもある」とされている。
日本が「スパイ天国」と呼ばれる理由
世界のスパイ組織は、「国外情報機関(CIA、MI6など)」「国内情報機関(FBIなど)」「軍の諜報機関」の大きく3つに分けられる。日本には、CIAやMI6のような「対外情報機関が存在しません」。一方で、日本に入ってくるスパイを調査する機関としては公安警察、公安調査庁、防衛省の情報本部があり、「国内に入ってくるスパイの監視能力は高い」と山田氏は評価する。
しかし、日本が「スパイ天国」と言われる背景には、公安機関の能力が高いにもかかわらず、「スパイを摘発できるだけの法律が整備されていない」という根本的な問題がある。日本にはスパイ活動そのものを取り締まる「スパイ活動禁止法」のような法律が存在しないため、スパイが情報収集活動を行っていても「見ているだけで手を出せないのが現状」だ。情報が実際に盗まれた場合でも、「窃盗罪や不正競争防止法違反などの『別件』で摘発されることはあります」が、スパイ行為そのものを逮捕することはできない。企業が被害に遭っても、警察ができるのは「社員が勧誘されているから注意してください」と連絡することに限られるという。
さらに、政府の正規職員として来日するスパイは「外交官」の肩書きを持つため、「不逮捕特権を有しており、犯罪を犯しても逮捕されません」。過去には、ロシアのスパイに勧誘された自衛官が逮捕された事件があったが、情報を渡したロシアのスパイは不逮捕特権によりその場を立ち去り、「数日後にスーツケースを引いて帰国した」という。「盗まれた情報を取り返すこともできず、逮捕もできないのが日本の現状」だと山田氏は指摘する。
この法整備の遅れは、国際的な情報共有の枠組みへの参加にも影響を及ぼす。アメリカや西側諸国が結ぶ「ファイブ・アイズ」のような情報同盟は、価値観の共有と「きっちりと情報を守る法律があるため」に成り立っている。しかし、日本は法整備ができていないため、この枠組みに入れてもらえず、「信頼を置いてもらえていないのが現状」である。
中国によるスパイ活動の巧妙な手口
中国は、日本が特に情報を欲しがっている国の一つであり、隣国として深い利害関係がある。中国のスパイ活動は多岐にわたる。
政治家への影響工作
中国は「自国に都合の良い政治家を育成したり、政策に影響力のある人物を動かしたりする」ことを狙っている。世界中で問題になっているのは、「政治家の秘書にスパイを潜り込ませる活動」であり、日本でも「国会議員の秘書の中にも、中国の政府系機関と関係のある人物が確認されています」。このような人物が「国会議員の通行証を持ち、自由に議会を往来できる状況は問題視されていますが、日本の法律ではその活動自体を取り締まることができません」。
過去の衆院選と関連付けて、中国が数年間かけて「自国に都合の良い政治家が国のトップになること」を望み、工作活動を行っている可能性も指摘されている。また、議員連盟などを通じて中国と近い関係にある「媚中派」と呼ばれる政治家を取り込む活動も活発だ。政治家が「握られている」、つまり弱みを握られ、情報提供や特定の行動を強要されているケースも存在すると推測されており、ハニートラップのような手口も用いられることがある。
産業スパイ活動とデジタル情報収集
産業スパイ活動では、「留学制度を利用」する手口が見られる。中国政府が有能だと見込んだ留学生に声をかけ、日本企業への就職を支援するのだ。また、日本に来ている中国人の中には、中国政府のやり方を嫌う者もいるが、その場合は「中国にいる家族の年金や学校への影響をちらつかせたり、小遣いを渡したりして情報提供を促すパターン」もあるという。
「偶然を装った接触」も巧妙な手口だ。繁華街などで一人で飲んでいる人に声をかけ、親しくなってから情報提供を求めるケースや、道に迷ったふりをして社員に接近し、「個人的な情報(趣味嗜好など)を探りながら心理的な弱みにつけ込んでいく」手口が用いられる。
さらに、「共同開発」の提案には特に注意が必要だ。中国側から共同開発を持ちかけられる場合、「技術を狙っている可能性が非常に高い」という。共同開発と称して技術を盗み、その後、中国側が安価な製品を先に市場に投入し、日本の企業を潰すという事例が報告されている。日本の大学教授が開発した精密機械の技術が軍事転用可能と見なされ、研究費を提供する名目で共同開発を持ちかけられ、サンプルを渡してしまったケースもある。
現代のスパイ活動の「約7割はパソコンやデジタルデバイス上で行われている」と山田氏は述べる。中国では、国家情報法により「中国の国民、企業、現地採用者を含む関係者全員に情報提供の義務が課せられています」。また、反スパイ法も改正され、「デジタルデータも情報収集の対象」となっている。中国に渡航する際は、「スマホやパソコンに痕跡を残さない」よう細心の注意が必要だ。政府関係者や企業関係者は、プライベートのデバイスを持ち込まず、政府支給のデバイスを使用することが推奨される。過去には、日本政府の要人のパソコンにウイルスが仕込まれていた事例も報告されている。中国国内ではVPN(仮想プライベートネットワーク)の使用や通信の暗号化が禁止されており、「データが丸裸にされ、見られている」と認識すべきだ。
中国での邦人拘束事例と「スパイの広範な範囲」
中国では、日本人ビジネスマンが「スパイ容疑で不当に拘束される」事件が多発している。アステラス製薬の日本人幹部が拘束された事件では、半年以上拘束され、後に起訴された。この人物は、日中の橋渡し役として活動していたにもかかわらず、日本への情報持ち帰りを懸念され逮捕されたと推測される。
拘束された場合、日本政府や大使館が拘束理由を把握することや、本人との面会が困難な状況が続くことがある。「国家情報法により、中国の国民、企業、関係者全員に情報提供の義務が課せられています」。「スパイの範囲が非常に広範」なため、拘束を避けることが困難な状況だ。観光客であっても、街中で「建物の写真を撮るだけで、それが軍事施設と見なされれば、スパイ行為の口実を与えてしまい、拘束される可能性」がある。
山田氏は、日本にいるとスパイ活動が身近に感じられないかもしれないが、実際には「すぐ近くで発生している脅威である」と強調した。
国際ジャーナリストの山田敏弘氏が指摘する日本の「スパイ天国」問題は、法整備の遅れに起因し、国家安全保障上の重大な脆弱性を示している。中国の巧妙かつ組織的なスパイ活動は、政治、経済、そして個人のデジタル情報にまで及ぶ。外交特権を持つスパイの取り締まりが困難な現状は、国際的な情報共有の足枷にもなっている。この脅威は決して遠い話ではなく、私たち自身の問題として認識し、法整備の必要性を強く訴えていくべきである。
国際ジャーナリスト・山田敏弘が警鐘を鳴らす!「日本が『スパイ天国』と呼ばれる理由と中国の巧妙な手口」


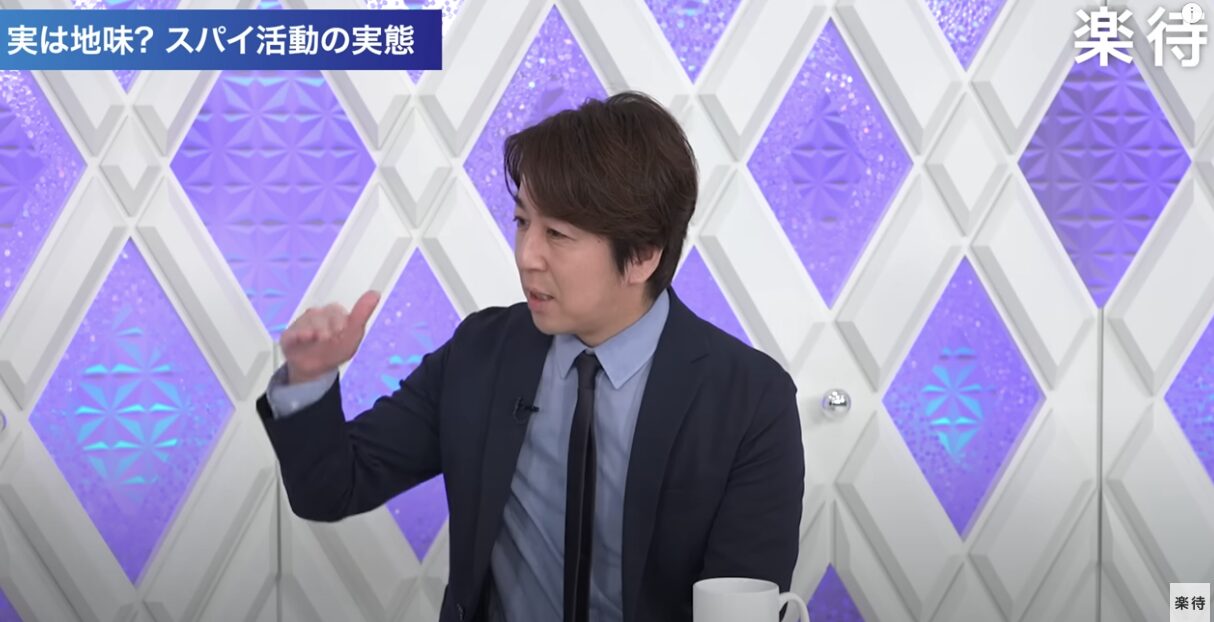


コメント