経済評論家の渡邉哲也氏が、米国が導入した新たな関税政策の真意を読み解く。これは単なる貿易協定ではなく、米国独自の「IEPA法」に基づく国家安全保障上の措置であり、その目的は「作るアメリカ」を復活させることだと語る。
「IEPA法」という最強の武器と「緊急事態」の定義
今回の米国関税は、通常の貿易協定に基づくものではなく、米国独自の「IEPA法(緊急経済権限法)」に基づいていると渡邉氏は指摘する。この法律は、大統領が国家非常事態宣言を発令すれば、資産没収や関税賦課など、ほぼフリーハンドであらゆる措置を取ることを認めるものだ。
米国は、現在抱える「膨大な貿易赤字」を緊急事態と定義した。これは、世界各国が米国からの貿易黒字によって生活しており、米国の製造業等の生産基盤が奪われ、このままでは国家が存続できないという認識に基づいている。その主要な目的は、世界各国に対し「貿易赤字の穴埋め」、すなわち、貿易黒字を米国に返すよう求めることだという。
「80兆円」の真意と日米の新たな関係
一部で誤解されている「80兆円を税金として米国に渡す」という解釈は間違いだと渡邉氏は断言する。この「5500億ドル(約80兆円)」は、日本と米国の「投資手段の提供」を指す。
この投資の枠組みは、日本企業等が米国に投資する際に、保険や支援を行うことで、米国に投資しやすい環境を整えるものだ。投資対象となるのは、LNG・先端燃料、エネルギーインフラ、半導体製造、重要鉱物、医薬品の国内回帰、そして米国の造船業の復活など、多岐にわたる。
トランプ政権は、これらの投資を通じて米国を再び「製造業としての作るアメリカ」に戻すことを目指している。米国単独では困難なため、日本を含む世界各国に協力を求めている。日鉄によるUSスチール買収も、この構造の中で成功した例として挙げられている。
この投資による利益の90%は米国国内に留保され、再投資されることが求められる。これは、中国の政策と類似している。渡邉氏は、この「80兆円」という金額が、日本の年間貿易黒字8兆円の10年分に相当することから、長期的な貿易収支是正を意図していると分析する。
関税率に隠された米国の意図と「関税同盟」の形成
米国は、日本からの輸入品には15%の基本関税を課すなど、各国に関税率を設定している。しかし、その税率は単なる経済指標ではなく、米国との関係性を表すものだと渡邉氏は読み解く。
ブラジルやシリア、ラオスといった「反米国家」と見なされる国々には高率の関税が課されている。スイスには39%という高関税が課せられたが、これは金の輸出による貿易黒字の膨大さや、医薬品製造の米国移転が合意に至っていないためだと推測される。
インドに対しては、ロシアからの安価な武器やエネルギーを大量購入し、第三国に転売して利鞘を抜いていると見ており、これをやめない限りさらなる関税を課すと脅しているという。
この関税は、米国の「関税自主権」と「国家緊急事態」に基づいているため、米国政府の判断で上下させることが可能だ。米国は単なる経済問題としてだけでなく、米国との関係性を表すものとして関税率を設定しており、「関税同盟」を形成しようとしている。BRICSなど、米国と対抗する国際枠組みを構築した場合、高関税を課すとしており、特にBRICS共通通貨の導入には「1000%の関税」を課すと警告している。これは、米国の「通貨支配」および「世界的な産業支配」を確立する意図がうかがえる。
「デミニマス・ルール」の廃止と中小企業への影響
今回の関税政策で特に注目すべきは、「デミニマス・ルール」の変更だ。これまで800ドル以下の小口貨物(国際郵便等)は免税されていたが、米国当局は、中国や香港、マカオへの関税強化後、フェンタニルなどの違法薬物が第三国を経由して米国に流入していると主張し、このルールを全品目に対して「一旦停止」し、2027年からは「廃止」すると発表した。
これにより、今後は小口貨物にも関税が課せられる。実行関税率16%未満の国(日本など)からは1個あたり約1万4千円、16%以上の国からはそれ以上の関税が課せられる。この変更は、全品目チェックにかかるコストの回収と、小口貨物の配送そのものを抑制する目的があり、個人や中小企業による国際的な小口貿易にも大きな影響を及ぼすだろう。この変更は2024年8月27日から適用される。
はたして、米国のこの強硬な政策は、世界にどのような秩序をもたらすだろうか――。

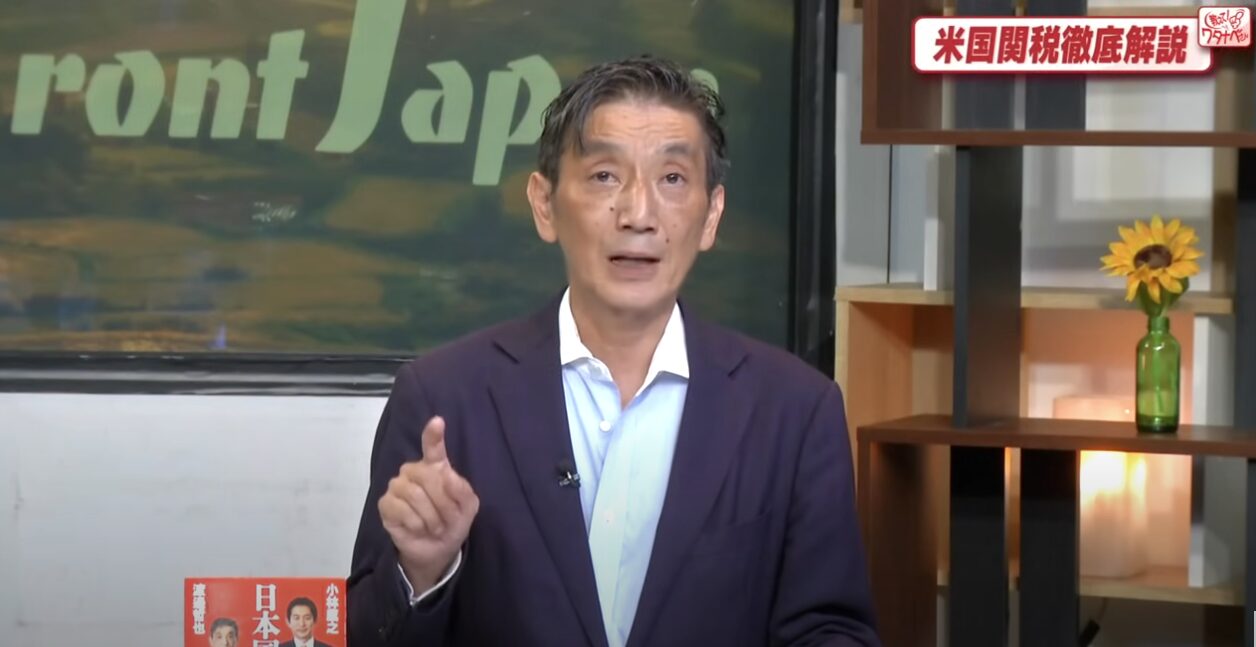


コメント