元駐中国大使の垂秀夫氏が、中国を理解するための核心的な視点と、習近平政権の深層を語る。多くの日本人が見過ごしがちな「戦略的思考」の重要性を説き、中国経済の現状、台湾問題、そして習近平後の中国の展望について、感情を排した客観的な分析がなされている。
中国を理解するための3つの原則
垂氏が中国を理解するために最も重要だと強調するのが、感情や先入観を排除した「客観的な情報収集」だ。多くの情報に触れ、論文の著者と直接会うことで、単なる事実だけでなく、その背景にある「付加価値情報」、すなわち「インテリジェンス」を得ることが鍵だと語る。
そして、中国を理解するには、「中国共産党を知ることは不可欠」だと断言する。特に毛沢東の「矛盾論」「実践論」「統一戦線工作理論」は、今日の中国の行動原理に深く根ざしており、中国に関わる者にとって「必須の教養」だという。
また、垂氏は「日本人が一番足らないのは戦略的思考なんですね」と指摘する。毛沢東が日中戦争中に示した「721指針」を例に挙げ、その徹底した戦略性を解説。相手が戦略的な思考を持つ国である以上、日本もこれを磨く必要があると警鐘を鳴らす。
習近平の野心と「現代版冊封体制」
習近平政権は、鄧小平時代とは異なる、新たな国際秩序の構築を目指している。垂氏は、この動きを「現代版冊封体制」と呼ぶ。習近平は、G7を「小グループ」と見なし、途上国への投資や援助を通じて、中国に都合の良い国際秩序を築こうとしている。
習近平による権力集中は、胡錦濤時代の「政権が倒れるかもしれない」という危機感から生まれたと分析する。集団指導体制を破壊し、自らを毛沢東に次ぐ指導者と位置づけた背景には、「自分の好きなようになれないからやれない」という野心があったという。結果として、「真の習近平時代の到来」には10年を要した。
鄧小平が最重視した「経済発展」から、「国家の安全」を最優先する政策に転換したことも大きな特徴だ。反スパイ法の強化や、福島処理水問題への過激な反応は、その表れだという。
崩壊寸前の中国経済とBYDの危機
中国経済の現状について、垂氏は「我々が思ってる以上に相当悪い」と強調する。公式発表されている5%以上の成長率は「いい加減な話」であり、実態は「良くて1、2%」程度だろうと指摘する。特に深刻なのが消費の低迷であり、その根底には不動産市場の悪化がある。
不動産価格は「少しずつしか落ちない」ため、人々はさらなる下落を予想し、購買意欲が低下。保有資産は「資産価値がゼロになっているんですよ。簡単に言えば」という状態に陥っている。政府がバブル崩壊を認めないため、問題は解決せず「ずっと爆弾を抱えたままごまかしていく」状態が続くと見ている。
中国の電気自動車大手BYDについても、「相当危ない」と指摘。安売りの背景には現金化の必要性があり、サプライチェーンにおける「錬金術」的な資金調達が逆回転し、資金不足に陥っているという。
台湾問題と日中関係の未来
台湾問題については、軍事侵攻だけでなく、中国の「平和的統一」という言葉にこそ注目すべきだと警鐘を鳴らす。軍事侵攻はリスクが高く、「そう簡単じゃない」。一方で、外交的・経済的圧力やスパイ活動で台湾社会を分断させ、「平和的に話し合って解決しました」という形を追求する方が、「安上がりだし、中国にとって一番受け入れやすい」と分析する。
日本の国会議員が「台湾有事は日本有事」と叫ぶだけでは不十分であり、「もっと戦略的頭を使わないとダメ」だと提言する。日本が「愚者であってはいけなくて賢者であるべき」だと締めくくり、国力を高めていく必要性を強調する。
習近平後の中国に待ち受けるもの
垂氏は、習近平氏の健康問題は「ありうる」としつつも、直ちに深刻な状況ではないと見ている。しかし、現在の「一人独裁体制」は、彼の死によって終焉を迎える可能性が高い。
その後は、一時的な集団指導体制の復活が予測されるが、「一人による一強体制を支えるような体制になってる」ため、長くは続かないと見ている。党内民主化が進む「ソフトランディング」か、ソ連崩壊のような「大きな大混乱が起きる」ハードランディングの「あらゆる可能性はありうる」。
そして、毛沢東の死後に中国を立て直した鄧小平のような「経験値、知見持ってるような人」は、現在の中国には「見当たらない」と述べ、混乱を収める力を持つ人物の不在を指摘する。
感情を排した冷静な分析が示す中国の真実。はたして日本は「賢者」として、この難局を乗り越えることができるだろうか――

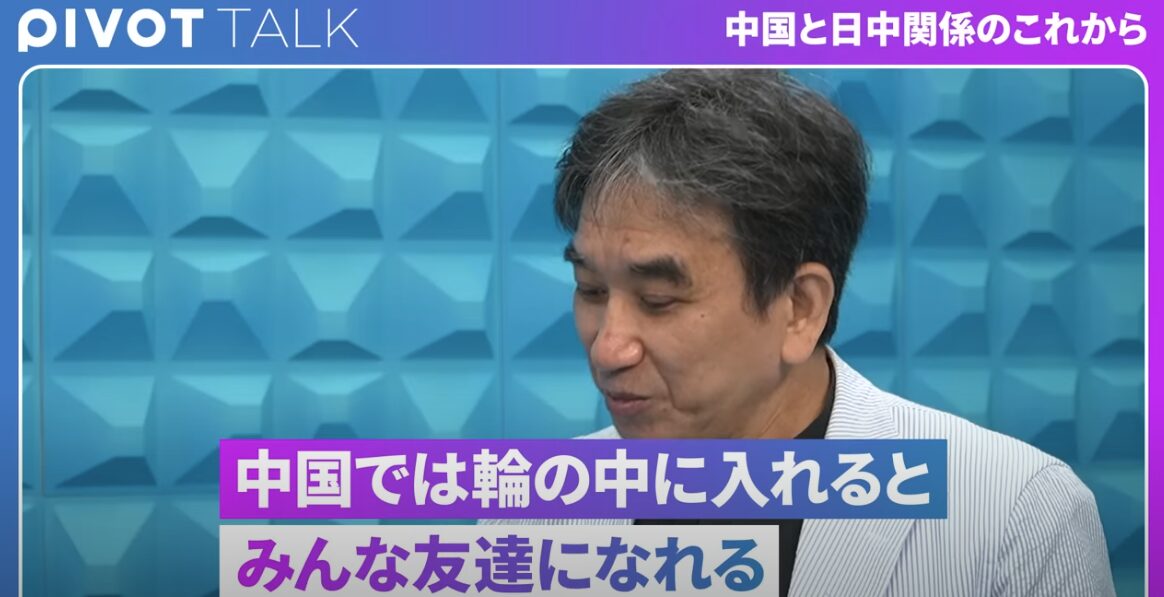


コメント