チームみらい党首の安野貴博氏が、ABCテレビ「正義のミカタチャンネル」に出演し、日本のAI戦略と、AIがもたらす未来社会の展望について熱く語った。チームみらい党首の安野貴博氏は、日本における生成AI利用率の低さを指摘しつつも、AI開発の「賢いAIを使いこなす」分野において日本の「勝ち筋はまだある」と語る。少子高齢化による人手不足を背景に、AI導入への社会的合意が得やすい日本は、エネルギー確保とサイバーセキュリティを強化し、適切にAIを社会実装することで「テクノロジーで誰も取り残さない日本を作る」ことを目指す。
日本のAI活用における現状と課題
総務省が発表した情報通信白書によると、日本における個人の生成AI利用割合は26.7%と、中国(80%以上)、アメリカ(68%)、ドイツ(60%)と比較して低い現状にある。これに対し安野氏は、画像系や動画系の生成AIでは日本のコミュニティが活発であるとしつつも、「元々の情報リテラシー、ITのリテラシーというのが、やっぱ他の国と比べてちょっと低いところが日本にはあって、その影響が結構出ちゃってるな」と、日本のITリテラシーの低さが全体的なAI利用率の低さに繋がっていると分析した。
AI開発競争において、アメリカがトップを走り、その半歩後ろを中国が追随している状況を指摘し、「そのはるか後ろに日本がいる」と厳しい現状認識を示した。特に「投資できる資金のゲーム」である側面が強く、日本とは「2桁多いお金でやっている」と、投資額の差が大きいことを語った。
日本の「勝ち筋」と少子高齢化がもたらす有利な環境
しかし、安野氏は「日本の勝ち筋はまだあると思っている方」だと語り、悲観的な見方ばかりではないことを強調した。AIには大きく分けて二つの競争軸があると説明する。一つは「賢いAIを作るぞ」という開発競争、もう一つは「賢いAIができた時にそれを産業で活用する、使いこなすぞ」という応用競争だ。前者の開発競争では日本はアメリカ・中国に「5、6年くらい遅れてる」ため厳しい状況だが、後者の「使いこなす」レースは「まだ始まったばっかり」であり、日本にも十分勝機があると見ている。
日本がAIを使いこなす上で有利な立場にある理由として、少子高齢化と人手不足問題を挙げる。「少子高齢化でどんどん人口が減ってっています。全産業人手不足になってます」と述べ、この状況を解決するためには「もうAIしかない」という切迫した状況にあることを強調した。これはアメリカやヨーロッパとは異なり、AIによる自動化が雇用の問題を直結させないため、「ここの領域においては実は社会的には有利な立場にいる」と分析した。つまり、日本はAI導入に対する社会的合意が得やすい環境にあるというのだ。
エネルギー問題とサイバーセキュリティの強化
AI活用には膨大な電力が必要となるが、日本国内でそれを賄えるかという問いに対し、安野氏は「しっかり考えなくちゃいけなくて、おそらく生成AIだけじゃなくて、AIを使っていくとすごい電気が必要になる」と述べ、エネルギー確保の重要性を強調した。今後の社会において、「エネルギーをどれだけちゃんと安定的に確保しできたかどうかっていうのが経済成長の上限を決めていくことになる」と語り、エネルギー計画で約10%足りないと試算される電力供給を確保するため、あらゆる手段を講じるべきだとした。具体的には、火力発電所の「少なくとも維持した方がいい」ことや、都市部の屋根に太陽光パネルを敷き詰めることなどを挙げた。
さらに、原発の再稼働についても「すべきだと思います」と明言し、安全性や地域住民の合意形成を前提としつつも、電力不足による社会的混乱を避けるためには必要だと訴えた。
スパイ対策やサイバーセキュリティについても言及し、日本が全体的に弱い分野だと認識を示した。現代の戦争のやり方は「地上戦が始まる前段階で電子戦と呼ばれるサイバー戦争が起き」、さらにその前段階で「認知戦と呼ばれる、国内世論にSNSなどで介入してきて、戦わずして自分たちのいい方向にその国を持っていこう」とする戦いが繰り広げられていると説明。これらの分野において、サイバーセキュリティの強化が極めて重要だと強調した。今回の日本の選挙でも「海外からの介入があったかもしれない」という報道があったことに触れ、その振り返りの必要性も指摘した。
AI規制と日本の「適切なライン」
EUでAI規制法(AIアクト)が制定されていることに対し、日本でも必要かという問いに、安野氏はEUの中でも見直しの動きがあることを示唆しつつ、「日本はこの4月、5月にAI推進法っていうのができまして私はすごく評価しています」と語った。
AI規制には、EU型のような「がっちり法律に書いて規制しよう」というアプローチと、アメリカ型の「イケイケどんどん、頑張ろうぜみたいな」アプローチがあるとし、それぞれに利点と欠点があることを説明した。規制法は新しい技術開発を阻害する可能性がある一方、アメリカ型はどこまで進むか分からず不安が残る。日本は「ちょうどその中間くらいのところに置いたので、これは結構適切なラインだと思う」と述べ、バランスの取れたAI推進法の制定を評価した。
政治とAIの融合:政策立案と選挙活動への応用
国会議員がAIを使いこなせるかという懸念に対し、安野氏は「使ってない議員さんに懸念されてるイメージがある」と苦笑しつつ、政策立案においてAIが非常に有用であることを力説した。「リサーチは本当に早くなります」と述べ、他国の政策比較など、従来であれば各言語の文献を個別に調べる必要があった作業が「チャットGPTだと全言語をまたいでやってくれたりする」と、AIの具体的な活用メリットを挙げた。
AIによる仕事の自動化と、それに伴う雇用の問題についても触れ、自身の選挙期間中に「AIあんの」というシステムを開発したことを明かした。「私の声で『質問何でも受けるよ』と言って、24時間YouTubeライブを続ける」というユニークな取り組みを紹介し、自身が演説する傍らで「バーチャル上の選挙活動はもうAIあんのがやってました」と語った。
AI時代に人間が生き残るために必要なこととして、安野氏は「AIって目的を自分で考えることはしないんですよね」と指摘する。AIは与えられた目的に対して最適な手段を実行するが、「その『〇〇をやってほしい』って命じるのはやっぱ人間である」と強調した。そのため、「『ここを目指したい』とか『これを達成したいんだ』って欲望する力、これはすごく大事だと思います」と述べ、ディレクション能力や目標設定能力といった人間の意思の重要性を語った。
テクノロジーで誰も取り残さない日本へ
安野氏は、チームみらいが目指すところは「テクノロジーで誰も取り残さない日本を作る」ことだと改めて強調する。この目標達成には「誰も取り残さないようにできるための経済力がまず必要」であり、そのためには「今後伸びていく産業を育てる」こと、特にAI産業への積極的な投資が不可欠だとした。さらに、「いろんな人の意見を聞く仕組みが必要」であり、井戸端システムのようにITやAIの力を活用することで、「今まで以上に聞けるようになるはず」と語り、この「両輪を回していこう」というゴールを描いていることを明かした。
チームみらい党首の安野貴博氏の語りからは、日本の未来をAIとテクノロジーで切り拓こうとする強い覚悟が伝わってくる。AIがもたらす可能性を最大限に引き出しつつ、リスクを最小限に抑える現実的なアプローチ、そして少子高齢化という日本の課題を逆手に取った「使いこなす」戦略は、これからの日本の進むべき道を示すものだろう。
はたして、安野氏が提唱する「欲望する力」を持つリーダーシップと、永田町に創設されるAIエンジニアチームは、日本の政治と社会に真のイノベーションをもたらし、「誰も取り残さない日本」を実現できるだろうか――。AIが社会のあらゆる側面に浸透していく中で、安野氏の挑戦が日本の未来にどのような影響を与えるのか、その動向に注目したいものだ。
チームみらい党首の安野貴博氏が、ABCテレビ「正義のミカタチャンネル」に出演し、日本のAI戦略と、AIがもたらす未来社会の展望について熱く語った。

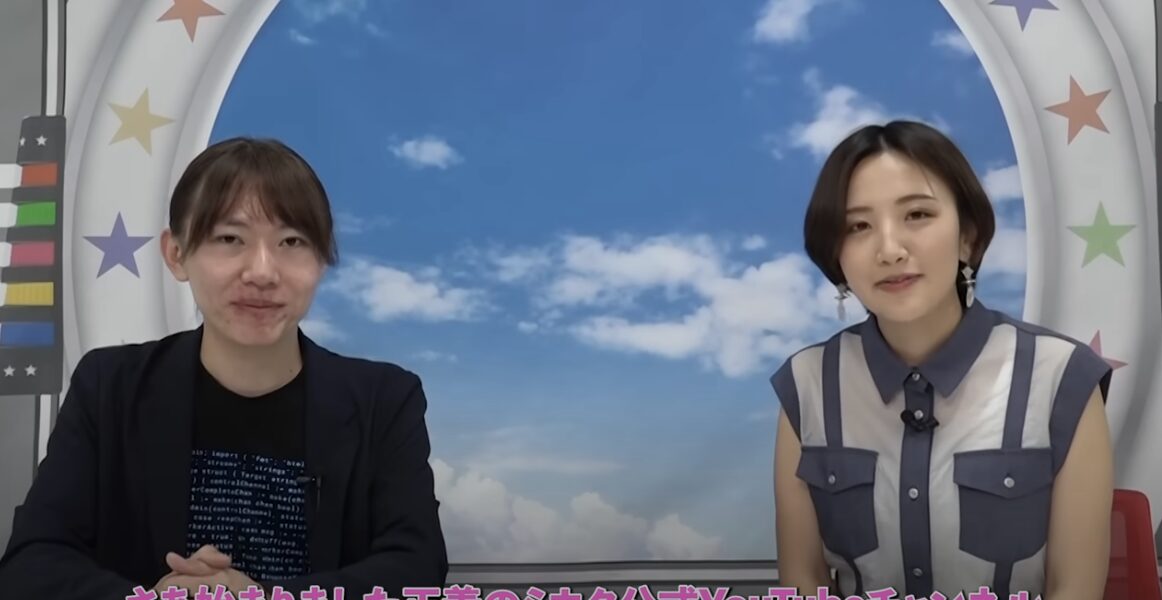

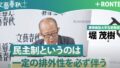
コメント