選挙ドットコム編集長の鈴木邦和氏は、今回の参院選を「政党の世代交代が起きた選挙」と総括する。与党だけでなく既存政党が軒並み苦戦する一方、国民民主党や参政党といった新興政党が躍進した背景には、SNSや動画サイトの情報を「重視した」有権者が5割に達したネット選挙の影響が大きいと指摘した。
参院選の総括:政党の世代交代と連立政権の終焉
鈴木氏は今回の参院選を振り返り、全体の総括として二つのポイントを挙げる。一つ目は「伝統的な既存政党がほぼ全部負けた選挙」だという。これは「政党の世代交代が起きた選挙」だと分析する。
二つ目は、今回の選挙をもって「自公のみの連立政権が終わりを迎えた」という点だ。その理由として、今回の自公の獲得議席が47議席だったのに対し、次の3年後に参院で過半数を取り戻すためには78議席が必要であり、これは「事実上不可能な数字」だと指摘する。そうなると、衆参含めた新たな枠組みを模索する必要があり、「すごく歴史的な選挙だった」と強調した。
実際に、自民党だけでなく、公明党、日本共産党、そして立憲民主党も事実上「負けに等しい」結果だったと述べ、「歴史のある政党がみんな揃って負けたな」という印象だと語った。
政治不信とネット選挙の影響
既存政党が軒並み苦戦した背景には、政治不信があると感じるかと問われると、鈴木氏は「政治不信は間違いなくあります」と断言する。そして、この政党の世代交代、特に新興政党が大きく勝った要因として、「ネットの影響は絶対に外せない」と力説した。
投票日の出口調査では、投票する際に選挙に関するSNSや動画サイトの情報を「重視した」人が「5割」に達したという。これは昨年の調査で3割程度だったことを考えると、「そんなに上がったんですか」と驚かれるほどの増加だ。この2、3年でネット選挙の影響がものすごい大きくなったのが全体のトレンドだと指摘する。
さらに、その影響は投票行動に明確に現れている。SNS情報を「重視した層」と「重視しなかった層」とでは投票先が全く異なり、「自民党、公明党、立憲民主党、共産党、そして社民党、全部あるんですけど、全部重視した層ではやっぱりポイントが低くなっていて」逆に「重視しなかった層ではやっぱポイント高くなってる」というデータがあるという。「ネットの中でやっぱりはっきり負けている」ことが顕著に現れていると分析した。
一方で、国民民主党、参政党、れいわ新選組、そして日本保守党といった新興政党は、軒並み「ネットの方が非常に強い指示を得ていて」、ネットの影響力が上がったからこそと語った。
年代別の比例投票先を見ても、その傾向は明らかだ。「自民党、公明党、立憲、共産、それから社民が高齢世代に偏っている」。対して「若い世代は国民、参政、れいわ、そして保守辺りを熱く信じてる」というのだ。これにより、若い世代や現役世代が新興政党を支持し、高齢世代が支持する伝統政党はネットの影響力増大とともに支持を減らしているという全体構造が浮き彫りになったと述べた。
若年層の投票率向上とネットメディアの役割
「若い世代は投票に行かない」という通説がある中で、今回の選挙では投票所に若い人が多かったという感想が多く聞かれたことについて、鈴木氏は「私は間違いないと思ってます」と語る。投票率は基本的にメディアの報道量と選挙が激戦かどうかで決まるというが、近年はネットメディアの情報伝達量も要因として加わっているという。
NHKの事前調査では「明らかに若い世代の投票傾向が増加してる」というデータがあり、SNS上の情報が選挙において活発になっていることとの相関は確実だという。「若い世代の投票率向上っていうずっと社会問題だったものがですね、ネットの影響によって解決に向かいつつある」と、ポジティブな側面を指摘した。
ネットメディアには偏った情報があるという懸念に対しては、「マスメディアとネットのメディアっていうのは補完関係にある」という見解を示した。マスメディアは公平中立であるがゆえに深掘りした情報が出しにくい一方、ネットメディアは中立ではないかもしれないが「深い情報が知れたりする」と語る。それらが「ミックスされた形で選挙情報が有権者に届くってのは私は決して悪くないことだなと思ってます」と述べ、双方の利点を活かした情報収集が重要だとした。
各党の評価:自民党の敗因と立憲民主党の伸び悩み
自民党の大敗要因
自民党の大敗の要因は主に4つに分解できると鈴木氏は分析する。
- ネットの影響力拡大:自民党に関連するYouTube動画は再生回数が多くても「ほとんどがネガティブ動画」だという。選挙期間中の調査では、自民党関連の上位100本の動画のうち「93本ネガティブで」、「7本が中立でポジティブは0でした」と衝撃的な数字を明かした。これにより、自民党のネガティブ情報が有権者に届き、マイナス影響を与えているという。
- 保守層の離反:保守層が保守党や参政党に流れたことは間違いないと指摘する。
- 物価高騰と政権運営:世界的な物価高騰は政権運営に逆風となり、選挙に影響を与えたという。
- 政治不信:自民党の政党支持率は2012年の政権復帰以来35%から40%を推移してきたが、「2023年の11月の裏金問題で一気に落ちて、そこから2年ぐらいずっと上がってない」というのだ。政治資金問題がきっかけでベースの支持率が10%落ちており、これが「一番大きい要因」だと結論付けた。この10%の減少は「めちゃくちゃ恐ろしいこと」であり、一度離れた支持が取り戻せない状況にあるという。
実際に、「長年自民党を支持してきた人が『今まで自民党に言ってほしいと思っていたことを、参政党であり保守党が言っている。だから私はもう支持しません』という人が何人もいらっしゃいました」と、具体的な事例を挙げた。
立憲民主党の伸び悩み
立憲民主党が伸び悩んだことについては、「立憲民主党の政党支持率ってそもそも10%後かない」と指摘する。自民党の支持率が25%ある上に公明党が乗ることを考えると、元々厳しい状況だという。
民主党時代から「3対6対9の法則」という、自民党に競り勝つための法則があったことに触れ、自らの支持層を固めるだけでなく、無党派層の6割、自民党の3割を削る必要があったと説明した。しかし今回は、無党派層を参政党や国民民主党に奪われ、自民党の支持層も同様に奪われたため、「立憲が伸びなかった」と分析した。比例投票先を見ても、「第2位が国民主党で、第3位が参政党で、立憲民主党は第4位」であり、政党支持率として上がっていない状況が明確になったと語った。
多党化する政治と「調整役」の必要性
鈴木氏は、この10年、特に民主党政権が終わってからを振り返ると、「政党の統合は事実上無理」だと考えているという。日本の政治が「複雑になってしまっている」ためだ。昔は保守と革新というシンプルな軸で良かったが、今はあらゆる個別政策で軸が異なり、参政党のように「自民党の層だけじゃなくて、立憲の層も削っているし、れいわの層も削ってる」政党も現れている。このような複雑な対立軸の中では、政党の統合は難しいとし、法案ベースでの協力はあり得るかもしれないが、政権を共に担うのは困難だろうとの見方を示した。
今後はさらに「多党性になっていく」と予測し、3党、4党、5党による政権の可能性が高まるだろうと語る。そうなると、多様な考え方を持つ政党が協力する上で、「調整役」となる政党が必要になってくるだろうと指摘した。
参政党躍進の3つの要因
参政党が伸びた要因は大きく3つに分解できると鈴木氏は分析する。
- メディア露出の増加:都議選での躍進がマスメディアで報じられ、その露出量が圧倒的に増えたこと。特に選挙直前に梅村氏が政党に優遇され、所属国会議員が5人になったことで、テレビの討論番組などに呼ばれる機会が増えたことが大きいと語る。
- 独自の政治的ポジション:参政党の主張は「トランプ政権のポジショニングと近しいもの」があると指摘する。反グローバリズム、反マスメディアといった主張や外国人問題への取り組みは、世界的に台頭する新興政党が捉えている潜在的な有権者のニーズを、参政党が早くから訴え、露出が増えたことで一気に受け入れられたという。
- 組織力と選挙戦略の巧みさ:特に「YouTube選挙のモデルを作ったのは参政党」だと評価する。2022年に初めて政党要件を満たした際に、切り抜き動画を積極的に活用して台頭したという。YouTubeやTikTokを含めた戦略のうまさは、新興政党の中でも「先頭に立っている」と語る。さらに、「今回の参院選で全選挙区に候補者を立てる」という地上戦の組織力を強調。熱量の高い党員が年間3万円の党費を払い、地域で組織を作り候補者を擁立していることが、風が吹いた時にそれを受け止められる構造だと分析した。
SNSでのネガティブキャンペーンが横行する中でも、参政党はむしろ支持者の熱量を高めたことについて、鈴木氏は「トランプと非常に近い属性を持ってる」ためだと解説する。政治不信やマスメディアへの不信感を抱く支持者にとっては、既存勢力からの批判が「反骨精神」となり、ネガティブキャンペーンが「全然効かなくてむしろ火をつけちゃう」現象が起きていたと分析した。
日本維新の会の健闘とチームみらいの「ブルーオーシャン」
日本維新の会については、「想定より比例は取ったな」という印象だと述べ、健闘したと評価する。これまでの維新の得票は、国民民主党や参政党が今回獲得した票を以前は維新が取っていたものだという。社会保障を重視した層からの支持は厚かったものの、物価経済対策に比べると争点としてのパイが小さかったため、全体情勢の中では伸び切らなかった側面もあると分析する。しかし、社会保障を2番手の争点として選んだ戦略は間違いではなかったとし、結果として比例で予測を上回る4議席を獲得したことは「検討した」と言えるとした。
チームみらいの躍進については、「私も難しいと思ってました」と、当初の予想は厳しかったことを明かす。しかし、蓋を開けてみると150万票を獲得したという。その要因について、現在の仮説として、「選挙戦って基本的には投票先未定の人たちが最後まで3割ぐらい残る」が、その多くは「現役世代の女性が圧倒的に多い」無党派層であると指摘する。今回の参院選では、女性から熱く支持される無党派層の受け皿となる政党が他に少なく、チームみらいが「ブルーオーシャンを取れて」最終版で伸びていったと分析した。安野氏自身も街頭演説で「現役世代の女性がすごい増えてった」と感じていたという。チームみらいの「分断を生まない」というコンセプトと、子育て政策の充実が、この層に響いたと見ている。今後も国政においてブルーオーシャンを取れる政党が他にあまりないため、チームみらいは「今後もっと伸びていくな」と期待感を示した。
民主主義の未来とテクノロジーの可能性
鈴木氏は、選挙制度や公職選挙法の抜本的な改革には時間がかかると認識している。「4年に1回の名前しか書けない今の選挙制度って民意を正しく反映できてない」と問題提起し、もし現代で民主主義をゼロから作り直すなら「絶対このシステムにならない」と語る。有権者の一票に込められた思いが分かりにくい現状を「致命的だ」とし、民意の解像度が低いことが根源的な問題だと指摘した。
しかし、選挙制度をすぐに変えるのは難しいからこそ、選挙ではない「通常の行政運営のプロセスにテクノロジーを入れていくことを考えるべき」だと提言する。パリ市のように、年間予算の一部を市民が直接事業提案し、投票で決めるような事例を挙げ、選挙という一度きりの機会ではない形で「いかに民意を政治にテクノロジーを使って反映していくかっていうもの」には、「非常に可能性ある」と語った。その意味でも、チームみらいがそれを最も実現できる政党だとし、注目しているという。
選挙ドットコム編集長の鈴木邦和氏の分析は、今回の参院選が単なる議席の増減に留まらず、日本の政治構造そのものに変化の兆しをもたらしたことを明確に示している。政治不信の深化、ネット選挙の影響拡大、そして既存政党の世代交代といった構造的な変化は、今後も日本の政治を多党化へと導くだろう。
はたして、テクノロジーが政治に与える影響は、鈴木氏が期待するように、国民が「自分自身で直接的に意見を表明できるようなシステム」を構築し、分断ではなく「みんなが政治の話をするの当たり前になっていく」社会を実現できるだろうか――。今後の日本の政治の展開、そしてテクノロジーが切り拓く民主主義の新たな形に、大いに期待したいものだ。

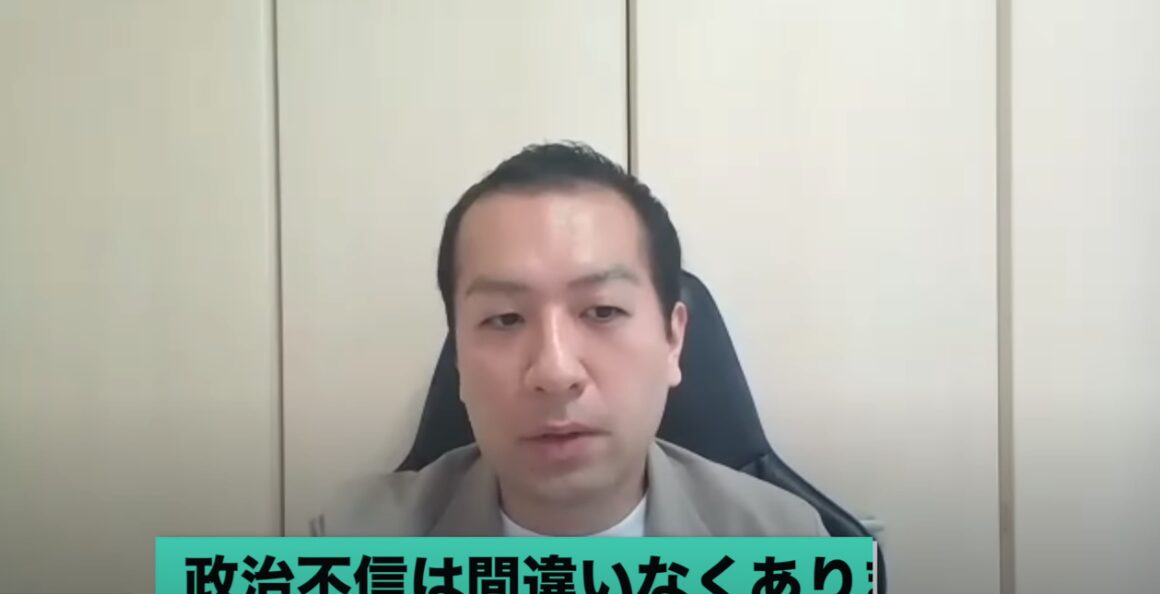


コメント