ジャーナリストの須田慎一郎氏は、8月中旬以降が濃厚とされる石破首相の退任後、自民党総裁選の行方を分析した。次期総裁選の方式が「両院議員総会」(簡易型)となるか、「フルスペック型」となるかが「今後の政局を占う上で重要なポイント」だと指摘。特に高市氏のような候補にとっては地方票が不可欠であり、「フルスペック型が望ましい」と述べた。有力候補としては高市早苗氏と小泉進次郎氏を挙げ、国民民主党が高市氏を「最も組みたい相手」と目していることにも触れた。自民党が衆参両院で過半数割れの少数与党に転落した現状では、新総裁は野党との協力・共闘が不可避であり、「誰が新総裁に選ばれるかによって、組む相手が変わり、日本の経済路線や社会のあり方が決まるため、総裁選の行方は非常に重要である」と強調した。
石破首相退任後の総裁選:方式が日本の未来を左右する
ジャーナリストの須田慎一郎氏は、8月中旬以降が濃厚とされる石破首相の退任後、自民党総裁選の行方と、それが日本の政局に与える影響について詳細な分析を行った。
石破首相の退任は、広島・長崎の原爆慰霊式典への出席、および日米韓税交渉の決着を見計らって、8月中旬以降が濃厚であるという。これは、1年前の岸田首相の辞任(8月13日)と類似したスケジュール感だ。
次期総裁選の方式は、今後の政局を占う上で極めて重要なポイントとなる。国会議員のみで新総裁を選出する「両院議員総会」(簡易型)か、国会議員票に加え、47都道府県に国会議員と同数の地方票が割り当てられ、地方での投票も行われる「フルスペック型」かだ。須田氏は、「どちらの方式が採用されるかは、今後の政局を占う上で重要なポイントとなる」と指摘する。特に、高市氏のような候補にとっては、地方票が重要になるため、「フルスペック型が望ましい」とされている。
次期総裁有力候補:高市氏と小泉氏の動向
次期総裁の有力候補としては、主に高市氏と小泉進次郎氏が挙げられる。昨年の総裁選の顔ぶれと大きくは変わらないと見られるが、林官房長官や加藤勝信財務大臣は、現在の「有事」とされる状況下では「役不足」と見なされ、有力視されていないという。
高市早苗氏は、明確な積極財政派だ。昨年の総裁選候補者の中でも、最も積極財政を打ち出している。支持基盤としては、国民民主党が「最も組みたい相手」と目されており、国民民主党が掲げる財政再建とは異なる要求(年収103万円の壁引き上げ、ガソリン暫定税率廃止など)に対し、高市氏が受け入れやすいとされている。しかし、自民党内の「長老連中」(ベテラン議員や派閥領袖クラス)からの受けが悪いという弱点が指摘される。この弱点を克服するためには、地方票が不可欠となるため、フルスペック型の総裁選を望むと推測される。物価高対策や外国人問題への明確な姿勢から、参議院選挙で自民党が票を失った層(賛成党が票を伸ばした層)からの支持が厚いと見られている。
一方、小泉進次郎氏は、財政再建路線(消費税減税に否定的、大規模な財政支出に否定的)であり、世論調査では高市氏に次ぐ支持を得ている。高市氏とは考え方が異なるのが特徴だ。その他、小林鷹之氏も積極財政的な方向性を示す数少ない候補の一人として挙げられた。
総裁選と野党との協力体制の行方
自民党が衆参両院で過半数割れの少数与党に転落している現状を踏まえると、新総裁は野党との協力・共闘が不可避となる。連立政権の形態としては、完全な連立政権か、政策ごとに協力相手を決め、自民党が譲歩する「パーシャル型」(部分的連立)が考えられる。
主要野党の動向も注目される。国民民主党は、石破体制との協力は「全くない」と明言している。昨年の「三党合意」(自民・公明・国民民主)で提示された年収の壁引き上げやガソリン暫定税率廃止が実行されず、「騙された」と感じているためだ。財政再建に前向きな要求(消費税減税など)を飲むハードルが高く、高市氏や小林鷹之氏を「最も組みたい相手」と見ている。
立憲民主党は、年金改革関連法案の可決・成立で自公と組んだ経緯がある。代表の野田佳彦氏は、年金制度安定化のためには将来的な消費税増税が必要との考えを持つため、積極財政派が総裁になると組むのが難しくなるとの懸念がある。
野党による連立政権の可能性については、「100%ない」と断言されている。国民民主党の玉木雄一郎代表によると、立憲民主党とは国家観や原発政策(エネルギー政策)において「水と油」であり、組むことは不可能だという。
須田氏は、「今後も自公が政権運営の軸となり、どの野党がどのような形で協力していくかが問われる」と結論づける。そして、「誰が新総裁に選ばれるかによって、組む相手が変わり、日本の経済路線や社会のあり方が決まるため、総裁選の行方は非常に重要である」と強調した。
総裁選に影響を与える主要課題と勢力
参議院選挙の敗因としては、最重要課題が「物価高対策」、第二の課題が「外国人問題」だと分析された。定住型外国人の増加によるゴミ出し問題、生活習慣の違いによる摩擦や恐怖感、オーバーツーリズムによる市民生活への影響(例:京都でのバス乗車困難)などが挙げられ、これが賛成党などの支持拡大につながったという。高市氏はこの問題に明確な姿勢を示すと期待されている。
財務省の意向も総裁選に大きな影響を与えるという。財務省は「増税を求める政治勢力」を「ポピュリズム」と位置づけ、その影響を軽減したいと考えている。地方票が結果を左右するフルスペック型総裁選では高市氏が選ばれる可能性があるため、財務省はこれを嫌う。財務省は、国会議員の多くが「弱みを握られている」あるいは「アメとムチで言うことを聞いている」両院議員総会での決定を望んでいる。
総裁選の複雑性について、須田氏は「自民党は「積極財政+保守」で行くのか、「緊縮財政+リベラル」で行くのかという重大な岐路に立たされている」と指摘する。総裁選の方式(フルスペック型か両院議員総会か)が、日本の将来の増税路線を決定づける可能性があり、非常に注目されるという。
須田慎一郎氏の分析からは、石破首相退任後の自民党総裁選が、日本の政治の行方を大きく左右する極めて重要な局面であることが鮮明に浮かび上がる。候補者の政策、野党との連携、そして総裁選の方式を巡る様々な思惑が複雑に絡み合う中、特に積極財政を掲げる高市氏と、長老議員との対立、そして財務省の意向が、総裁選の行方を大きく左右する要因となるだろう。はたして、自民党は国民の期待に応え、日本の未来を切り開く新たなリーダーを選出できるだろうか――。今後の展開から目が離せない。

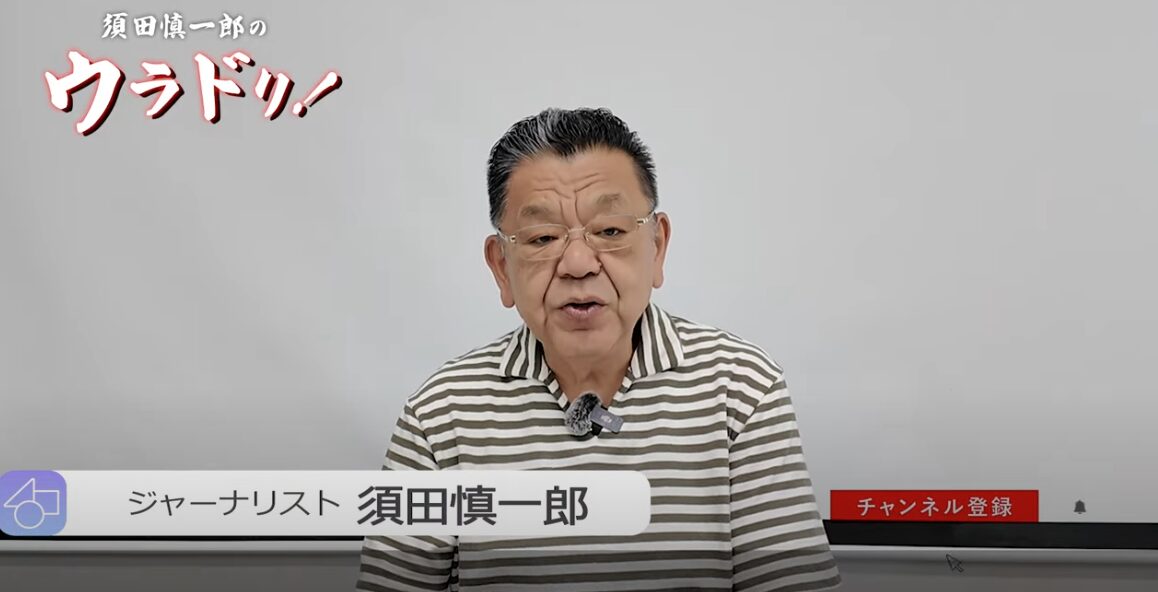


コメント