元テレビ局報道ディレクターの下矢一良氏が、選挙特別番組の知られざる舞台裏を解説する。通常の番組とは異なる特殊な制作体制、衆参選挙で変化する番組内容、そしてスポンサー不在の中で「億単位」の費用が投入される実態を語る。さらに、AIやSNSといった最新テクノロジーを駆使した各局の戦略にも言及し、番組をより深く楽しむための視点を提供する。
選挙特別番組の過酷な制作現場:報道局総動員体制の裏側
下矢一良氏は、選挙特別番組の制作が通常の番組制作とは異なる「特殊な体制」で行われることを明かす。民放各局では、選挙が決定すると「特別チーム」が招集され、社内の会議室を占有して準備を進めるという。このチームには、主に政治記者の経験を持つベテランスタッフが呼ばれることが多い。彼らは政治家との取材ルールやテロップ表記の細かいルールを熟知しているため、一から教える手間が省けるのだ。
NHKは民放とは異なり、「ずっと選挙だけ備えているチーム」が存在し、非常に手厚い体制で臨んでいるという。しかし、投票日当日(放送日)には、報道局員が「全員出動」してもまだ人手が足りないほどの「総力戦」となる。各議員の選挙事務所や各党本部からの生中継など、多岐にわたる中継に対応するため、人手はいくらあっても足りず、フル稼働の状態になるのだと下矢氏は語る。
衆参選挙で変わる番組の顔:ストレートニュースか企画物か
番組制作者の視点から見ると、衆議院選挙と参議院選挙の特別番組には明確な違いがあると下矢氏は解説する。
衆議院選挙は、総理大臣の解散宣言によって選挙日程が予測不能なため、準備期間が十分に取れないことが多く、制作側は「ハードになる」という。有名議員が多く、政権交代の可能性も高いため、視聴者は「結局結果どうなったんだよ」という情報に注目する。そのため、各局とも「ストレートに情報をバーンと伝える」傾向が強いのが特徴だ。石破総理や小泉進次郎氏、野党の党首など「有名人って大体衆議院議員」だと下矢氏は指摘する。
一方、参議院選挙は、有名な議員が少なく、政権交代が起こる可能性も「極めて稀」なため、結果への視聴者の関心は衆議院選挙ほど高くはないという。そのため、番組制作者は「色々こう企画を考えてね、それを見てもらうっていう傾向が強い」と下矢氏は語る。この点で「ストレートなニュースはNHKのほうが情報が多かったり正確だったりするところなんですけど、企画という意味ではテレ東が面白い」と評価される、企画と知恵で勝負するテレビ東京らしい傾向が出やすいのが参議院選挙の特徴だとされる。
スポンサー不在の「億単位」の出費:テレビ局の公共性への責任
選挙特別番組は、その性質上、通常の番組とは異なるスポンサー事情を抱えている。「選挙とか政治系の番組ってあんまり関わりたくないんですよ」という企業の意向により、選挙特別番組には基本的にスポンサーがつかないと下矢氏は明かす。これは、特定の政党の支持者からのクレームや、政治的な圧力とは異なる形で商品購入に繋がらないことを懸念するためだという。
スポンサーがつかないため、番組と紐づかない「スポットCM」が流される。しかし、「それでも選挙特番にスポットCMを流して欲しくないっていうスポンサーは多いので、普段のCMよりは流れてるCMのバリエーションは少ない」そうだ。
その一方で、選挙特別番組の制作には「めちゃめちゃ金かかるんですよ」と下矢氏は強調する。特に、報道局員が総動員される人件費は「えぐい」と表現され、出口調査などの費用もかさむ。各局によって異なるものの、「投票日8時以降のために億単位使ってんですよ」というから驚きだ。スポンサーがつかない一方で出費は膨大であるため、「テレビ局側は完全に持ち出し」となる。しかし、公共の電波を預かる報道機関としての責任として、これを実行しているのだ。
最新テクノロジーの導入:AIとSNSが選挙報道を変える
莫大な予算が投入される選挙特別番組では、普段はできないような「実験的な取り組み」が行われることも特徴だ。特に近年はAIとSNSの活用が目立つという。
下矢氏は、今年(2023年)の参議院選挙では、「ズバリAI人工知能、あとSNS」といった、テレビ業界が苦手とされてきたテクノロジーを各局が「積極的に打ち出している」点が共通の傾向だと語る。視聴者は「どの局がAIやSNSの活用の仕方がうまいか」という視点で比較することで、番組をより楽しめると下矢氏は提案する。また、どの局がどのIT/AI企業と組んでいるかを見るのも面白い点だという。
各局の具体的な取り組みとしては、NHKが「AIを導入」し、従来の「担当者の勘」に頼っていた情勢予測の精度が「上がってんのか」に注目だと述べた。日本テレビ(日テレ)は藤井キャスターと櫻井翔を二枚看板とし、SNSに焦点を当て、「フェイクニュース」の「事実確認」を行う機能や、独自の「あなたの政治的な意見はどの候補者とマッチするか」という「診断ソフト」を用意。さらに「縦長のスマホ画面で見やすい縦字幕」を用意し、若年層の視聴者を意識していると解説した。
TBSはNHKと競合する形で、「AIで選挙状況を開票分析をする」と打ち出し、「NHK対TBS」が見どころだと下矢氏は語る。フジテレビはAIは打ち出していないものの、SNSの「バズった度合い」と出口調査を重ねた独自の「熱量スコア」を導入している。テレビ朝日(テレ朝)はCG活用や「スマホ連携」を打ち出すが、AIのような「派手なもの」は少なめだという。
そして、テレビ東京(テレ東)は、投票日前から「政治100の疑問」特集を用意し、動画配信サービス「テルトビズ」との連動も行っている。他局より「半額以下の予算」と見られる中で「どうやって工夫して頑張ってくか」が見どころだと下矢氏は評価した。
選挙特別番組は、単なる開票速報に留まらず、各テレビ局が莫大な費用と人材を投じ、公共性への責任を果たすべく、様々な工夫と挑戦をしている番組であると下矢一良氏は解説した。特に近年はAIやSNSといった最新技術を積極的に取り入れ、テレビ報道の新たな可能性を模索する場となっている。私たちは、これらの制作背景や各局の特色、そして最新テクノロジーの活用方法に注目することで、これまで以上に番組を深く、そして多角的に楽しむことができるだろう。はたして、次回の選挙特番では、どのような新たな試みが披露されるだろうか?


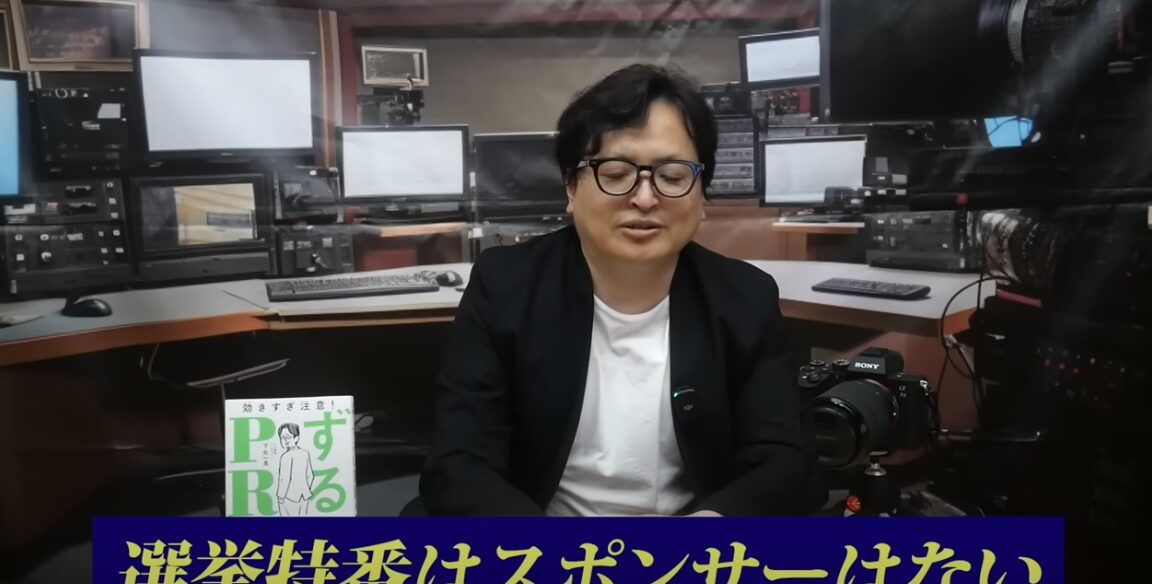


コメント