元テレビ局報道ディレクターの下矢一良氏が、週刊誌業界で「ほぼ一強」と言われる週刊文春の強さの秘密に迫る。「文春リークス」による情報収集の革新、早期のネット対応、そして「スクープ至上主義」のカルチャーが相乗効果を生み出し、盤石な地位を築いたという。しかし、その強さの裏には潜在的なリスクも潜んでいると警鐘を鳴らす。
「文春一強」を支える3つの革新的な戦略
下矢一良氏は、週刊文春が週刊誌業界で「ほぼ一強」と言われるまでに至った理由を3つの要因に集約して解説する。
第一に、「文春リークス」による情報収集の革新だ。週刊文春は2014年からこの情報提供窓口をいち早く開設し、一般からの情報提供を積極的に募った。これにより、従来の記者による人脈ネットワークに依存した情報収集では難しかった、「一期一会」の情報収集が可能になったという。記者との個人的な関係に縛られず、忖度のない情報が幅広く集まるようになり、これまでアクセスできなかった業界や分野からの情報も一気に文春に集まるようになったと下矢氏は指摘する。その効果は、中居正広氏のスクープにおいて顕著で、他誌が「中居正広、危機乗り越えた」と報じる中、文春は「中居9000万円女性トラブル」といった踏み込んだ見出しを掲げることができたのだ。
第二に、早期かつ積極的なネット対応が挙げられる。週刊文春は週刊誌の中でも最も早くネット進出を果たした。下矢氏は、「うちは紙と一緒に死にますよ」とまで他誌が言っていた時代に、文春は電子版を積極的に展開し、現在では「月間4億~5億PVを誇る体制」を築いていると語る。さらに驚くべきは、電子版を紙よりも1日早く(木曜発売の紙に対し、水曜公開)配信するという大胆な決断を下したことだ。これは社内の販売部門や書店・コンビニエンスストアからの反対を押し切っての英断であり、読者への「最速」提供を優先した結果である。紙の売り上げが減少する中でも、電子版がそれを補い、収益を維持・拡大しているという。
第三は、「スクープ至上主義」のカルチャーである。週刊文春は、創刊当初から「スクープ至上主義」のカルチャーを築いてきた。他誌が文章の技巧や切り口の工夫に重きを置くのに対し、文春は情報自体のインパクト、すなわち「田中K不倫」のような強力なスクープを追求する姿勢が根付いていたと下矢氏は解説する。このカルチャーは、情報が即座に共有されるネット時代において、「お金を払って記事を全部読む人が少ない」現代の読者層に非常にフィットしており、見出しのインパクトで読者を惹きつけることに成功しているのだ。
強さの好循環と盤石な経営基盤
上記の3つの要因が相互に作用し、週刊文春は「強さがさらに強くなる」という好循環を生み出していると下矢氏は指摘する。
ネット対応による収益増が、豊富な取材体制への投資を可能にしている。週刊文春の編集部員は「60人体制」であり、これは他の週刊誌と比較して「破格の人数」であると下矢氏は述べる。これにより、多くの記者が取材に専念できる環境が整っているのだ。
また、週刊文春は他の週刊誌と比較して広告費への依存率が低いとされる(数千万円レベル)。これにより、広告主への「忖度」が少なく、より独立した報道が可能となっているという。
さらに、安定した収益基盤があるため、「かかってこい」と言えるほどの財務基盤を確立している。他誌であれば訴訟費用で経営が立ち行かなくなるリスクがある中でも、文春は訴訟を恐れずに強気な報道を続けられるのだ。
盤石ではない未来?潜む3つの「落とし穴」
しかし、下矢氏は、週刊文春にも長期的に見て「盤石とは言えない」3つの潜在的なリスクを指摘する。
まず、名誉毀損に対する法制度の厳罰化である。現在の日本の名誉毀損に対する賠償金は100万円から200万円と安価であり、文春にとっては記事が売れることによる利益が賠償金を上回るため、リスクが低い。しかし、「名誉毀損の罰が軽すぎる」という世の中のトレンドが続き、将来的に法制度が改正され賠償金や罰金が大幅に引き上げられた場合、現状の「裁判上等」の姿勢を維持することが困難になる可能性があるという。
次に、過度な取材による犠牲者の発生と世論の変化が挙げられる。週刊文春の記事には、政治資金問題のような「公益性」の高い記事と、芸能人の不倫のような「エンタメ性」の高い記事の両方がある。後者のエンタメ性の高い記事において、文春の「ご報道」や過激な取材が原因で、対象者が社会的生命を奪われたり、自死に至るような悲劇的な事態が発生した場合、世論の風向きが大きく変わり、週刊誌の存在意義自体が問われる可能性があると下矢氏は警鐘を鳴らす。過去には「FOCUS」などの週刊誌が過激な取材で世論の支持を失い、廃刊に至った事例もあり、文春もその二の舞になる可能性は否定できないと述べる。
最後に、「文春砲」というブランドによる自縄自縛のリスクである。「文春砲」という期待とブランドが、編集部や記者に「今週も大スクープを出さなければ」という過度なプレッシャーを与えている可能性があると下矢氏は指摘する。このプレッシャーから、本来であればもっと丁寧な取材が必要な場面で無理な見出しをつけたり、強引な取材や結論付けを行ったりする傾向が徐々に見られるという(例:フジテレビ問題での橋下徹氏からの指摘による記事修正)。このような無理が続けば、記事の信頼性を損ね、結果的に読者離れを引き起こす可能性があるのだ。
週刊文春の圧倒的な強さは、「文春リークス」による情報収集の革新、早期かつ積極的なネット対応、そしてスクープ至上主義という独自のカルチャーが巧みに融合し、好循環を生み出した結果であると下矢一良氏は解説した。これにより、豊富な取材体制、低い広告依存度、そして訴訟への耐性という盤石な経営基盤を築き上げた。しかし、その輝かしい成功の裏には、名誉毀損に関する法制度の厳罰化、過度な取材による社会的犠牲者の発生、そして「文春砲」というブランドによる自縄自縛といった潜在的なリスクも抱えている。これらは短期的に顕在化する問題ではないものの、長期的な視点で見れば、文春の強さを揺るがす要因となり得るだろう。今後も週刊文春がその地位を維持できるか否かは、これらの潜在的なリスクにいかに対応していくかにかかっている。


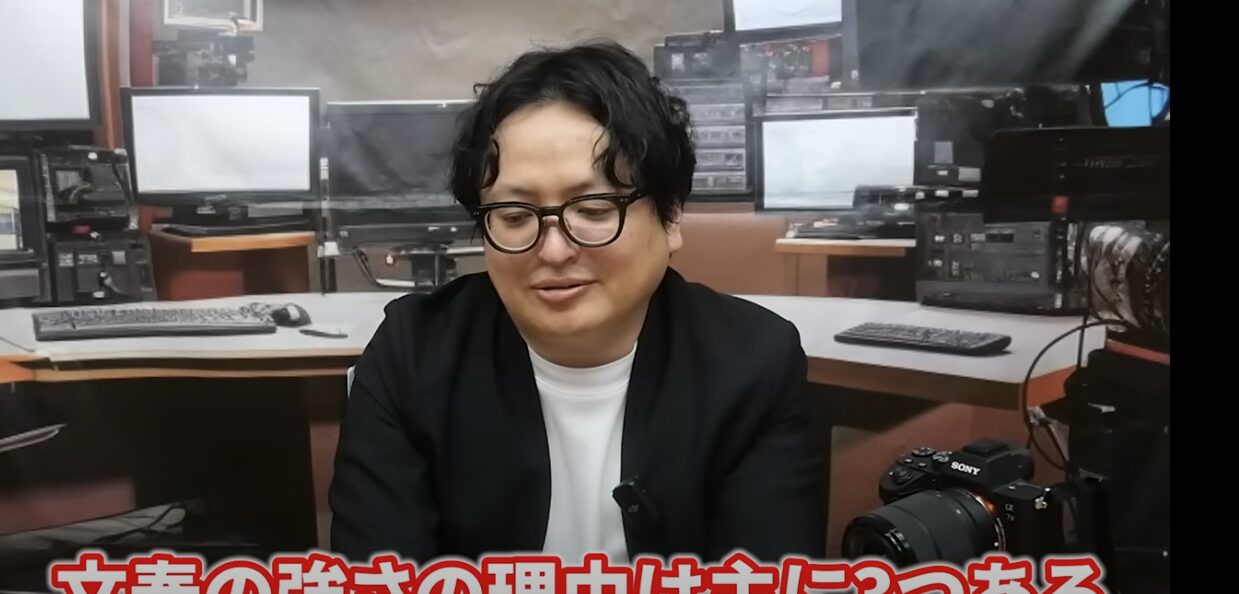


コメント