作家の佐藤優氏は、日本に統一的な中央情報機関は存在せず、内閣情報調査室が「非常に強力な組織」としてインテリジェンスの中核を担う実態を語る。しかし、その強みは「優秀な分析官たちの活動」など個々の人材に依存しており、「割り箸を刺して氷山を支えている」ような脆い構造だと警鐘を鳴らす。持続可能な組織とするためには、「情報職を作らないとだめ」と提言した。
日本の主要インテリジェンス機関とその特徴
佐藤氏によると、日本にはCIAやMI6のような統一的な中央情報機関は存在せず、複数の省庁がそれぞれ情報収集を担っているという。
公安調査庁:潜入の伝統
公安調査庁は、旧陸軍中野学校の伝統を受け継ぎ、潜入による情報収集に強みを持つと佐藤氏は語る。「陸軍中野学校なんかの伝統を組んでるのは公安調査庁ですからね。ここは潜入していい情報取ってますよ」と評価する。しかし、積極的な情報活動を行うため、時には中国などでトラブルが発生することもあるという。「色仕掛けてるから時々摘発されて、中国あたりでトラブルが起きる」と、その活動の一端を示唆した。
警察(公安警察):世界トップクラスの防諜能力
警察、特に公安警察は、カウンターインテリジェンス(防諜)において「警察はカウンターインテリジェンスとして世界一の力持ってる」と絶賛する。その能力は世界トップクラスだという。
外務省:弱体化する情報部門
かつて外務省には国際情報局があり、一定の情報収集能力を有し、各国情報機関との交流も活発だったと佐藤氏は振り返る。しかし、自身の事件を示唆するように、過去の事件を機に「情報は危険だ」という認識が広まり、国際情報局が格下げされ、領事局が強化されたという。「あの時は国際情報局というのがあって、外務省それなりに情報を持ってるっていう」状況から、「情報は危険だと。正しい情報を持ってると自分たちが思う通りの政策ができない場合がある」という考えが広がり、「国際情報局を国際情報統括感想者に格下げしたんですね。あれ情報いらないっていうメッセージなんです」と述べ、情報部門が徐々に弱体化している現状を指摘した。
内閣情報調査室(内調):日本のインテリジェンスの中核、しかし課題も
現在、日本のインテリジェンスの中核を担うのは、内閣情報調査室(内調)だと佐藤氏は語る。非常に強力な組織であり、国内外のあらゆる情報源をフラットに扱い、分析官が真偽を見抜くという。「内閣ってのは面白いとこで各国情報機関から秘密情報取ってくるでしょ。新聞記者の話、色々情報持ち歩いてるような人の話、週刊誌の話、スポーツ新聞の話、全はフラットなの。それで分析官が本物だと思ったものを内閣情報調査室長― 要するに内閣情報官に渡して、それが安保局長、総理のとこに行く。全部フラットに見て何が真実か」と、その情報収集と分析の手法を説明した。
特に、小林良樹氏(元高知県警本部長、内調で国際テロ担当)の活躍を高く評価しており、「国際テロリズムに関して一度も日本は間違えなかった。これ小林さんの判断が正しかったから」と述べ、日本が国際テロやウクライナ戦争で情報判断を誤らなかったのは、内調の優秀な分析官たちの功績が大きいと評価している。
しかし、内調には大きな課題もあるという。その強みは個々の優秀な人材に依存しており、システマティックな組織ではないというのだ。「優秀な分析官たちの活動によるもので、システムはきちんとしてないんですよ」と指摘し、現在の状態は「割り箸を刺して氷山を支えている」ようなもので、個々の人材が欠けると脆い構造だと警鐘を鳴らした。
日本におけるインテリジェンスの課題と人材育成への提言
佐藤氏は、日本におけるインテリジェンスの最大の課題は、統一機関の不在と人材育成にあると語る。
統一機関の不在と「政策と情報の分離」の建前
CIAやMI6のような統一的な中央情報機関がないことが議論の対象となっているが、佐藤氏はこれはインテリジェンス文化の問題であり、容易には変わらないと見ている。また、アメリカの教科書に書かれている「インテリジェンス・サイクル」や「政策と情報の分離」は、あくまで建前であり、実際には情報が政策を決定すると指摘する。「教科書を守ってるのは下っ端のインテリジェンスオフィサーだけです。上の方に来るとみんなくっついちゃってます」と、現実との乖離を明かした。
人材育成とキャリアパスの欠如
内調の最大の課題は、優秀な個人に依存しており、システマティックな人材育成やキャリアパスが確立されていないことだと指摘する。持続可能な組織とするためには、公務員採用区分に「情報職」を新設し、専門的な教育を行う必要があると提言した。「公務員の採用区分で情報職を作らないとだめ」という。
インテリジェンス担当者に求められる精神性についても言及し、「世直し型」の正義感が強すぎる人物はインテリジェンスには向かないという。「正規が強すぎるのはダメなんです。世直し型の人はインテリジェンス向かないんです」と語る。また、「お国の為だからやってくれ」と頼まれた際に、上司が高級なランチを奢ってくれる場合は要注意であり、最終的には「はい、やります」と言える覚悟が求められるという。
戦前の「秘密戦」とその現代的意義
戦前の日本陸軍参謀本部第2部(情報担当)が「秘密戦」を4つに分類し、実践していたことは、現代のインテリジェンスにも通じる概念だと佐藤氏は語る。
- 諜報: 相手に知られずに情報を取得すること。「相手に知られないようにして相手の情報を取ってくる」
- 防諜: 情報を守ること。
- 積極防諜: 偽の情報を流したり、偽のターゲットを見せたりして、相手を欺瞞すること。「偽のターゲットー ここに隠したいものがあるんだって大して隠したくないようなものを相手に取らせるっていう形で相手を欺瞞する」
- 宣伝: 自国の弱点を隠し、強みを誇張して、相手に誤った評価をさせること。「弱いところを極力隠して、強いところを過大に見せて相手に評価をさせる」
そして、これら3つの欺瞞手法を組み合わせて、「実力以上の成果を出す」ことが「謀略」だと定義する。陸軍中野学校の「謀略の心は誠」という教えは、相手を納得させるような「誠実な」謀略でなければ成功しないという考え方を示しているという。「謀略とは何かって言うと実力以上の成果を出す」「謀略の心は誠だと言うんだから相手にとって本当にいいと言って相手を納得させるような謀略しか成功しない」。
情報収集において最も重要なのは、情報提供者が「信頼できる」人物であることだ。その人物の考え方を参考にすることが、質の高い情報を得るためのノウハウであると佐藤氏は締めくくった。「この人が言ってることが信頼できるっていう人を捕まえて、その人の考え方を基本的に参考にすること」。
佐藤優氏の解説は、日本のインテリジェンスが、内閣情報調査室を中心に優秀な個人の活躍によって成り立っている現状を明確に示した。しかし、その持続可能性には大きな課題を抱えているのも事実だ。はたして、システマティックな人材育成と情報専門職の創設、そして外務省の外交官養成のような実践的かつ長期的な教育システムの導入は実現するのだろうか――。そして、戦前の「秘密戦」の概念が現代の情報活動にどう活かされていくのか、今後の日本のインテリジェンスの進化に注目したいものだ。

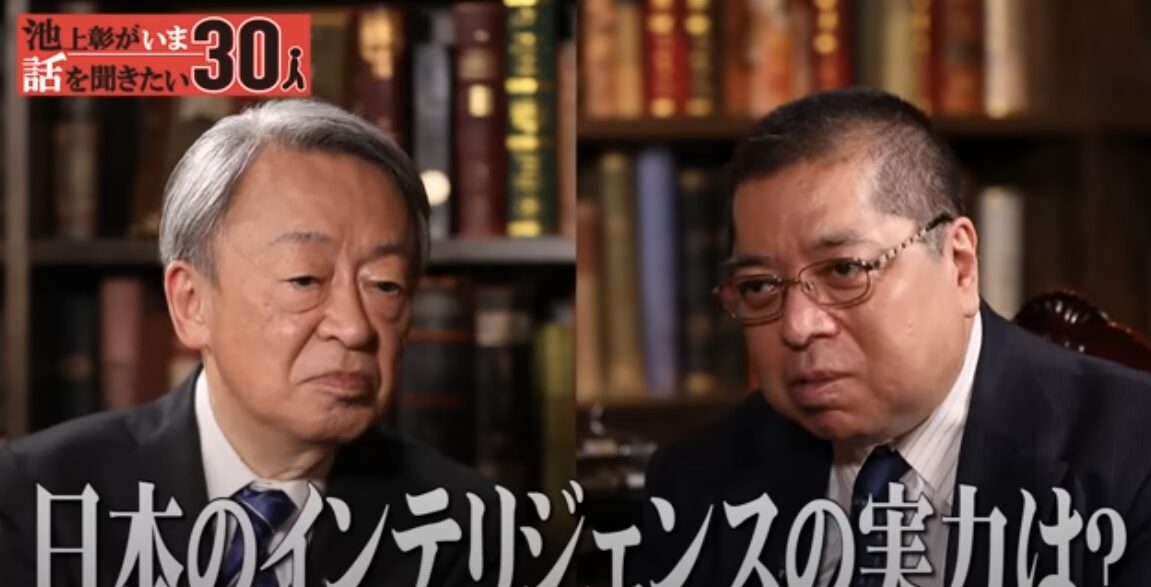


コメント