2025年7月11日、選挙ドットコム編集長の鈴木邦和氏が、参議院選挙の最新分析を語った。今回の参院選はネットの影響力がこれまで以上に拡大し、特に「参政党」の躍進と「自民党」の苦戦が顕著だ。また、伝統的な「公明党」の弱体化も指摘されており、自公が過半数を割る可能性は7割に上ると分析している。
ネットの影響力拡大と「参政党」の躍進
今回の参議院選挙で最も注目すべきは、ネット(SNSや動画サイト)の影響力だ。東京都知事選挙の出口調査では、SNSや動画サイトを重視した有権者が4割を超え、彼らの投票行動に明確な優位性が見られる。鈴木氏は、「再生の道に14%も入れてる」と、ネット重視層における「再生の道」への高い投票率を指摘した。最も参考にした情報としてSNS・動画サイトを挙げた有権者は17%、ニュースサイト・アプリを含めると30%を超えているという。
候補者側もこの変化に対応し、参議院選挙の全候補者の7割がSNSアカウントを開設している。YouTubeでの選挙関連動画の再生回数は、公示後6日間で2.5億回に達し、その9割以上が第三者によるものだ。特に「切り抜き動画」やネットメディアの動画が主流となっている。
このような状況の中、「参政党」が目覚ましい躍進を遂げている。公示後6日間のYouTube再生回数データでは、賛成党関連動画が1億回を超え、2位の自民党(6000万回)を大きく引き離している。その背景には3つの理由があると鈴木氏は分析する。
- 都知事選での議席獲得によるメディア露出の増加:都知事選で4人中3人が当選したことで、マスメディアでの報道量が急増。「地下アイドルだったのが出てきた」ような状況だと鈴木氏は例える。
- トランプ大統領と近い政治的スタンス:「反マスメディア、反グローバリズム、ワクチン政策への姿勢など、かなりトランプと近い」政策やスタンスが、グローバリズムの歪みに焦点が当たる中で有権者に受け入れられている。「日本人ファースト」というキャッチコピーも分かりやすいと評価されている。
- 卓越した選挙戦術:YouTube選挙の原型を作り、切り抜き動画を組織的に活用するなど、ネット戦略が最先端を行っている。加えて、各地域に支部を作り党員を増やし、候補者を全国に擁立するなど、伝統的な「地上戦」も非常に上手い。「旧来的な選挙のやり方と最新のネットのハイブリッド」が参政党の強みであり、元自民党出身の神谷氏の政党運営の手腕が大きく貢献していると鈴木氏は分析する。
「自民党」の苦戦と「公明党」の弱体化
自民党関連動画のYouTubeでの上位100本のタイトルを見ると、93本がネガティブな内容であり、ポジティブな内容はゼロだ。「コメント欄もネガティブなものしか出てこない」と鈴木氏が語るように、自民党へのネット世論は極めて厳しい。他党の関連動画でも自民党は「ヒール役」として登場することが多く、ネット上で大量の「ネガキャン」が貼られている状況だ。かつてネット戦略に長けていた自民党だが、X(旧Twitter)やYouTubeといったプラットフォームの変化のスピードに追いつけていないことが、この状況を招いている。
一方、公明党は今回の参院選で大幅な議席減が予測されている(改選前14議席に対し、予測は6~11議席)。弱体化の理由は大きく2つ挙げられる。
- 支持層の高齢化による地盤沈下:公明党は創価学会員による票だけでなく、学会員が友人に働きかける「フレンド票」に支えられてきた。しかし、支持層の高齢化により、「学会員の方が1人亡くなってしまうとか選挙活動ができなくなってしまうと、票としては3票から4票減る」という構造的な問題がある。東京都議会議員選挙では、4年前と比較して得票を2割以上減らしており、この地盤沈下が急速に進んでいる。
- 調査精度の低下:公明党の選挙戦術は、高い調査精度に基づき、危ない選挙区に資源を集中させることで成り立ってきた。しかし、ネットの影響力拡大により、当選ラインが読めなくなったり、フレンド票の読みづらさが増したりしている。鈴木氏は「公明党のその基本戦術は今狂ってる」と指摘した。
参議院選挙の予測と今後の連立政権
今回の参議院選挙の最大の焦点は、自民党と公明党で過半数(改選部分で50議席)を維持できるかどうかだ。現状の予測レンジ(自民党と公明党合わせて41~53議席、中央値47議席)から、鈴木氏は「自公過半数割れの確率は7割」と見ている。自民党の議席予測は35~42議席で、「戦後最低の36議席を下回る可能性すらある」と鈴木氏は語った。立憲民主党は議席を伸ばす見込みであり、自民党と議席をシーソーゲームのように分け合う形になるだろう。複数区では公明党、国民民主党、参政党が競り合っており、公明党の議席減が国民民主党や参政党の議席増に繋がる可能性がある。
自公が過半数割れした場合、自公のみの連立政権は事実上終焉すると鈴木氏は分析する。「今回取れなかったらこの先無理」だからだ。今後の連立の構図は大きく3パターンが考えられる。
- 自公+国民民主党:最も可能性が高いとされている。自民党にとって公明党を切るメリットは小さく、公明党との関係を維持したまま、国民民主党との連携を深める可能性が高い。
- 自公+維新の会:維新の会と公明党は大阪での対立が激しく、公明党が維新に強い恨みを持っているため、連立成立のハードルは高い。
- 自公+立憲民主党:政策的な距離があり、実現可能性は低い。
野党間の連立政権は、衆議院での過半数に達しないため、解散総選挙がない限りはほぼ不可能だ。
石破首相の去就と次期総裁候補、そして政策決定への影響
自公が過半数割れした場合、石破首相は退陣表明せざるを得ないと見られている。その後、自民党総裁選が行われることになり、次期総裁候補としては高市早苗氏と小泉進次郎氏が本命視されている。次期総裁選は党員投票を含めたフルパッケージで行われる可能性があり、衆議院選挙で勝てる候補かどうかが重視されるだろう。
自公が過半数割れし、複数の政党が協力する形になった場合、野党ベースの法案が成立する可能性が高まる。特に消費税の減税(食料品)や大企業への課税強化など、複数の政党間で政策が一致する分野では、法案通過の可能性が高まる。「野党ベースの法案が通る可能性がある」のが、参院選後に起きる現象だと鈴木氏は語る。しかし、連立政権の形態によっては審議が遅れる可能性も指摘されている。
長期的な政治変動の展望
今回の選挙で起きている変化は、日本の政治史上、数十年ぶりの大きな変化だと鈴木氏は捉えている。ネットメディアの普及により、有権者の政治的価値観が多様化し、政党の支持層が細分化していることが背景にある。これにより、従来の二大政党制の志向が弱まり、多党化の時代に突入すると予測されている。特に、若年層の支持者がネット上で活発であり、彼らを中心に保守的なコンテンツへの関心が高いことから、政治的な「右寄り」の傾向が強まる可能性も指摘されている。また、今後は「外国人問題」や「ナショナリズム対グローバリズム」といった新たな対立軸が重要性を増し、政策論争の中心となる可能性が示唆されている。
今回の選挙結果は、日本の政治が不安定になる一方で、これまで実現が難しかった政策の可能性も広がるだろう。はたして、私たちは政治の大きな転換期を目の当たりにしているのだろうか。


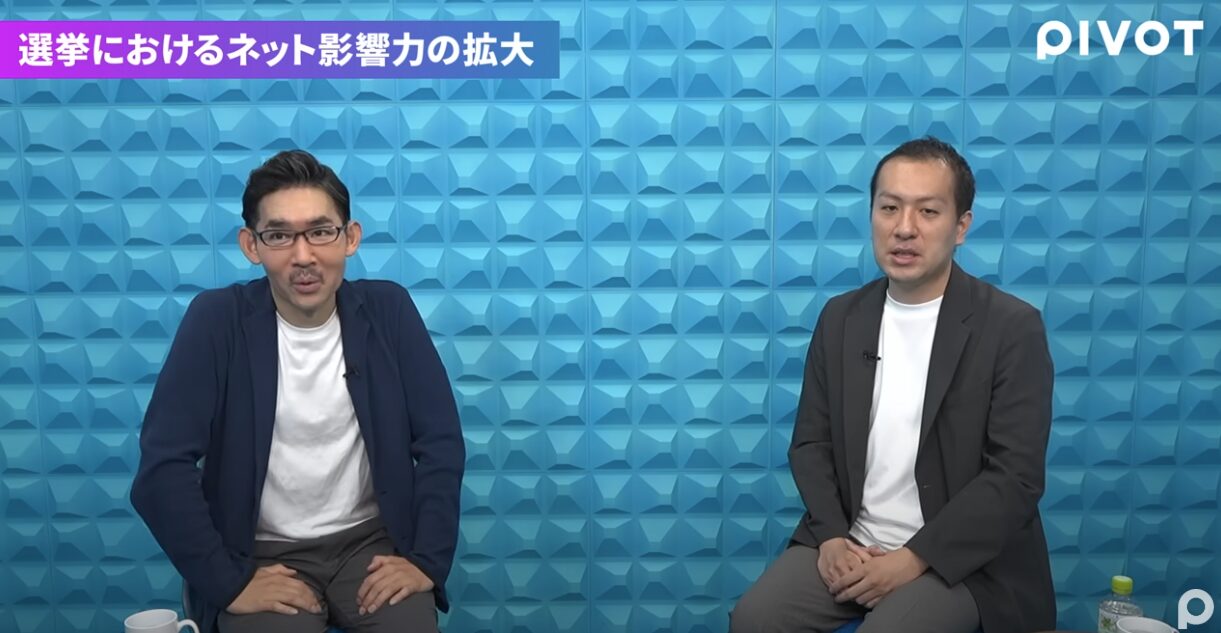


コメント