政治ジャーナリストの鮫島浩氏が、参議院選挙で注目を集める参政党の躍進について詳細な分析を展開する。参政党が掲げる「日本人ファースト」という言葉が有権者の心に響いている背景には、既存政党やメディアへの強い不信感があると指摘。他の新党とは異なり、参政党が「党員獲得を最優先するリアルな草の根活動」を展開し、特に「3、40代の主婦層」の支持を得ている点を強調する。鮫島氏は、既存政党が参政党を「危険な極右政党」と位置付け「大連立で対抗する構え」を見せることが、「逆効果」であり、参政党の本質は「究極のポピュリズム政党」だと警鐘を鳴らす。
「日本人ファースト」が突き刺さる──参政党躍進の背景
参議院選挙で、参政党が掲げる「日本人ファースト」という言葉が、全国の有権者の心に深く刺さっていると政治ジャーナリストの鮫島浩氏は分析する。経済界やリベラル派が参政党を「政党と見なし警戒」し、自民党と立憲民主党が「反グローバリズムの高まりに大連立で対抗する構え」を見せているが、鮫島氏はこれは「逆効果」だと断言する。参政党を台頭させたのは「上からのイデオロギーではなく草の根ポピュリズム」であり、既存政党やオールドメディアが「結託して抑え込めば大衆の支持を得て益々躍進していく」と予測した。
既存政党の誤算──石丸氏、斎藤氏の事例から見る「一過性の嵐」論の危険性
昨年夏の東京都知事選挙で躍進した石丸慎司氏や、昨年秋の兵庫県知事選挙で大逆転した斎藤元彦知事の例を挙げ、鮫島氏は彼らが「オールドメディアを敵に回しながらYouTubeで支持を拡大」し、日本社会に衝撃を与えたと指摘する。「自民も立憲も嫌だ、テレビも新聞も信用できない」という、既存政党とマスコミに対する無党派層の「強烈な不信」が、彼らを時の人に押し上げた。しかし、現在の彼らには当時の勢いはなく、既存政党やオールドメディアの間には、今回の参政党旋風も「一過性の嵐に過ぎない」という楽観論が広がっているという。
しかし、鮫島氏はこれが「参政党の実像をあまりに知らない彼らの願望に過ぎない」と一蹴する。石丸氏や斎藤氏が「男性のネット民を中心に支持を広げ」、「リアルな組織を作り上げてこなかった」ために勢いが続かなかったのに対し、参政党は異なる戦略を取っているのだ。例えば、NHKから国民を守る党が42人を擁立して全員落選したように、ネット人気だけでは選挙に勝てないことを指摘する。
参政党の強み──「草の根」と「主婦層」
参政党は3年前の参院選で「神谷代表が比例で当選し国政デビュー」を果たした。旗揚げ当初は「かなり偏った主張が目立ち」、「カルトやキワモノとして警戒されてきた」が、路線対立で当初メンバーが離脱し、神谷代表が党運営を掌握して盛り返してきたという。
その原動力となったのが、「全国に地方支部を張り巡らせ党員獲得を最優先するリアルな草の根活動」である。毎月1000円の党費を払って参政党に加わる人々が「全国で急増」しており、「その中心は3、40代の主婦層」であると鮫島氏は強調する。
国民民主党の躍進がネットの男性支持者層が中心だったのに対し、参政党の神谷代表がターゲットにしたのはあくまでも「主婦層」であった。政策も「食の安全、子育て支援、そして急増する移民への不安」といった生活に根差したものが中心になり、主張も「徐々にマイルドになってきた」と分析する。
参政党は「草の根活動とSNS戦略で党費を払って一緒に活動してくれる党員」を増やしていった。候補者も「党本部のトップダウンではなく各地で党員たちが自分たちで決めていく」という草の根組織運営が、今回の参議院選挙で全選挙区に候補者を擁立する背景にあると解説した。
ポピュリズムの新潮流──既存政党とのズレ
鮫島氏は、本来政党が「党員獲得を通じて全国に党勢を拡大していく」べき姿であるにもかかわらず、日本の新党は「マスコミに取り上げられて風に乗ることばかりを重視し、党員獲得の努力を怠ってきた」ために次々に消えていったと指摘する。その中で参政党は「党員獲得に全力で取り組んで成功した初の新党」であると評価する。
「日本人ファースト」というキャッチコピーも、「神谷代表のトップダウンで打ち出したというよりも草の根活動を通じて人々が感じている不安、グローバリズムへの不信感を感度よくすくい上げた結果」だと見るべきだという。参政党は「イデオロギー政党ではなく究極のポピュリズム政党」であり、しかもそれは「ふわふわとしたポピュリズムではなく草の根ポピュリズム」だと強調する。ここを理解しないと「参政党旋風を一過性の現象と見誤ることになる」と警鐘を鳴らす。
自民党を見限り国民民主党に流れた保守層が参政党に流れ込んでいるのは事実だが、参政党の詳しい支持層は彼ら男性の保守層ではなく、「各地で草の根活動を続けている主婦層」であると改めて指摘する。
既存政党の動揺と「大連立」の思惑
参政党旋風の本質に最も気づいているのは「実は自民党」だと鮫島氏は語る。自民党が地域活動を徹底し、党員獲得に努めてきた経験があるためだ。ある保守王国の県議会議長が、立憲民主党以上に「恐れているのが参政党でした」と証言したという。その県では移民が急増し、「県民は毎日の暮らしに不安を感じている」ところに、参政党が若い女性候補を擁立し「日本人ファースト」を訴えている。一部の世論調査では「なんと立憲を抜いて2位へ踊り出ている」という驚くべきデータもある。
選挙区でも比例でも参政党は「自民票を確実に切り崩している」現状があり、今や自民党にとって「立憲民主党以上に潜在的な脅威になりつつある」という。岸田総理や自民党幹部が参政党を「危険な極右政党」と位置付け、その台頭を抑え込むことが「新たに大連立の大義名分に加わってきた」と鮫島氏は解説する。立憲民主党の野田義彦代表も、「日本人という言葉が歓迎される空気に危機感を感じる」と明言し、参政党の脅威論を煽っている。これは「自民との大連立の大義名分にするそんな思惑が滲んでいます」。現に、立憲を支持するリベラル言論の間では「石破政権を倒すことよりも参政党の対当を抑え込む方が優先だ」という声も上がり始めているという。
ヨーロッパの教訓と日本政治の行方
このような現象はヨーロッパ諸国で既に起きていると鮫島氏は警鐘を鳴らす。経済界が安い労働力を求め、リベラル派が人権重視の立場から移民政策を推進した結果、移民急増に不安を募らせる大衆が「移民反対の新興勢力へ流れていった」。これに慌てた中道右派と中道左派の既存政党は、進行勢力を「極右政党」と位置付け「連携して抑え込んだ」が、大衆はこれに反発し「益々新興勢力へ流れていった」という歴史を辿っている。日本も「同じ道を辿っているように見える」と語った。
参政党の台頭で「最も割を食ったのは国民民主党」だと鮫島氏は指摘する。両党は「右下のポジションを争っている」と政治マトリクスを用いて解説し、「勢いは参政党」であると断言する。国民民主党が「神谷代表のように吹っ切れて反グローバリズムの旗を高く掲げることができませんでした」という点が、参政党に追い抜かれつつある大きな要因だと指摘した。国民民主党は参院選の複数人区で参政党に激しく追い上げられており、「正念場を迎えている」という。
一方で、参政党との向き合い方が難しいのが「左下に位置するれいわ新選組」である。財政政策では同じ立場だが、左右のイデオロギーが異なる。令和新選組の執行部は、これまで自民・立憲の双方と戦う姿勢を示してきたが、今のところ参政党とも激突する方針のようだ。しかし、鮫島氏は「参政党と真っ正面から激突するのは選挙対策としては逆効果だ」と警告する。激突すれば「左右のイデオロギー対決の印象が強まり上下対決が薄れてしまう」ため、上下対決に持ち込めるかどうかが「れいわは大きな岐路に立っている」という。
参政党の躍進は、既存政党がこれまで見過ごしてきた有権者の不満や不安を巧みにすくい上げた結果である。特に「草の根ポピュリズム」と「主婦層」を基盤とした支持拡大は、既存の政治分析では捉えきれない新たな現象と言えるだろう。既存政党が参政党を「危険な極右政党」として抑え込もうとする戦略は、かえって有権者の反発を招き、さらなる支持拡大を招くかもしれない。日本政治は今、ヨーロッパ諸国が辿った「移民反対」の進行勢力への大衆の流出という道を歩んでいるのだろうか――。今後の政界の動向から目が離せない。


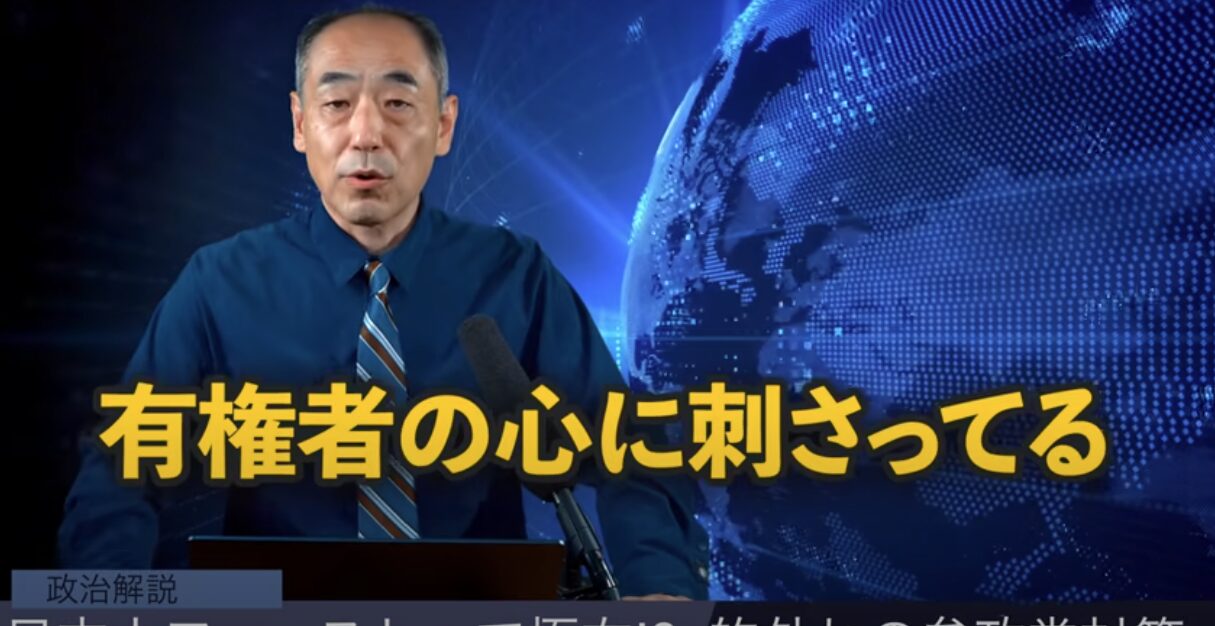


コメント