政治ジャーナリストの鮫島浩氏が、永田町を揺るがす「鈴木俊一自民党総裁・玉木雄一郎総理」という驚くべき連立構想について、その背景と二人の元総理の思惑を詳細に解説する。この構想は、夏の終わりから秋にかけての激動の政局を占う上で、重要な鍵を握る。
「石破降ろし、玉木総理」の密謀
鮫島氏によると、自民党の麻生太郎氏と岸田文雄氏が主導する「鈴木俊一自民党総裁・玉木雄一郎総理」という連立構想が水面下で進んでいる。この構想は、昨年、自公与党が過半数を割り「少数与党国会に陥った後」に、「石破を降ろし、玉木を総理に担ぐ自公国連立政権を模索」したことに端を発するという。
麻生氏は、かねてから国民民主党との連携を模索し、岸田政権時代には副総裁としてガソリン減税を巡る国民民主党との裏交渉を担ってきた。これは、ライバルである菅義偉氏に対抗し、公明党や維新以外の新たな連携軸を構築しようとする麻生氏の思惑があったからだ。
麻生氏の「高市リスク」回避と鈴木俊一の擁立
麻生氏の念頭にあるのは「高市リスク」だ。次期総裁選で高市氏が総裁になった場合、「立憲民主党は高市総理阻止のため野党連立政権に踏み切る可能性」があり、「自民党が野党に転落する高市リスクは過小評価できません」。麻生氏はこれを何としてでも避けたいと考えている。
そこで浮上したのが、麻生氏の義理の弟でもある鈴木俊一氏の擁立だ。自身の推す茂木氏の党内人気の低さや、小泉進次郎氏を推せば菅義偉氏がバックについている状況を鑑みた結果、岸田氏から鈴木俊一氏の擁立が提案された。
鈴木氏は麻生派の重鎮であり、財務大臣の座も麻生氏から引き継いでいる。両者は「大宏池会」と呼ばれた新派閥のメンバーであり、共にエリート官僚出身の主流派に対抗する「傍流」としての共通点がある。
しかし、鈴木氏が総裁になった場合、「あまりに麻生色が強く麻生傀儡のイメージは避けられません」。これは、内閣支持率の低下に繋がるリスクも指摘されている。
岸田氏の「深読み」と再登板への布石
一方、岸田氏は自身の総理再登板を目指しており、そのために麻生氏の支持が不可欠だと考えている。
石破政権誕生後、麻生氏が最も嫌う派閥解消を打ち出したことで一時決別したが、石破総理が林芳正氏を重用したことで、石田政権と距離を置き、「再び麻生太郎に接近」した。
岸田氏は「何としてでも麻生太郎のご機嫌を取り戻したい」という強い意志があり、そのために自身の再登板を棚上げし、「麻生太郎が一番喜ぶシナリオ」、つまり「麻生太郎がキングメーカーとして君臨できる体制」である「鈴木俊一総裁、玉木雄一郎総理」という連立プランを提案したという。
しかし、これは岸田氏の「深読み」かもしれない。鈴木氏が72歳であり総理になる可能性が低いこと、そして玉木政権が「盤石ではない」ため、「そう長く持たないだろう。遠からず自分にチャンスが巡ってくるはずだ」と読み、自身の再登板への足がかりとしたい意図がある。
実現への課題と懸念点
この連立構想には、いくつかの大きな課題と懸念点が存在する。
まず、鈴木俊一氏が総裁選を勝ち抜けるかどうかだ。一般党員も参加するフルスペックの総裁選では、「党員人気の高い高市や小泉進次郎が有利になる」可能性があり、「鈴木さんは大穴、決戦投票に残れない可能性」も指摘されている。
また、「総理の椅子を国民民主党に譲る」ことに対しては、「党内の反発は非常に強い」と予想される。鈴木氏が麻生氏の義理の弟であることから、「麻生傀儡」のイメージも強く、「内閣支持率に悪影響を与える」可能性も指摘する。
「石破総理を引きずり下ろし、その後に誕生する政権が麻生傀儡だ。これはあまりにイメージが悪い」と鮫島氏は語る。
夏から秋にかけての激動の政局
「石破退陣から自民党総裁選、そして連立協議、新内閣誕生」と、夏から秋にかけて政局は大きく動くと予想される。
この「鈴木総裁・玉木総理」連立プランは、現時点では「総裁レース序盤の観測の側面が強い」としながらも、麻生氏と岸田氏という二人の元総理が描くシナリオとして、今後の動向が注目される。
はたして、麻生太郎と岸田文雄の目論見通りに、この連立構想は実現するのだろうか。

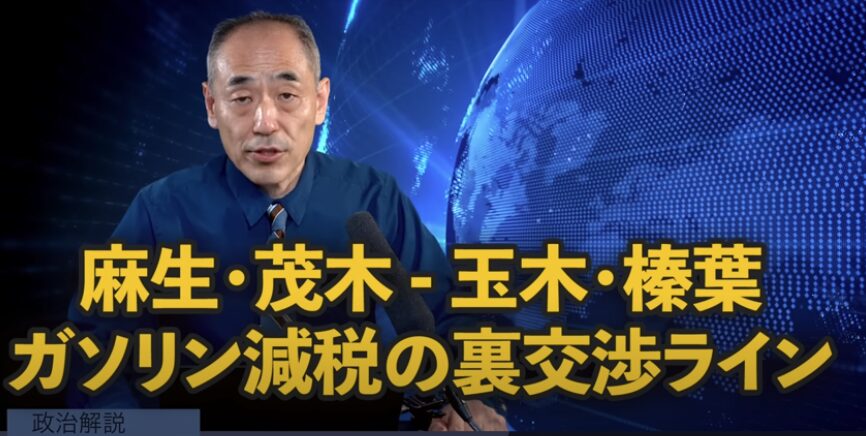


コメント