評論家の與那覇潤氏は、月刊正論2025年2月号で取り上げた「推し選挙」の問題について解説する。この現象は、都知事選や兵庫県知事選で起きた、特定の候補者への熱狂的な支持を指す。これはルールを守りつつも逸脱したいという現代社会の欲求を映し出していると指摘。民主政治が直面する新たな課題と、その危険性を深く掘り下げる。
「推し選挙」とは何か?──熱狂と逸脱のメカニズム
與那覇氏は、「推し選挙」を「何がなんでも私石丸さんがいい、斎藤さんがいいっていうなんか熱狂的なファンが演説会に殺到して番狂わせの成績を出してしまった」現象と定義する。特に、2024年夏の都知事選で2位に入った石丸伸二氏や、出直し再選挙で再選された兵庫県知事の斎藤元彦氏の事例を挙げ、本来であれば「何者なのかよくわかんない」あるいは「相当やばいパワハラとかやってたんじゃないのという疑惑があって」もかかわらず、有権者が「推しだからこの人に一票入れますっていう有権者が大量に出現した」ことで社会現象になったと説明する。
この「推し」という言葉は、2010年代初頭のAKB48ブームで生まれたという。AKBグループの「総選挙」は、CD購入に投票権を付与することで、ファンが「同じCD俺は10枚買った、俺は100枚買ったみたいな人」が続出し、特定のメンバーを応援する「推し」文化が確立された。與那覇氏は、このAKBの仕組みが「ルールを守りながら逸脱したいっていう」「今の日本社会で多くの人が抱いてる欲求に形を与えたものだった」と分析する。
かつては「社会的な逸脱行動」と見なされていた、アイドルの追っかけのような行為が、AKBの「総選挙」という「一定のルールを設けることで制度化しちゃった」のだ。これにより、「普通に異常でしょ」という行為が「あなたがやってることは正しいコンプライアンスを守ってるむしろ」という形で肯定され、安全に逸脱できる道が作られたという。この流れが、まさに現在の「推し選挙」へと波及していると指摘する。
例えば、斎藤元彦氏の再選時には、NHK党の立花孝志氏が「自分は当選する気ないけど斎藤さんを応援したいから出馬して選挙演説します」と表明し、「2馬力選挙」とも言われた。これは「明らかに異常な行動なんだけど少なくとも現状では違法ではない」ため、「取り締まることができない」と與那覇氏は解説する。人間が持つ「逸脱への欲求」を、「違法じゃないじゃないですか」という形で「安全に逸脱したい」という行動が、2020年代に入って様々な場所で顕在化していると分析する。
「革命できない」時代の安全な逸脱とSNSの台頭
與那覇氏は、人々が安全な逸脱を求める背景には、「革命できないから」という理由があると指摘する。20世紀までであれば「こんな世の中俺はもう嫌だって思っていたら革命するという道」があった。しかし、冷戦終焉とともに、革命が必ずしもより良い社会をもたらすとは限らないという認識が広まった。特に日本では、「露骨に破る人って少ない」という国民性があり、合法的に逸脱する道が模索されてきたという。
2010年代には、薬物依存の専門家である松本俊彦氏が指摘するように、ギリギリ合法な「危険ドラッグ」が流行した。しかし、近年はそれも下火になり、「ルールに乗っってますよね、違法じゃないですよねっていう実質的な危険ドラッグができた」と與那覇氏は語る。これは、ストロング系飲料のような「未成年じゃなければ別に買うことは完全に合法で」「飲むと食べるみたいな」形で、ルールを守りながら逸脱欲求を発散できるものが増えたことを指している。
このような状況下で、SNSの台頭が「推し選挙」を加速させている。SNSでは、特定の政治家や政党を支持する「推し活」が活発に行われ、まるで「YouTuberみたいになってきてる」と指摘されるほど、切り抜き動画などを通じた情報戦が展開されている。
「人に合わせて党を作る」民主政治の危機
與那覇氏は、「推し選挙」がもたらす危険性として、「それは逸脱欲求なんだからちゃんと認めないのは非常にまずい」と警告する。そして、民主政治が「人に合わせて党を作る」という傾向が強まっていると指摘する。
これまでは、「日本の民主主義が遅れてるんだ」「レベルが低いんだ」と言われがちだったが、アメリカのトランプ現象やフランスのマクロン現象など、世界的に「こう人に合わせて党を作るみたいな」動きが強まっているという。
この現象の根底には、有権者が「自分を代理することを求めてるから」という心理があると與那覇氏は推測する。つまり、特定の政策を実現してほしいというよりも、「俺になりかわって暴れてほしい」「俺は大したことない存在かもしれない。でもこの素晴らしい人を推している時点で俺にも価値がある」という欲求が存在するという。この心理は、宇佐見りん氏の小説『推し、燃ゆ』にも描かれていると述べ、遠くにいる偶像を推すことで自己肯定感を得るメカニズムが働いていることを示唆する。
日本社会の絶望と新たな選挙制度への模索
與那覇氏は、このような「推し選挙」の背景には、日本社会の「絶望」があると分析する。格差の拡大、氷河世代の放置、少子化の進行などにより、「絶望していく人が多い中で、押すっていうかそこがこう唯一の心の寄り所じゃない」かと語る。
アメリカのオピオイド危機とトランプ政権の誕生に触れ、日本でも「コンビニで事実上ドラッグ売ってますやんみたいな、こうマイルドに起きてる」ものの、アメリカ以上に「逃げ場がない」状況にあると指摘。家族関係や地域社会のつながりが希薄になり、「自分地のことは自分地の内側で解決しろよと」「じゃあお前が1人で解決しろよみたい」な日本の特性が、よりマイルドながらも深刻な危機を招いているという。
現状は「推し選挙ぐらいの発散ですんでる」が、「これがここで止まるのか、日本のトランプ登場みたいなところまで行くのか」は不透明だという。
最後に與那覇氏は、選挙間近で有権者が選挙をどう捉えるべきかという問いに対し、「推しじゃなくて政策を読んで選びましょうみたいに言いたいところですけど、そう言って届く人は推し投票してないと思う」と述べ、その難しさを認める。しかし、「今選挙に行って日本良くなると思えないなっていう風になったら、むしろじゃーどういう選挙制度になってくれたら日本もうまくいくんだろうかみたいな」メタ的な視点から考えることが「生産的じゃない」かと提案する。例えば、完全な小選挙区制、比例代表制、あるいは「一選挙から複数の人が通るけど投票する側も複数名前かける」ような、一人が複数候補に投票できる制度の導入などを例に挙げる。
現状の「1人1票」では、有権者は「推ししか書けない」と選択肢が限定される。しかし、複数の候補に投票できる制度であれば、「1人は政策を読んで真面目にもう1個は推しとか」あるいは「1人は普段まお世話になってる先生に、でももう1人は若くて挑戦した人のうち1番この人いいなって思った人にとかできるかもしれない」と、投票の選択肢が広がり、より柔軟な意思表示が可能になるだろう。
評論家・與那覇潤氏が語る「推し選挙」は、現代日本の社会状況を映し出す鏡である。人々の「安全な逸脱」への欲求が、民主政治の根幹を揺るがし、新たな危うさをはらむ。はたして、この「推し選挙」の波はどこへ向かうのだろうか。そして、私たち有権者は、この現象とどう向き合えば良いのだろうか。


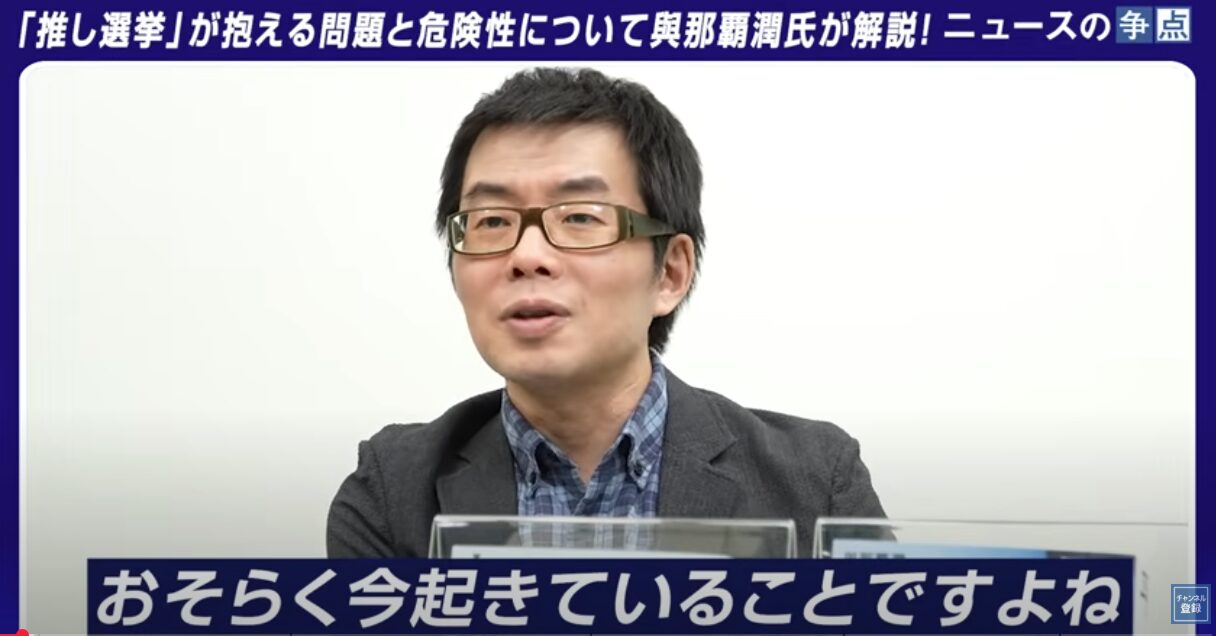


コメント