作家の小名木善行氏が、一般的に肯定的に語られる明治維新の「文明開化」の裏に隠された「グローバリズム」、すなわち「植民地支配」の側面を詳細に解説する。明治以降、日本が失ったものや経験した苦難に焦点を当て、歴史を多角的に見ることの重要性を語る。
「植民地支配」としてのグローバリズム
小名木氏は、「グローバリズムって日本語に翻訳したらどうなるかっていうとこれ植民地支配って言います」と、その本質を端的に表現する。「ごく一部の人たちが貧しいところに行って貧しい人たちから財産を巻き上げることによって自分たちだけが贅沢な暮らしをする」ことが、グローバリズムの真の姿だと指摘する。
一般的に、明治維新は「近代国家への移行」や「文明開化」として肯定的に語られることが多い。しかし、小名木氏は「日本を壊し始めた」側面があったと語る。江戸時代にはなかった大規模な戦争が明治以降に立て続けに起こり、「とどのつまりが先の対戦ですよね」と第二次世界大戦で多くの命が失われたことに言及する。「近代国家になりました、文明開化しました、いいことばっかりになりましたって言えるんでしょうか?」と疑問を投げかける。
不平等条約が招いた黄金の流出と経済的支配
開国後、日本はアメリカとの間で不平等条約である「日米修好通商条約」を結んだ。特に問題となったのは、第5条の「外国の通貨と日本の通貨は同量で適用する」という規定だ。これにより、当時の香港と日本の金銀両替相場の4倍もの差を利用され、アメリカから来たハリスによって「日本国内から黄金がドバーっと流出したんです」。
小名木氏は、当時の世界の黄金の総量のうち「オリンピックプールに換算して3倍分、このうちの2杯分が日本産の金なんです」と述べ、日本が「黄金の国ジパング」であったことを強調する。そして、ハリスがこの黄金の流出で得た莫大な利益が、リンカーン大統領による南北戦争の戦費に充てられたと主張している。
仕組まれた戊辰戦争と内乱の長期化
南北戦争で余った北軍の銃と弾薬、軍装は、イギリス・フランス経由で日本に持ち込まれ、幕府側と新政府側の双方に売却された。「いらないものを回収してどするんだ。じゃあ日本に売り付けたれていう話になって」という形で、日本は外国勢力の内乱の舞台にさせられた。
戊辰戦争では「幕府の側も軍側も同じものを使って、同じ格好をして戦った」と、内乱が仕組まれたことで外国勢力が儲かる構図があったと指摘する。「1500万人ぐらいが死んでくれるはずだった」という外国勢力の期待とは裏腹に、実際の死亡者数は「3万人ぐらいで終わっちゃった」と述べ、日本人の内乱を最小限に食い止めようとする精神性が、大規模な内戦を回避した可能性を示唆する。
伝統の喪失と地方の衰退
明治維新以降、日本の伝統的な価値観や文化は急速に失われたと小名木氏は語る。「伝統的な日本の価値観とか文化があの明治維新以降急速に失われていくことになった」という。武士道の喪失、和服から洋服への変化、新暦への変更による季節感の喪失などがその具体例だ。
また、政治・経済の中心が東京に一極集中したことで、江戸時代には「それぞれの国がいわば独立国」として存在していた地方の文化と自治が「衰退した」と問題視する。「排仏毀釈」によって仏教の寺や仏像が破壊されたことにも触れ、日本の精神文化が破壊されたと述べる。
庶民を苦しめた所得税と自由民権運動の真実
明治新政府が導入した所得税は、農民に現金の納付を義務付けたことで、「日本の庶民っていうのがものすごく米の変動によって生活が苦しめられるという状態が起こりました」と説明する。
教科書で教えられる自由民権運動が「思想的なもの」であるという見方に対し、小名木氏は「所得税」によって生活が困窮した庶民が、「俺たちみんな全員が損してるよね。とんでもない政治をやるような国に対して、わしらから直接文句言えるような、そういう政治そういう形を作ってくれ」という切実な要求が背景にあったと語る。
はたして、歴史を多角的に捉えることで、現代社会が抱える問題の本質も見えてくるだろうか――。

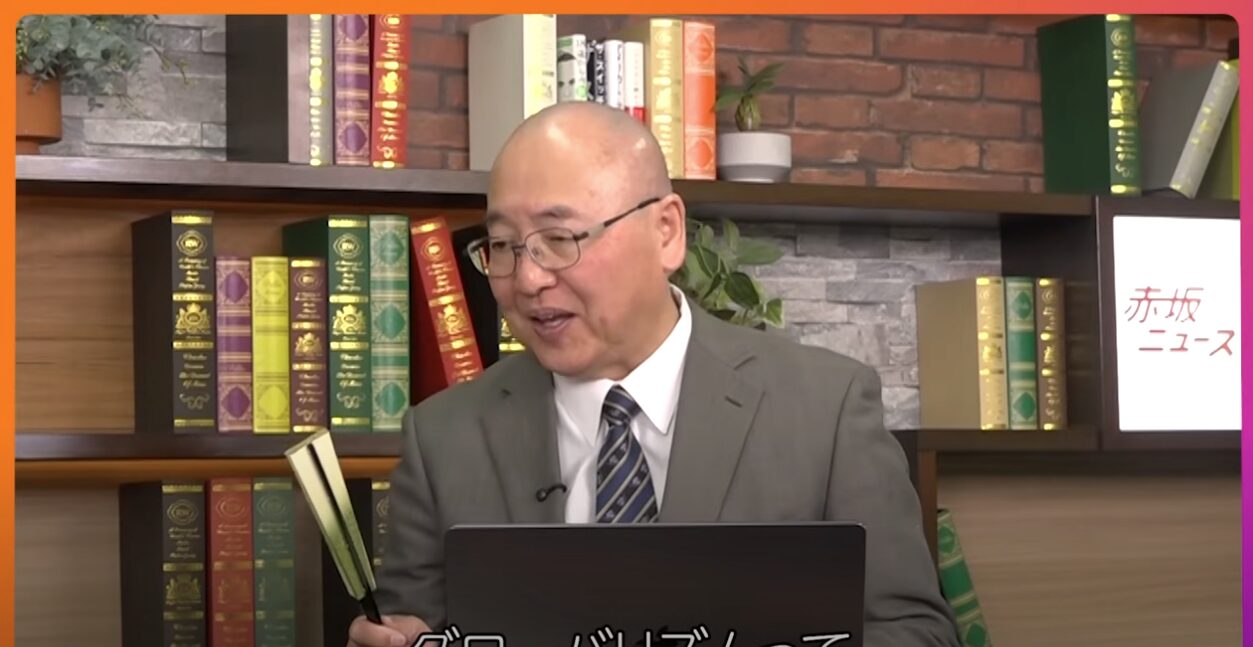


コメント