経済評論家の三橋貴明氏が、ステファニー・ケルトン教授との対談でMMT(現代貨幣理論)について解説した。政府の貨幣発行能力や財政赤字に対する誤った認識が、日本経済の停滞を招いていると指摘する。
「政府の赤字」は「国民の黒字」である
三橋氏は、MMTの根本的な考え方として、日本やアメリカのような自国通貨を発行する政府は、民間とは異なり「貨幣発行者」であることを強調する。そのため、政府が支出を行う際に「お金がなくなる」ということはない。
この点を理解しないまま、日本国内では財政破綻論が盛んに報じられてきた。しかし、財務省自身が2002年に発行した対外文書にも「日本やアメリカなどの先進国の自国通貨建ての国債のデフォルトは考えられない」と明記されているにもかかわらず、国内向けのプロパガンダでは、依然として財政危機が叫ばれている現状を批判する。
また、MMTの重要な視点として、「政府の赤字は、政府以外の経済セクター(民間部門)にとっては黒字である」という会計上の恒等式を挙げた。三橋氏は「本来財政赤字が増えたってことは、我々(国民や企業)の黒字が増えたというような認識にならなきゃいけないんですけども、なぜかそういう報道が全くされない」と、緊縮財政が続いてしまっている現状を憂う。
銀行は「何もないところからお金を創り出す」
ケルトン教授は、従来の「課税で集めたお金を政府が支出する」という考えを転換し、「まず政府が支出を行い、後から課税によってそのお金の一部を経済から引き戻す」という、貨幣の流通メカニズムに基づいた順序を提示したと三橋氏は解説する。
また、銀行の信用創造についても、「銀行は他の人の預金から貸し出すという風に信じたならば」「あなたの預金を別の客に貸すからあなたの預金が減りますよっていう話なんてないでしょ?」というケルトン教授の発言を引用し、銀行が融資を行う際に「何もないところからお金を創り出す」現実を指摘する。
緊縮財政が招いた20年以上のデフレ
三橋氏は、日本のGDP成長が他の先進国に比べて低い理由として、政府支出の伸びが著しく低いことを挙げる。21世紀に入って以降、GDPが2倍近くになったカナダ、アメリカ、イギリスでは政府支出も同様に2倍近く増加しているのに対し、日本は政府支出が1.08倍に過ぎない。
ケルトン教授が「政府の支出というのは非常に重要な部分なんです。それがなければより強い回復の条件を整えることができない」と述べていたように、日本政府が十分な支出を行わなかった結果、20年以上にわたるデフレからの脱却が遅れていると分析する。
また、政府債務が増加しても金利は低下し続けているという日本やアメリカのデータが示すように、MMTは「クラウディングアウト」論を否定する。金利は市場原理ではなく、中央銀行の政策によって決定されるものであり、「貯蓄のプールが限られている」という考え方は誤りであると強調する。
政治的プロパガンダとしてのMMT批判
MMTはしばしば「お札を刷る理論」と誤解され、ハイパーインフレへの懸念が表明されることがある。ケルトン教授は「MMTの正しい知識を提供すること。決して、お金を印刷する理論ではありません」と述べており、三橋氏もこの誤解を解く必要性を訴える。
アメリカでは、共和党議員がMMTを「社会主義的」と批判する動きが見られるが、これはMMTの性質とは関係なく、伝統的な政治ゲームの一環であると指摘する。共和党が「財政赤字は危険」と主張しながら、政権時には赤字を膨らませてきた事実がその証拠だ。
これは、「誰かの赤字は誰かの黒字」というMMTの原則が、特定の層に利益をもたらす形で利用されてきたことを示唆している。
変化は「ボトムアップ」で起こる
三橋氏は、MMTが経済学における「天動説から地動説への転換」に例えられるほどのパラダイムシフトをもたらす可能性を秘めていると語る。
しかし、その変化はトップダウンではなく「ボトムアップ」で起こると強調する。ケルトン教授が「国民一人ひとりがMMTを学び、政治指導者に良い政策を実践するよう訴えることの重要性」を説いていたように、国民が正しい知識を得て声を上げることが、政策変更と経済の健全化に繋がるという。
はたして、国民の誤解が解け、MMTに基づいた経済政策が実行される日は来るのだろうか。


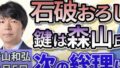

コメント