元JA全農常務の久保田治巳氏は、現在の日本の食料自給率(カロリーベース)が約38%まで低下している現状に対し、これは戦後の農業政策が「食料自給率低減政策」として機能した結果だと指摘した。その政策はGHQの占領政策に端を発し、日本の国防・軍事政策として意図的に行われた可能性があると推測。食料自給率100%を目指すための具体的な提言として、肉食中心の食生活の見直し、魚食文化の再評価、農家の所得安定化、そして遊休農地を活用するための「半公務員」制度の導入など、これまでの固定観念を打ち破る大胆な政策転換が必要であると強調した。
食料自給率低下の「真の目的」を問う
元JA全農常務の久保田治巳氏は、現在の日本の食料自給率が約38%という危機的な水準にある現状に対し、その根深い原因と、食料自給率100%を目指すための具体的な提言を行った。
久保田氏は、日本の食料自給率の低下は、単なる政策の失敗ではないと指摘する。「戦後の農業政策の基本は大成功したんですよ。なぜかと言うとその基本が食料時給率低減政策だった」。この発言は、戦後の農業政策が、意図的に食料自給率を低下させる目的で運用されてきた可能性を示唆する。
さらに、その背景にはGHQの占領政策があり、日本の国防・軍事政策として意図的に行われた可能性があると久保田氏は見ている。「外国の大学では(中略)相手の国の食料自給率を減らしてこっちがコントロールする。それはある意味国防であり軍事政策だということをはっきり教えてるわけですからね」。自由化やFTA、TPPといった関税ゼロ、非関税障壁の撤廃が推進され、結果的に食料自給率が低下してきたと分析。農家や農業組織、農林水産省の職員も真摯に努力してきたにもかかわらず自給率が下がり続けたのは、目的が「食料自給率を低下させること」にあったと結論付けた。
食料自給率100%へ:食生活と農家の所得安定化
久保田氏は、食料自給率100%を目指すための具体的なアイデアを複数提示する。
畜産物と魚介類の分野では、輸入飼料に依存する肉食中心の食生活の見直しを提言。肉の価格を上げることで消費量を減らし、自給率改善に繋げる。また、海に囲まれた日本は本来魚食民族であるとし、魚の消費を増やすことで自給率を向上させるべきだという。さらに、鯨は日本の伝統的な食文化の一部であり、適切に管理することで魚の資源管理にも繋がり、食料自給率向上に貢献できると述べ、鯨肉の輸入牛肉に置き換えるための戦略として、国際的な「かわいそう」論が利用された可能性を指摘した。
穀物分野と農家の所得保障については、現在の農家の所得が低く、多くが兼業農家であるため、国からの補助金が不足している現状を問題視。「農家のお子さんが農業を継ぎたいと思うような(中略)一定の収入が確保されて、国民の皆様からもリスペクトしてもらえるようにしていただけるのにそんな費用は必要ないと思うんですよ」と、農家に安定した所得を保障し、農業が「大事でリスペクトされる」職業となるような仕組みを構築することの重要性を強調した。これにより、若者が農業を継ぐ意欲を高めることができるという。
新たな担い手と中山間地の活用
新たな農業の担い手については、「半公務員」制度の導入を提案。遊休農地や耕作放棄地の多い地域において、役所が公務員として農業従事者を雇用する。彼らは普段は林業や自然環境保全の仕事に従事し、農繁期には農業を行うことで、安定した収入を確保しながら農業を継続できる。これにより、地方創生にも貢献できると語る。「公務員だったら給料が安定してるじゃないですか。でこんだけ作ってねと」。
また、コロナ禍で普及したZoomなどのネット会議を活用し、地方に住みながら農業と他の仕事を両立できるような環境を国が推奨・支援すべきだという。外獣対策としては、イノシシやシカなどの外獣被害が深刻な中山間地域において、行政が主導して外獣駆除を推進し、捕獲された動物の肉(ジビエ)の流通を整備することで、新たな食料資源とすることを提案した。
株式会社の役割については、農地所有が条件の良い農地を独占し、大規模化することで市場を支配する可能性があるため慎重な姿勢を示した。しかし、耕作放棄地が多い中山間地域など、条件の悪い場所での農業参入には一定の補助金を出すことで、その知恵とノウハウを活用することを提案する。
久保田治巳氏の提言は、現在の食料自給率の低さや農業の現状が、単なる政策の失敗ではなく、より深い意図があった可能性を強く示唆している。食料自給率100%の目標達成のためには、これまでの固定観念を打ち破り、発想の転換と大胆な政策転換が必要であると強調した。財政当局との連携や、国民全体の農業に対する理解とリスペクトを深めることの重要性も指摘している。はたして、久保田氏が示すこの「発想の転換」は、日本の食料安全保障の未来を切り拓くことができるだろうか――。

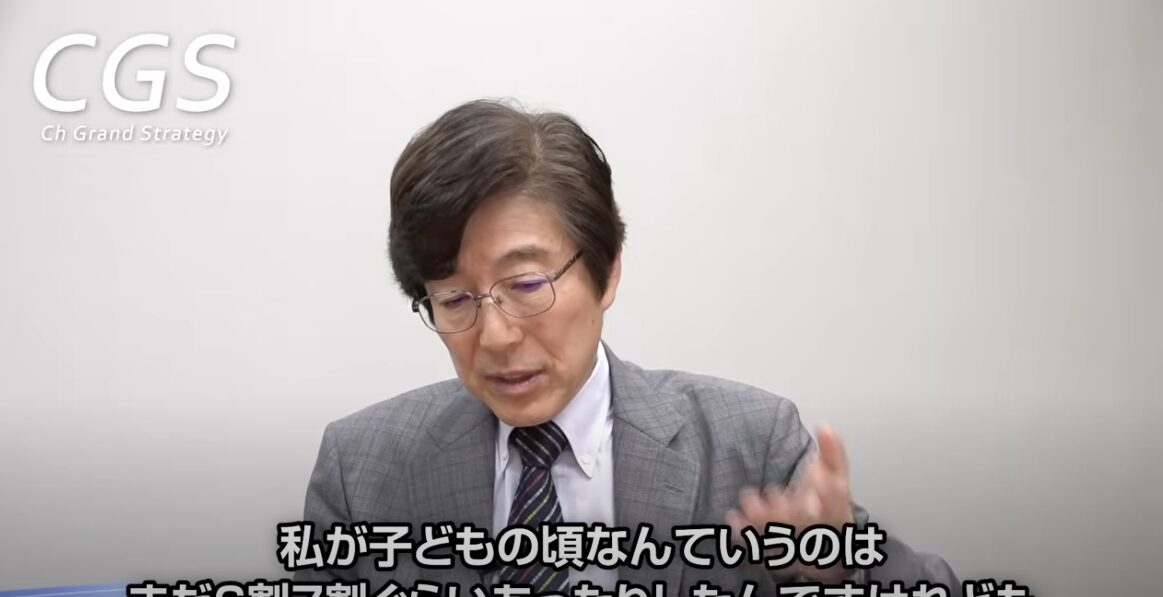


コメント