元JA全農常務の久保田治巳氏は、昨年(2023年)の米価格高騰に関して、JAが「ぼったくった」という報道が誤解であると指摘した。JAは価格を吊り上げないよう、あえて高値で買い取らず、「消費者の小売価格が高騰するのを防ぐためでした」と述べ、結果的にJAグループの米の収率が15%減少した。米価格高騰の真因は、作況指数の実態との乖離や流通業者の買い占め、そして供給量不足にあったと分析。江藤農水大臣の辞任や小泉農水大臣就任後の備蓄米払い下げの随意契約への転換、農林中金法改正の動きなど、一連の出来事の裏に財務省の介入や政治的思惑が絡んでいる可能性を示唆し、「全てのマスコミが同じ方向の報道をする時っていうのはなんか違うな」と、情報を受け取る側の多角的な視点の重要性を強調した。
「JAがぼったくった」報道の誤解:真実は逆だった
元JA全農常務の久保田治巳氏は、昨年(2023年)の米価格高騰を巡る「JAがぼったくった」という報道に対し、その真実と背景にある複雑な要因について、自身の知見を交えて詳細に解説した。
昨年の米価格高騰に関して、JAが「ぼったくった」と報じられたが、久保田氏によると、実際にはJAは逆の行動を取っていたという。
JAは農家から米を買い取る際、市場価格より低い価格(概算金)を提示していた。しかし、高値で買い取る業者が現れたため、農家はそちらに販売する傾向があった。久保田氏は、JAが価格を吊り上げないよう、あえて高値で買い取らず、結果的にJAグループの米の収率が15%減少したと説明する。これは、消費者の小売価格が高騰するのを防ぐためだったのだ。結果として、JAは契約済みの顧客への供給が滞り、農水省に備蓄米の放出を要請する事態となった。
久保田氏は、「真面目一本でさせていただいてる」と述べ、JAが価格を吊り上げることなく、むしろ安定供給を優先していたことを強調した。
米価格高騰の真因:見えない供給不足と流通の動き
米価格高騰の真因は、報道されたようなJAの「ぼったくり」ではなく、複数の要因が絡み合っていたと久保田氏は分析する。
まず、農水省が公表した作況指数(米の収穫量予測)が、実際よりも高く見積もられていた可能性を指摘する。「指数ほどは取れてないっていう声がほとんどでしたね」と、全国のJA組合長からの聞き取りに基づき述べた。さらに、作況指数は玄米ベースの収穫量を示すものであり、実際の流通量である白米の収穫量を正確に反映していないという。昨年の猛暑により、玄米の量としては取れても、精米すると白い粒(品質の低い米)が多く、歩留まりが大幅に低下したのだ。「玄米では取れていたんだけども白米にすると歩留まりがすごく落ちるということ」が、流通する白米不足の要因となったと久保田氏は説明する。
また、米の価格が上昇する期待があると、卸売業者や小売業者が在庫を積み増す動きが見られたことも要因だと語る。これにより、市場に出回る米の量が減少し、価格がさらに上昇するという経済原理が働いた。「マーケットに出てくる量が減ると値段は上がってしまう」と久保田氏は説明した。日本全体の米の消費量(食用)が約700万トンであるのに対し、作況指数通りの生産量であったとしても、供給は「カツカツ状態」であり、需要を満たすには不足していた可能性があったという。
備蓄米放出を巡る政権内の動きとメディア報道への疑問
一連の米価格高騰を巡る動きの中で、政治的な思惑や省庁間の力学が働いていた可能性も示唆された。
江藤農水大臣が「米が買ったことがない」という発言の後に辞任に追い込まれたことについて、久保田氏は、その直前に農水省が備蓄米の払い下げに関するデータを公表していたことを指摘する。このデータによると、卸売業者が備蓄米を転売する際、通常よりもはるかに高い手数料(2400円が961円に圧縮された備蓄米から7500円に跳ね上がっていた)を取っていたことが示されており、これはJAが「ぼったくった」という報道とは逆の事実を示唆しているという。
江藤大臣時代は、備蓄米の払い下げは「競争入札」が原則とされていたが、小泉大臣の就任後、財務省からのレポートに基づき「随意契約」が可能であるとされた。これに対し久保田氏は、「なんで小泉大臣にだけ教えてくれたんだろうかと」と、財務省の対応に疑問を呈し、特定の政治家を「花を持たせようとしている」と見ている。
小泉大臣が農水大臣に就任してすぐに「農林中金法の改正が必要な事項については早急に検討を進めていきたい」と発言したことについて、久保田氏は、コメの価格高騰対策だけでなく、農林中央金庫の金融問題が「本音なのではないか」と推測する。これは、国有財産の払い下げと金融問題が、同じ層の人々によって「つかさどっている」可能性を示唆しているという。
久保田治巳氏の分析は、今回の米価格高騰とそれに伴うJAへの批判、そして備蓄米の放出を巡る一連の動きが、単なる経済現象ではなく、複雑な政治的思惑や省庁間の力学が絡み合っている可能性が高いことを示唆している。はたして、私たちは報道の裏に隠された真実を見抜き、日本の食料供給の安定と農業の未来を守ることができるのだろうか――。久保田氏は、「テレビの言うことを鵜吞みにしないということが大事ですので、裏側を考えるということを習慣けていただきたいなと思います」と述べ、情報を受け取る側が多角的な視点を持つことの重要性を強調した。

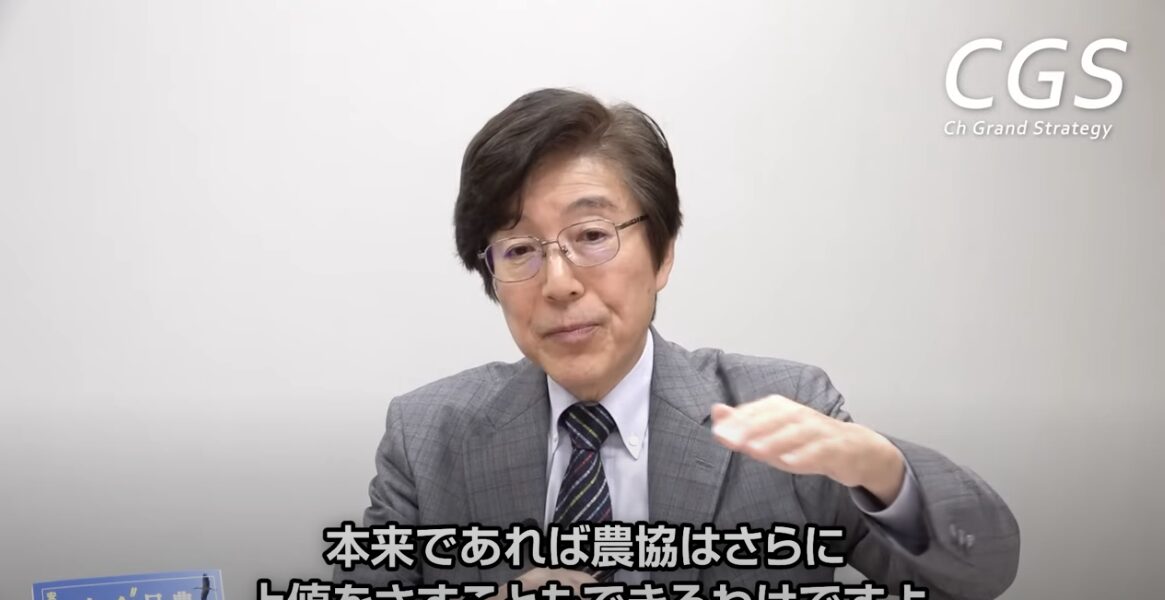


コメント