元JA全農常務の久保田治巳氏は、約10年前の農業改革期に突然持ち上がった全農の株式会社化要求の背景に、2016年の「日米間の密約」の存在があったと指摘した。この文書には、「非関税障壁」としての共同組合の存在が不適切であると日本政府が認識している旨が明記されており、株式会社化要求が「アメリカの意思」である可能性を示唆。オーストラリアでの類似の失敗事例や、郵政民営化の教訓を踏まえ、JAの「兼営」の重要性を強調した。農林中金の運用失敗がJAの「兼営」解体へ誘導される懸念も示し、「JAが悪いのではないか」という世論形成への警戒感を表明した。
2016年日米合意文書の衝撃:「非関税障壁」とされた共同組合
元JA全農常務の久保田治巳氏は、日本の農業が直面する根深い問題、特に共同組合である全農の株式会社化要求の背景に隠された、驚くべき事実を明らかにした。
約10年前の農業改革期に、規制改革会議が突然、共同組合である全農を株式会社化するよう求めた。久保田氏は当時全農に41年間勤務しており、この要求の背景に疑問を抱いたという。
調査の結果、政府のウェブサイトで公開されている文書に、日本とアメリカがTPP(当時アメリカも参加)に際して結んだ「前段での下準備」に関する取り決めが記されていたことが判明したと久保田氏は語る。この文書には、「非関税障壁」が不適切であると日本政府が認識している旨が明記されているそうだ。さらに、規制改革会議に議案を提出し、その規制改革会議の意向に従って日本政府が必要な措置を取る、とアメリカ政府と日本政府が合意しているという。
久保田氏はこの合意文書を分析し、全農の株式会社化要求が「アメリカの意思」である可能性を示唆している。共同組合は買収ができないため、この形態自体が「買収防衛策」ひいては「非関税障壁」と見なされた可能性があるという。
当時の外務大臣(岸田氏)は、この文書に法的拘束力はないと答弁していたが、実際には自主的に買収防衛策の解消に応じているように見えると久保田氏は指摘する。NTT法第4条には、政府が3分の1以上の株を保有することで買収防衛策としている条項がある。この条項の削除が過去に議論されたことと照らし合わせると、共同組合を株式会社化することで、買収の可能性を排除する既存の枠組みを破壊する意図が見て取れると語った。
オーストラリアの失敗と共同組合の普遍的意義
久保田氏は、JA民営化・株式会社化に反対する理由として、過去の失敗事例を挙げる。2010年にオーストラリアで全農と同様の穀物サプライヤーが株式会社化され、その後買収されてしまった事例が紹介されている。久保田氏は、この事例を分析し、全農の役員に株式会社化の危険性を説明したという。
株式会社が利益の最大化を追求する組織である一方、共同組合は農家から安く買い叩き、消費者に高く売るという悪しき慣行を防ぐ役割を果たすと久保田氏は説明する。このため、農産物や畜産物に関しては、世界中で共同組合の事例が非常に多いという。ヨーロッパでは世界の売上の約56%、アメリカでは約25%を共同組合が占め、日本と合わせると、先進国における共同組合の事業は全体の9割に達する。これは、共同組合のメリットが世界中で認識されている証拠であると強調した。
また、ちょうど共同組合年であることもあり、日本国会でも共同組合を認める宣言がほぼ全ての政党(一部を除く)によって賛成され、採択されたという。
JA民営化・株式会社化への懸念:郵政民営化の教訓と農林中金の動向
久保田氏は、JAの民営化・株式会社化に反対する理由として、過去の郵政民営化の失敗を挙げる。郵政民営化は、「郵政が税金を無駄遣いしている」という誤った情報に基づいて行われ、結果的にサービスの質の低下や利便性の喪失を招いたと指摘する。郵政は、郵便事業の赤字を貯金事業と簡保事業の黒字で補い、ユニバーサルサービスを維持していた。しかし民営化により分割された結果、郵便事業は採算が取れなくなり、値上げやサービス低下が起きているという。
JAも郵政と同様に、信用事業(金融)、共済事業(保険)、経済事業(米の販売など)を兼営している。この兼営によって、赤字になりやすい事業を他の事業の利益で補い、農家や地域住民に対する総合的なサービスを安定的に提供していると久保田氏は説明する。株式会社化によって兼営が分断されると、赤字事業は維持できなくなり、農家への支援や食料供給体制が弱体化する恐れがあると警鐘を鳴らす。
最近報道された農林中金の運用失敗(米国債の評価損)について、久保田氏はこれが単なる運用ミスではなく、背後に不穏な動きがある可能性を懸念している。他の生命保険会社は同様の含み損が発生しても売却せず保有し続ける選択をしているにも関わらず、農林中金が多額の損失を確定させたことに疑問を呈した。このような失敗が第三者委員会の議論を呼び、結果的にJAの兼営を解体する方向に誘導されるのではないか、という懸念が示された。
久保田治巳氏の分析は、日本の農業、特にJAが直面する課題が、単なる経営問題に留まらず、国際的な戦略や過去の政策の積み重ねに起因している可能性を示唆している。2016年の日米合意文書が「非関税障壁」として共同組合の存在を問題視していたという指摘は、日本の食料安全保障に対する深い懸念を抱かせる。はたして、私たちはこの歴史的経緯と外圧を乗り越え、日本の農業と食料の未来を守ることができるのだろうか――。共同組合の本来の役割と、過去の民営化の失敗事例を踏まえ、慎重な議論が求められる。

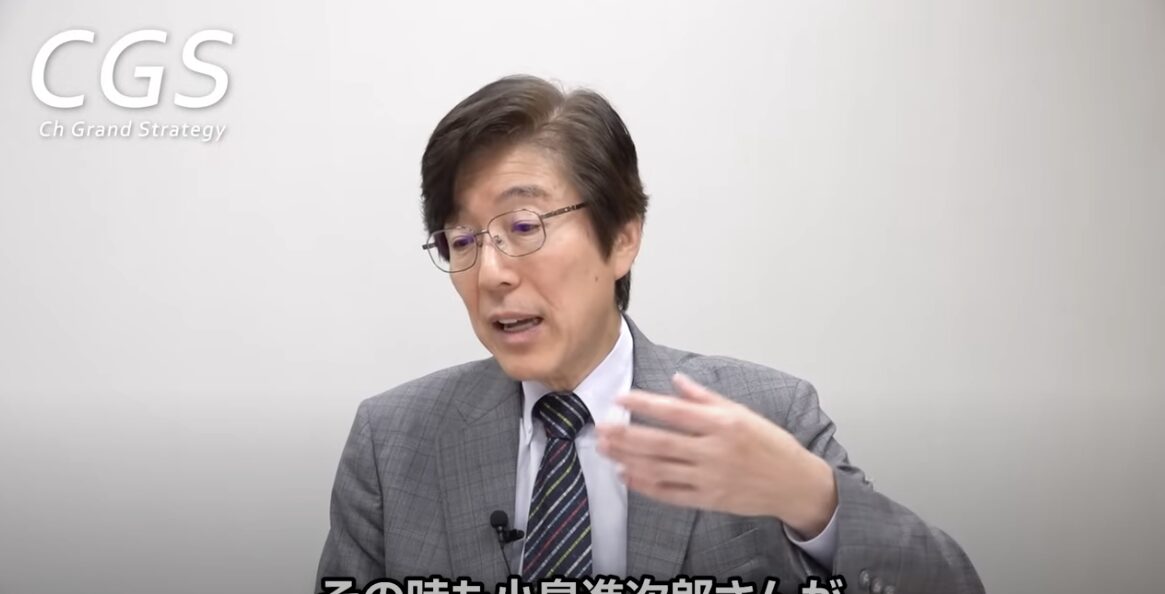


コメント