東京大学先端科学技術研究センター客員教授の河野龍太郎氏が、トランプ政権の「グローバリゼーションの巻き返し」やウクライナ戦争をきっかけとした「ドル離れ」の動きについて解説する。世界経済は今、ドル単一基軸通貨体制から、歴史的な転換期を迎えていると語る。
トランプが仕掛ける「ドル覇権の手放し」
トランプ政権の政策は、一見するとドル覇権を自ら放棄しようとしているように見えるが、その真意はグローバリゼーションの巻き返しにあると河野氏は分析する。
この20~30年でITデジタル革命が進みグローバリゼーションが加速した結果、アメリカの中間層の雇用は失われた。その不満を背景に関税を課すことで、失われた雇用を取り戻そうとしているのだ。
河野氏は、ドル基軸通貨体制による利益が、アメリカ国内の金融部門、IT部門、グローバルエリートに集中し、製造業や地域経済には還元されていないと指摘する。この国内の分配の不均衡が、トランプ政権を支持する層の不満の根源となっている。
「ドルのシステム、自分の国の通貨が世界の基軸通貨であることは、実はアメリカ国民の多くの人にとっては全然プラスじゃないじゃん」という声が、トランプ政権の強硬な政策を後押ししている。
ウクライナ戦争が引き起こした「終わりの始まり」
ドル基軸通貨体制の終焉の始まりは、トランプ政権の政策だけではなく、2022年のロシアによるウクライナ侵攻が重要な契機となったと河野氏は語る。
ロシアが国際送金システムSWIFTから排除されたことは、「金融の核兵器」と呼ばれた。しかし、このことでロシアは中国との貿易を人民元決済システムで行うなど、ドルシステムから独立した経済活動を進め、結果的に高い経済成長を維持している。
ロシアの事例は、「ドルシステムがなくても大丈夫」という認識を各国に広げた。その結果、各国の中央銀行は外貨準備におけるドルの比率を減らし、金の保有を増やす傾向にある。これは近年の金価格上昇の一因ともなっている。
金融市場はネットワーク外部性によって機能するため、ドル基軸通貨体制がすぐに崩壊することはない。しかし、今回の動きは「終わりの始まりに差しかかった可能性がある」と、その歴史的な転換点であることを示唆する。
中国の台頭とソフトパワーの破壊
中国の経済力は購買力平価で見た場合、すでにアメリカを上回っている。軍事力もアメリカに接近しており、中国の台頭はドル覇権の終焉を加速させる要因の一つであると河野氏は指摘する。
ジョセフ・ナイ氏が提唱した「ソフトパワー」は、アメリカの覇権を支える重要な要素だった。しかし、トランプ大統領のハーバード大学への言動に見られるように、このソフトパワーが破壊されつつある。これにより、中国とアメリカの「距離感」が縮まってきているのだ。
さらに、原油の国際取引におけるドル建て決済(ペトロダラー体制)も、中国の中東からの原油輸入量の増加や上海における人民元建て原油先物取引の開始により、「ペトロチャイナ体制」へと移行する可能性を秘めていると語る。
ニクソン・ショックとの類似性
現在のドル基軸通貨体制の揺らぎは、1971年のニクソン・ショックと構造的に類似していると河野氏は指摘する。
当時のアメリカも安全保障と国際金融システムを支えきれなくなったというロジックであり、国内の分配問題も背景にあった。ニクソン・ショック以降、変動相場制へ移行したが、その後もドルはその地位を強化してきた。これは「世界中の人が使うからドルをもっと使う」というネットワーク外部性の作用による。
しかし、現在は経済力、軍事力、そしてソフトパワーといったドルを「安全資産」とみなす要素に陰りが見え始めている。この信頼性の揺らぎが「みんながドルは安全だって思ってる人がいっぱいたのがどんどん減っていっていくとそれはその崩壊の始まり」だという。
河野氏は、今後の世界は「ドル単一基軸通貨体制」から「複数基軸通貨体制」へと移行する可能性が高いと見ている。戦後のドル一強体制は、むしろ歴史的な特殊例であり、経済力、軍事力、ソフトパワーといった総合力が分散することで、複数の通貨が基軸通貨として機能する時代が到来するだろう。
はたして、私たちは歴史的な転換点を迎えているのだろうか――。



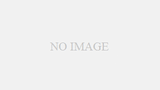
コメント