東京大学大学院特任教授の鈴木宣弘氏が、現在の米価格高騰をめぐるJA批判の誤解を解き明かし、日本の食料安全保障が直面する真の危機について解説する。
米価格高騰とJA批判の真相
現在報じられている米価格高騰の原因を「JAが米の価格を釣り上げている」とする見方があるが、鈴木教授はこれを「事実に全く反する」と明確に否定する。JAには「釣り上げる力がないんですね」と述べ、むしろ米不足に困窮している現状を指摘する。
米不足により、JAよりも高い価格を農家に直接提示する業者が増え、JAへの米の集荷率は「もう3割ぐらいにしかならない」と大幅に落ち込んでいる。鈴木教授は「JAさんはお米がなくて困ってる」と強調する。
食料管理制度の廃止後、流通が自由化され、JA以外の業者による米流通が拡大したことで、JAの集荷率はかつてのほぼ100%から低下し、米の価格をコントロールする力を失った。歴史的に見ても、JAの集荷率が下がると、「農家側とすればですね買い叩かれるわけですよね」と鈴木教授は指摘し、今回の高騰直前まで米の価格は「30年前のもう半分以下まで下がっていた」と述べる。
価格をコントロールしてきたのは、「小売を中心とした買い手の価格形成力、取引交渉力が非常に強い」相手側だという。「米の値段が買い叩かれてきたっていうこと自体が問題であって、JAが農家がある意味買い叩かれてきたってことが一番の問題です」と、JAへの不当な批判に警鐘を鳴らす。
農家がJAを通さずに直接販売する動きもあるが、これは一見有利に見えても、全体に広がれば「買い叩かれる構造を自分たちが作ってしまうことになるので全体の価格が押しげられていく」と鈴木教授は懸念を示す。そして、「農協の共同販売というものがみんなを守ってるんだということをきちんと認識する必要がある」と、JAの本来の役割の重要性を改めて強調する。
JAの本来の役割と「農政トライアングル」の変質
JAは、農家が単独で巨大な市場交渉力を持つ相手に対抗できない状況において、農家の生活を守るための総合的な相互扶助組織として設立された。「個々の農家さんが売ってたんでは大きな相手に叩かれてしまうと。だからみんなで集まってしっかりね価格形成できるように販売していこうねという共同販売」は、JAの大きな役割の一つである。
また、農業経営における金融的な課題や、不測の事態への備えを相互扶助の精神で支えるために、貯金を集め、貸し出しを行う「信用部門」や「共済部門」が作られた。これらは「農家の皆さんが総合扶助で守るために作られてきたわけですよね」と鈴木教授は語る。現在では、これらの機能は地域住民も恩恵を受ける、地域を支える総合的な機能となっている。
一部からは、農業の効率化や株式会社参入推進のためにJAを解体すべきだという主張がある。これは「農業で利益を得たいような人たち」の思惑が背景にあると鈴木教授は指摘する。企業が参入することで、「今頑張ってる小さな農家さんをやめる方向に持っていって、そして企業そのものが農業に入ってきてやるようなところに集約していく」方がメリットがあるため、JAが「非効率な人をね支えてしまってるんだ」という議論に繋がっているという。
かつて日本の農業政策を決定する上で強固な影響力を持っていたとされる「農水省、JA、農林族議員」の「鉄のトライアングル」は、もはや「大昔の話」であり、その影響力は大幅に弱まっていると鈴木教授は指摘する。農林族議員の減少や、TPP交渉におけるJA全中の指導・監督権の剥奪、そして財務省や経済産業省の影響力が増す中での農林水産省の弱体化がその背景にある。鈴木教授は、農水省が「農林水産省じゃなくて財務省経済産業局農業課ぐらいじゃないか」と、その弱体化を憂いている。
食料安全保障の危機と今後の政策提言
ロシア・ウクライナ戦争以降、世界の食料サプライチェーンが閉ざされる中で、国内生産の重要性が戦後初となるレベルで高まっているにもかかわらず、自給率向上の議論が進まない現状は「かなり危機的な状況」であると鈴木教授は警鐘を鳴らす。
「全体としての食料をどう確保するのか、そのための農業・農村をどうするのかっていう議論がない」現状が問題であると鈴木教授は指摘する。
JA解体論の背景には「外資が運用できるようにしたい」という思惑がある。これは「巨大穀物メジャーに振り飛ばすようなことをしてはいけない」と強く訴える。JAの共同販売や共同購入の破壊は、「自分たちがもっと買い叩きたい」と考える勢力によるものであり、これは「国民の富を飛ばす売国行為」であると指摘する。
真の農業政策の方向性として、鈴木教授は以下の点を提言する。
- 今の農協解体の議論は絶対阻止しないといけない
- 今頑張ってる人たち、そして地域社会地域コミュニティを守り、そして国民への食料供給をしっかり確保できる政策が必要である。
- 農家への直接支払いによって、消費者は安く食料を購入でき、農家は増産による価格下落分の所得を維持できる。
現在の日本農業は、食料安全保障の危機と、JAへの不当な批判、そして一部の勢力による「成長産業化」の名の下での農家や地域社会の破壊の危機に直面している。鈴木教授は、JAの本来の役割を再認識し、個別の農家を支えるための「直接支払い」を導入することで、生産者と消費者の双方を守り、真の意味での食料安全保障を確立する必要があると強く訴える。これは単なる経済問題ではなく、日本の社会と未来に関わる重要な課題である。私たちはこの現状を深く理解し、日本の農業と食を守るための行動を起こすべきだろう。
[引用元]【東大院特任教授が指摘】実はコメ価格を決めているのはJAではない!?(東京大学大学院特任教授 鈴木宣弘)【ニュースの争点】


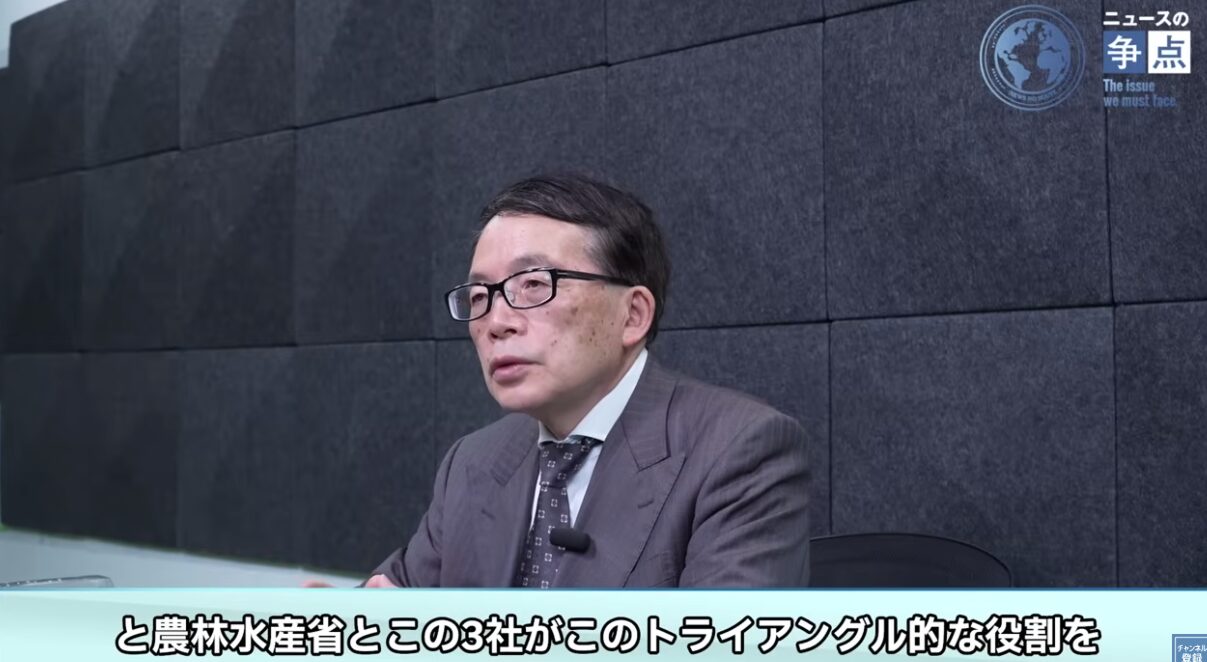


コメント