2025年7月20日に行われた参議院選挙で、参政党は事前の予想を上回り、1議席から14議席へと躍進した。特に比例代表では立憲民主党を上回る742万票を獲得し、自民党、公明党に次ぐ第3党となった。この結果を文藝春秋PLUSのインタビューで慶應義塾大学名誉教授の堀茂樹氏が分析し、参政党の強さの根源と、その批判に対する見解を語った。
参政党との出会いと草の根の「愛」
堀氏は、参政党の存在を去年の暮れまで知らなかったと明かす。しかし、知人の安藤裕氏が参政党から出馬することを知り、調べ始めたという。その中で堀氏が特に印象的だったのは、「地方に支部がありますね」と語るように、地方に根ざした党員組織の存在であった。
辻立ちで演説をする地方議員や党員の姿をネットで見て、「自分の故郷や、自分の祖国、あるいは家族とか、そういうそのものに対する思いを込めて『なんとかしないと日本は危ない』と」訴える姿に心を動かされたという。現代社会で個人主義やグローバルな活躍が強調される中で、参政党員たちは「もっとリアルなもの、もっと身近なもの、自分の国だとかっていう、ある意味では自分を超えるもの」への「簡単にあえて言えば愛なんだ」と堀氏は表現し、その熱量に「非常に感動的だった」と参政党への注目を始めたきっかけを語った。
憲法草案に見る「民族義的」な国民観と堀氏の異論
堀氏は、参政党の基本政策にはほぼ全面的に賛成である一方で、その「国家観」、特に「ネイション(国民共同体)」の捉え方については共有できない点があるという。参政党の国民観は「かなり民族義的」であると指摘する。
「啓蒙主義的ではなくて、むしろロマンティズムの系譜を引く」もので、神話の時代からの日本の継続性や永続性に根ざした「日本民族」というイメージが強く、「民族と国民の区別ができていない」と堀氏は述べる。堀氏の考える国民とは、血統主義の国であっても外国人を受け入れる可能性があり、民族とは異なるものだという。
特に、参政党の憲法草案(あくまで案だと前置きしつつ)について、「驚いたのは公職につくということについてですね、3代までダメだと」書かれている点を挙げ、これは考え直すべきだと訴えた。人間は環境に同化する性質があり、日本に住む外国人でも「同化されるんですよ」と述べ、文化的な同化の可能性をシャットアウトするような「決定論的な宿命論的なナショナルアイデンティの捉え方」には同意できないとした。
日本の文化的土壌と「脱グローバル化」の時代
では、なぜ根本的な意見の相違がありながらも参政党を支持するのか。堀氏はその理由として、日本の「文化的土壌」と「日本人の集団として持ってる文化的な傾向」を見誤ってはいけないという強い思いがあると語る。
「汝自身を知れ」と述べ、日本人が「それほど個人主義的な国ではない」ことを強調する。日本の家族システムは「直系と言われる。縦に続く長男が家を継いでいくという緊密な家族システム」が歴史的に定着しており、葬式や結婚式で親戚が集まれば、「長男から順々に並んで座りますよね」と、個人主義的な西洋とは異なる日本の集団的特性を指摘した。
このような文化的背景を持つ日本人が、「グローバルに活躍しろ、自分のために生きろ。家族から離脱していく」という意識を植え付けられても、「自分たちのメンタリティに馴染まない」と堀氏は語る。
さらに、現代は「脱グローバル化の時代」にあり、日本も「周回遅れで未だにグローバルグローバルって言ってますけど、もうそういう風に変化してきてます」と国際情勢の変化を指摘した。日本が独立国として生き残るためには、「日本は日本に立ち返る。日本人は日本人に立ち返る」ことが必要だと訴える。
堀氏は、むしろ「しっかりした土台があって、それが安定している時に一定程度の跳ね上がりというか、一定程度外へ出ていく、冒険的なことがある」と述べ、古いタイプの日本にこそ、独創性や冒険心が育まれる土壌があったのではないかと分析した。
参政党は「よっぽど近代的かもしれない」
既存政党がグローバル的なメッセージを発信していることに対し、堀氏は「西洋人になんかなれないんですよ」と厳しく批判した。
日本の強みは「継続性を重視し、製造業ができて熟練者を作れる強みがあるわけ」であり、ドイツと同様に「それほど個人主義的な文化じゃない」ことから、「アングロサクソンを真似する必要はない。真似するのは愚かだ」と強く主張する。
堀氏は参政党のフェスティバルに潜入した際の印象を語り、「尊敬できる日本人だなと。そしてこの人たちならやるかもしれない」と、草の根で立ち上がった普通の人々の熱意と可能性に驚きを隠さない。
彼らは既存のエリートからは「ポピュリズム」だと批判されるが、「本当の意味の民衆が日本的なやり方で組織を作ってらっしゃんだ」と評価する。さらに、「自分の意思を持った人たちの集団だからこれは強いぞ」と述べ、参政党の強さが個人の自律的な意思に基づいていることを強調した。堀氏は、古い考え方を選んでいるように見える参政党の行動原理こそが、既存政党よりも「よっぽど近代でかもしれない」と結論づけた。
「排外主義」批判の誤謬と民主主義の本質
参政党への「排外主義」批判に対し、堀氏は真っ向から反論した。多くの知識人やメディアが「テレッテルを張り付けるように排外主義って言って批判してるのは下の下」だと批判し、「デモクラシーっていうのは体制ですから。民主性っていうのは一定の排外性を必ず伴う」ものだと語る。
ギリシャのアテナイの民主主義を例に出し、それは同時に極めて排他的なものであったことを指摘。「そういう要素はなるべく少ない方がいいけれども、不可欠だということを考えてみていただきたい」と述べ、多数決で少数派が多数派の正当性を認めるためには「区切ってるから」であり、外部からの介入を排除する境界線が必要不可欠だとした。つまり、「国境のない状態で民主性はできない」のであり、「国民国家が民主性の不可欠の受け皿なんだ」と結論づけた。
EUが民主主義の赤字を抱えるのは「EU人民というのはいないから」であり、人民というまとまりがなければ民主主義は成立しないという自身の考えを述べた。
「あらゆるグループ、あらゆる集団は包摂と排除のシステムなんだ」と堀氏は語る。私生活の次元でも、恋人関係や親子関係が排他的であるように、政治の次元においても「ある人々のために働く、ある人々のに対して責任を取る」という排他的な性格は存在するという。国会議員は「日本の国民に対して責任を取るべきもの」であり、「日本人以外の人に対して責任は取るべきでは」ないという線引きは「あえて言うなら災害性」だとし、それが民主主義の成立に不可欠な要素だと主張した。
ただし、その「排外性」を「穏健化して、文明化してやっていくべき」だが、「その論理自体は包摂と排除のシステムの論理自体は変わらない」と述べ、排他性の論理そのものを受け入れることの重要性を訴えた。
「日本人ファースト」への批判とエリートの役割
「日本人ファースト」という言葉に対する批判について、堀氏は「彼らは日本人だという無意識から自由じゃないからじゃないか」と推測する。その無意識があるからこそ、「一層際立つんじゃな」いかと語る。
しかし、堀氏は「日本という国が没落して危なくなってくれば来るほど、逆に日本をなんとかしたいと、自分は日本人なんだと、そこに自分のアイデンティの寄り所を見出すという方々の気持ちは十分かる」と、参政党支持者の心情に理解を示した。
そして、「日本が余裕がなくなってくると国民を優先しなきゃなくなってきてる」状況において、「日本人のための政治をしてほしいっていう気持ちで日本人ファーストに感動する人々がいらっしゃるのはごく自然なこと」だと述べた。
ただし、日本人ファーストが「日本人をグラデーション化したものに別けていくことはやめなければ」と警鐘を鳴らし、それは「止めなきゃいけません」と強調した。これはアイデンティティ・ポリティクスが過激化する左翼の現状と同じ質のものになってしまう危険性があるという。
堀氏は、ナショナルアイデンティティは「自分の与えられたものとして受け取ってそれを受け入れる。そしてそれを土台にするということはいいんだけど、そこで閉じてしまうっていうのはよろしくない」と述べ、リーダー層が「知恵を働かせてやっていく必要はある」と語った。そして、参政党を批判するエリート層に対し、「『参政党に投票したやつは簡単に騙されてるんだ』とかっていうのは非常におこがましい」と厳しく指摘。エリートの役割は「民衆の足らないところを知識で補うという役割」だと語り、傲慢な態度ではなく、知識をもって民衆を導くことの重要性を訴えた。
慶應義塾大学名誉教授の堀茂樹氏の分析は、参政党の躍進が単なる一過性のブームではなく、日本の文化的土壌や民主主義の本質に根ざした現象であることを示唆する。既存のエリート層とは異なる視点から、草の根の活動や「日本人ファースト」に込められた国民の心情を深く理解しようとする姿勢は、分断が深まる現代社会において示唆に富む。
はたして、堀氏が指摘する「近代と前近代のマッチング」というパラドックスを抱える参政党は、その持つ可能性と危険性を自覚し、国民の多様な声を包摂しながら、真に「日本人」が望む未来を切り拓くことができるだろうか――。知識人が果たすべき役割と、国民が自らのアイデンティティをどう捉えるべきか。堀氏の問いかけは、日本の政治の未来を考える上で重要な一石を投じたと言えるだろう。

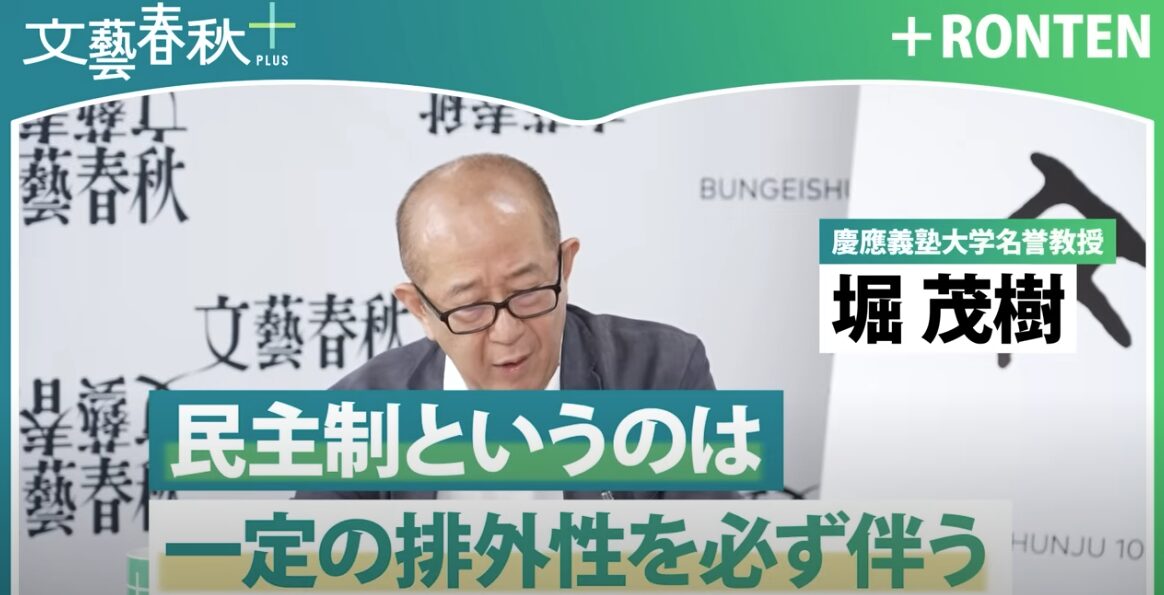


コメント