元朝日新聞政治部デスクの鮫島浩氏が、参議院選挙の結果から、立憲民主党が「最大の敗者であった」と断じる。投票率が上がっても勝てないリベラル勢力の自己矛盾と、その背景にある「古臭い左右イデオロギー対決」への固執を厳しく批判。世界の潮流が「上と下」の対立へと移る中、リベラル勢力再生への課題を提示する。
投票率上昇で惨敗した「最大の敗者」
今回の参議院選挙は、与党の過半数割れという大きな結果をもたらした。しかし、鮫島氏は、本当に目を向けるべきは与党の敗北ではないと指摘する。参院選の裏側で起きていた、立憲民主党の壊滅的な敗北と、日本のリベラル勢力が直面する深い闇を、鮫島氏の分析から読み解いていこう。
今回の参院選は、連休の中日に投票日が設定されたにもかかわらず、投票率は58.51%と前回から6ポイントも上昇した。これは、普段選挙に行かない「若者や現役世代の無党派層が投票所に足を運んだ結果」だと分析される。
これまでリベラル勢力は「投票に行けば自民党が負ける」と主張してきたが、投票率が上がって自民党が負けたにもかかわらず、立憲と共産党も大敗した。特に立憲民主党は、前回の衆院選から「417万票もの大幅減」となり、約4割の支持者が離れたという。これは自民党の減少数(178万票)の2倍以上であり、立憲民主党こそが「参院選の最大の敗者である」と鮫島氏は断じる。
この無党派層の票はどこへ流れたのか。それは、参政党、国民民主党、保守党といった「第三極の新興保守政党」へ流れたのだ。世論調査でも、立憲民主党の支持層が70代以上の高齢者に偏っている一方で、50代以下の現役世代では新興政党に大きく負けていたことが明らかになっている。
「石破やめるな」コールに見る自己矛盾
参院選での自民党の惨敗を受け、石破首相の辞任を求める声が強まると、立憲や共産党の支持層からは「石破がやめると高市政権や小泉進次郎政権が誕生するかもしれない」という警戒感から、「石破やめるな」という投稿が相次いだ。
鮫島氏は、この現象をリベラル勢力の「自己矛盾・自己否定」であると厳しく批判する。本来、民主主義のルールを重視し、選挙で示された民意を無視する首相の即刻退陣を主張するべきリベラル勢力が、その民意に否定された首相を激励するという、信じられない事態が起きたのだ。
この行動は、リベラル勢力自身が、立憲民主党の野田代表を中心とする「野党連立政権の誕生に期待できない」、つまり「政権交代を諦めている現実の露骨な現れ」だと分析された。
世界の潮流を見誤った「古臭い」イデオロギー
リベラル勢力がこれほど凋落した根本原因は、「古臭い左右のイデオロギー対決に固執している」からだと鮫島氏は指摘する。世界の潮流は、経済の自由競争と人権を重視する「グローバリズム」勢力と、それに反発し、国家主権の強化を求める「反グローバリズム」勢力という「上と下」の対決に移っている。
例えば、アメリカでは反グローバリズムを掲げるトランプが共和党を乗っ取り、大統領に返り咲いた。経済界や知識人はグローバリズムに賛同し、一般大衆は格差社会に反発して反グローバリズムに共鳴しているのだ。
しかし、立憲民主党は「自民党と共にグローバリズムを推進」し、緊縮財政を主張してきた。一方で人権や共生社会といった理念を掲げながら、反グローバリズムを掲げる参政党を「極右排外主義」と批判した。この結果、立憲民主党は自民党と一緒に敗北し、「むしろ自民党以上に沈んだ」。欧米で起きた既存政党の崩壊と全く同じ道を辿っていると鮫島氏は語る。
リベラル勢力再生への道
リベラル勢力がこの凋落を食い止めるためには、「貧富の格差をもたらしたグローバリズムへの反発に真正面から向き合う必要がある」と鮫島氏は結論付ける。古臭いイデオロギー対決から脱却し、世界の潮流である「上と下」の対立構造を理解し、その中で自らの立ち位置を再構築しなければ、日本のリベラル勢力に未来はないだろう。
投票率上昇という追い風が吹きながらも、自民党以上に大敗した立憲民主党。その惨敗は、日本の政治が新たな地平に突入したことを明確に物語っている。はたして、日本のリベラル勢力は、自己否定と向き合い、時代に即した新たな価値観を見出すことができるだろうか――。

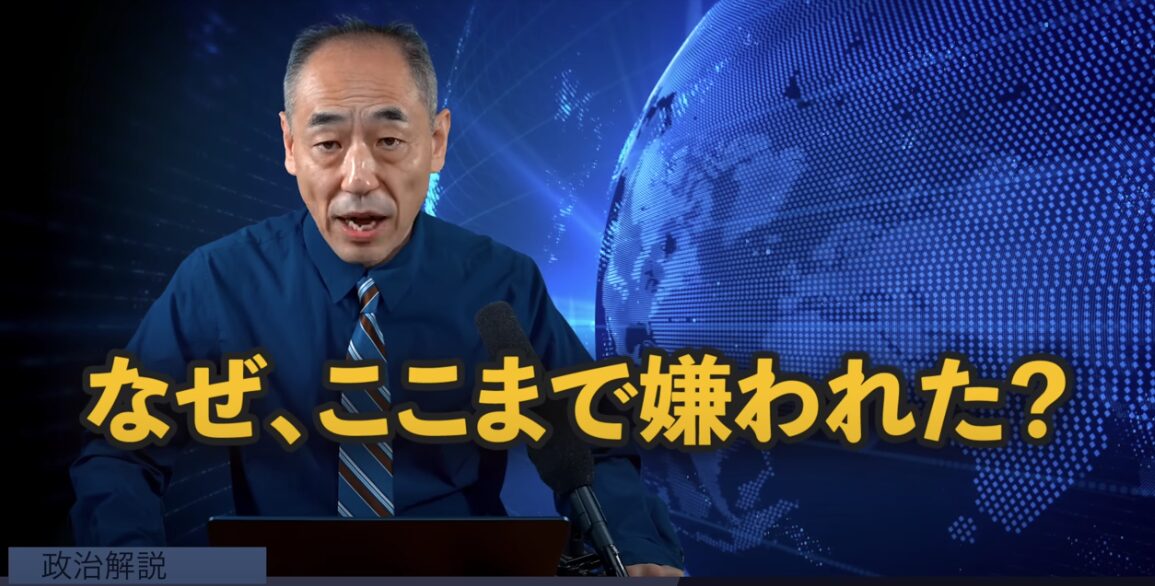


コメント