文芸批評家の浜崎洋介氏が、日本の政治家や国民の歴史認識が抱える問題を鋭く指摘する。終戦記念日の「談話」に象徴される「不甲斐ない話」の背景にある「政治家の限界」を指摘し、左派の「自虐史観」と右派の「ナルシズム」が真の反省を妨げていると批判する。そして、大東亜戦争の真実に向き合うための多角的な視点を提言する。
真の反省を阻む二つの歪んだ歴史観
終戦記念日に向けた首相による「談話」について、浜崎氏はその本質的な問題を指摘する。サンフランシスコ講和条約が東京裁判の受け入れを前提としているため、首相という立場の人間が「思想的あるいは実的に正しいことを言うのって非常に難しい」。
だからこそ、歴代の首相談話は「不甲斐ない話」にならざるを得なかったのだと、その「政治家の限界」を語る。石破首相が発表する談話も「厳しいものになる」と予測し、周辺国に「揚げ足取られ」てしまう危険性を危惧する。
浜崎氏は、大東亜戦争を巡る歪んだ歴史認識を、左右両派に存在する二つの極端な考え方として批判する。
左派が主張する「自虐史観」は、「戦前が悪かった、戦前は軍部が暴走した、戦前の日本人は狂気だった」とするものだ。浜崎氏はこれを「一言なんだよ」と一蹴する。それは真の反省ではなく、「過去を切り落とし、あいつらはバカ、僕とは違う」と線を引くことで、自分事として反省することを避けている行為だと指摘する。
一方、右派の「ナルシズム」は、「あの戦争は悪くなかった、アジア解放戦争であった」という見解だ。「負けてんじゃん」と批判し、ナルシズムに陥ることで「痛々しい現実に蓋をして」「反省できない」状態に陥ると警鐘を鳴らす。
左右両派ともに「あの戦争が一体何だったかということを心から反省したことが一度もない」と断言する。真の反省とは「自分たちの失敗だと思えばいい」ことであり、「我がことにしない限り、二度三度四度と同じ失敗するよ」と、失敗から学ぶことの重要性を強調する。
「必然」としての大東亜戦争
浜崎氏は、大東亜戦争の本質を理解するためには、まず「東京裁判史観に僕ら囚われるからそれを徹底的に排除する」ことが重要だと訴える。東京裁判は「アメリカの都合で作ってる」ものであり、国民や言論人はそれに「付き従う必要は全くない」と主張する。
そして、しっくりくる歴史観として「林房雄の東亜百年戦争という考え方がしっくり来るんだよ」と語る。「ペリーショックから始まってそっからの対応であそこまで行った」という「70年近い流れ」として戦争を捉えることで、大東亜戦争に至る「必然」が見えてくるという。
また、戦争を「軍部の暴走」という一言で片付けることにも異を唱える。軍部は「当時最高のエリート」であり、「バカだったで済むのか」と問題提起する。統制派と行動派といった派閥の形成や、第一次世界大戦への対応といった歴史の流れを見ることで、軍部が「真剣に頭を使っている」ことを理解すべきだと主張する。
国民全体の責任と「負け方」の問題
大東亜戦争は、軍部や政治家だけでなく「あれは国民がやった戦争なのよ」と浜崎氏は主張する。
ポツダム宣言が「国家が悪かった」とし、「国民は無垢で素直だった」と見なした点に対し、浜崎氏は「そんなことは全くなくてむしろ国民の方があの戦争に対しての参戦欲が激しかった」と反論する。当時の「ナショナリズムが渦巻いてた」状況を鑑み、「国民だけ免罪して政府だけが悪い、軍部だけ悪い。なんという卑怯」だと厳しく批判する。
さらに、戦争の「負け方もひどいんだ」と指摘する。サイパン失陥など「もう100%無理」な状況になっても「ずるずるずるずる」と戦争を続け、やめられなかった状況を問題視する。昭和天皇が「誰も戦争が止められなかった時」に終戦の意思決定をしたことからも、当時の日本人が「誰も何も決められない状況」に陥っていた弱さを指摘する。
現代への示唆と「本当の反省」の必要性
浜崎氏は、現代の平和教育が「イデオロギーに傾いてる部分がある」と指摘する。
「戦争は絶対にしてはならないことは分かってる」が、その「分かり方が多分おかしいんじゃないかな」と問題提起する。そして、「その分かり方が歪んでる限り、もう一回戦争しますからね」と警告する。
浜崎氏は、終戦80年談話に対し、「抵抗しましょう」と呼びかける。そして、イデオロギーではなく、「事実に基づいて」歴史を見つめ直し、過去の失敗から学び、現在の日本の問題と向き合うことの重要性を強調する。
はたして、私たちは大東亜戦争という過去の失敗から学び、未来の日本を築くことができるだろうか――。

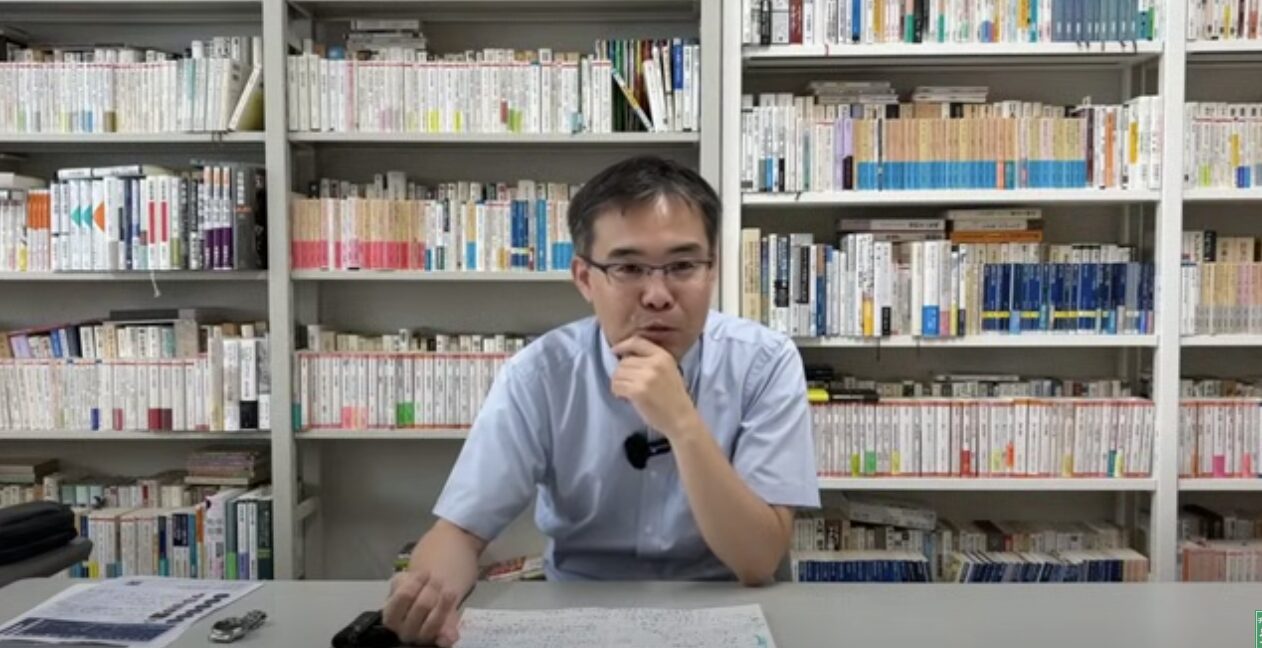


コメント