元参議院議員の浜田聡氏が、今回の参議院選挙での落選について語る。個人得票数で全国7位の33万票以上を獲得しながらも落選という異例の結果となった背景には、日本の選挙制度の課題が浮き彫りになった。その原因と、今後の活動への展望を明らかにする。
「全国7位」でも落選した選挙制度の壁
今回の参議院選挙で、NHK党の比例代表から立候補した浜田聡氏。個人得票数で「全国で7位となる33万5000票余りを獲得」した。これは、ドント方式という計算方法で議席が配分される比例代表制において、得票数上位10人の中で「浜田さんだけが落選してしまったのです」。
この結果に対し、ネット上では「制度のバグすぎる」といった声が多数上がっている。落選の直接的な原因は、NHK党の政党票が前回から半減し、議席が割り当てられなかったことだ。浜田氏も、「政党票はやっぱり選挙区の状況に大きく左右される」と分析する。
国政政党の要件を満たせなかったことで、「メディアの露出」が減り、その結果「支援者の方に呆きれられた、支持が離れたっていうところは非常に大きかった」と、浜田氏自身もその影響の大きさを認めている。
独自の視点で国会に切り込む「質問主意書」
浜田氏が多くの票を獲得した背景には、国会での独特な政治活動がある。特に注目されたのは、「質問主意書の提出件数がダントツですごい多い」質問主意書の積極的な活用だ。全議員が提出した質問主意書の半分以上を浜田氏が一人で担当したという。
新人議員時代には、麻生財務大臣(当時)から「かっこいいですよ今の質問は」と絶賛されたエピソードもある。麻生氏は、「自分で考えて質問を作っている」点を高く評価した。これは、役人が作成した質問をただ読み上げるだけの議員が多い中で、浜田氏の独自性が際立っていたからだ。
政治ジャーナリストの平井氏は、浜田氏の質問について、「普通の人が不満とか不安に思ってるけどどうにもならないかなと思ってるようなことをちゃんと聞いてくれる」と評価し、「右も左も関係なく評価が高い」と述べている。浜田氏も、SNSのインプレッション数を参考にしながら、「需要が高いんだけれど他の議員が取り組まない問題」を積極的に取り上げていきたいと考えている。
過去の成功と今後の展望
NHK党が2019年の参議院選挙で議席を獲得できたのは、「集金人の問題」を解決するという明確な目標があったからだ。しかし、暴力的な集金人の問題が解決したことで、「地方選挙に勝てなくなった」と浜田氏は分析する。今後の党の目標は「スクランブル放送」の実現だ。
浜田氏は、今後の活動について、「メディアとの戦いをしっかりしていきたい」と語る。多くの政治家がメディアとの対立を避ける中で、自分たちの存在意義があると主張する。
また、国政選挙で勝つためには「地方の組織」が重要であると認識しており、今後は「地方議員の方を増やして、地方の選挙を戦うことで我々のことを知ってもらう」ことに注力するという。浜田氏自身も複数の政治団体を作り、「いろんな形で地方の選挙に打って出て」活動を広げていく考えだ。
今回の落選は、一見すると不運な結果に思えるが、浜田氏はこれを「すごくプラス」だと捉えている。彼の落選によって、日本の選挙制度の問題が浮き彫りになっただけでなく、浜田氏自身の認知度や、NHK党への関心を再喚起する機会になったからだ。SNSのフォロワー数も大幅に増えたという。
得票数では勝利しながらも落選という矛盾を抱えた浜田氏。はたしてその経験は、次の政治活動で「すごくプラス」となるだろうか――

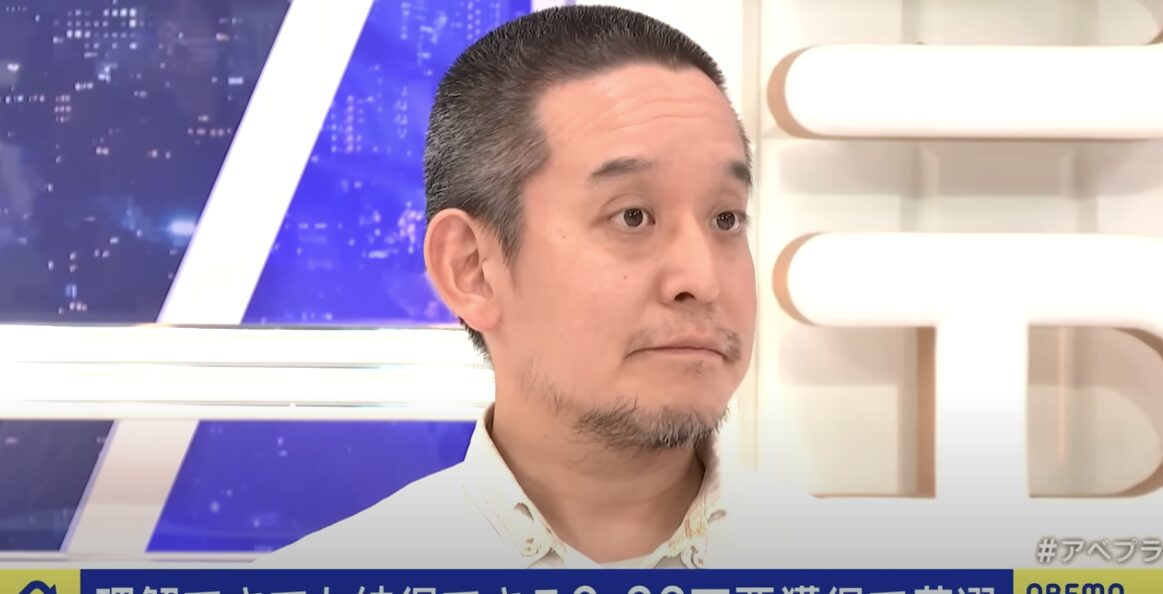


コメント