作家のエルヴィラ・バリー氏が、現代ロシアにおけるスターリン崇拝の根深い実態を解き明かす。ヴォルゴグラードに新たな記念碑が建ち、世論調査で称賛が高まる裏側には、単なる政治的イデオロギーではない「カルト」としてのスターリン主義、そして歴史的トラウマが絡み合っていると指摘する。ロシアが過去の「偉大さ」に固執する理由を、バリー氏の言葉を引用しながら紐解く。
スターリン主義は「宗教的な使命」を持つカルトだった
バリー氏は、スターリン主義を「単なる政治的なプロジェクトではなくカルト」だったと定義する。ボリシェヴィキは、「自分たちの運動を世界救済の使命、いわば世界を作り変えるという宗教的な使命と位置づけた」。このカルトはキリスト教の二元論や聖典、預言者といった要素を借用し、「閉鎖的なシステム、カルトを作り上げました」。このシステムは、人々が「心理的にその方が安全だから」スターリンを信じるようになり、カルト内で居場所を確保することが唯一の生存戦略となっていたのだ。
人々は恐怖と貧困の中で、「我々は新しい世界を築いている」というメッセージに「意味」を見出した。たとえ自由や命を犠牲にしても、「より偉大なもののために生きていると信じていた」のだ。これは、個人の生存が国家の評価に完全に依存する閉鎖的なシステムの中での、一種の「ストックホルム症候群」にも似た心理状態であったとバリー氏は分析する。
経済危機と「敵の創出」という生存戦略
1920年代後半のソ連は、工業の崩壊や熟練専門家の不足といった深刻な経済危機に直面していた。しかし、ソ連指導部は「『我々は失敗した』とは言えなかった」。そこで政権がとった戦略は「敵を作り出した」ことだった。
これが、無実の人々が架空の犯罪を自白させられた「見せしめ裁判」につながる。同時期には、経費削減のため「イデオロギーに偽装された残酷な会計処理」として「粛清」が始まったのだ。
この壮絶なテロの背景には、第一次世界大戦とロシア内戦のトラウマがあったとバリー氏は指摘する。スターリンの高官のほとんどは「9年間にわたる流血の経験」を持ち、「大量死は当たり前のことでした」。PTSDは診断されることなく、生き抜くしかなかった。さらに、スペイン風邪とチフスの流行が国全体を「熱にうなされ、半ば狂乱状態」に陥らせたという。
「偉大さ」という神話の代償
現代のロシアでは、「スターリンがソ連を大国にした」という神話が根強く信じられている。しかし、バリー氏はこの神話に疑問を投げかける。「国民が恐怖と貧困と沈黙の中で暮らしていたとき、それを本当に『偉大さ』と呼べるだろうか?」
スターリンの無謀な工業化と強制的な近代化は「人的犠牲をいとわない」ものであり、「その代償は計り知れないものだった」。バリー氏は、もしスターリンが地方で戦争を仕掛けなければ、「今日のロシアの人口は数倍になっていたかもしれない」と語る。彼の遺産は「偉大さではなく、よそ者によって再建された、荒廃した田舎」だったのだ。
また、今日でも多くのロシア人が信じる「スターリンが汚職を抑えていた」という話も幻想に過ぎない。バリー氏は、抑制と均衡がなく、独立した裁判所もないシステムでは、「汚職は例外ではなかった。それが設計そのものだった」と指摘する。
過去にすがる「目を背ける文化」
現代のロシア指導部は未来への明確なビジョンを持たない。そのため、過去の「美学」と「イメージ」に目を向けている。「ソビエトのイメージは強力だ。映画的であり、記念碑的だ」。現代のエリートたちは、「力と目的意識、自分よりも大きな何かに属しているという感覚を渇望している」のだ。
これは、「イデオロギーの復活」ではないとバリー氏は説明する。彼らが追い求めているのは、「かつてあったものではなく、実際には存在しなかったもの、つまり幻想への郷愁」なのだ。
この状況の背景には、スターリン時代に培われた「見ようとしない。目を背ける文化」がある。「隣人が逮捕された時、人々は目を背けることを学んだ」。この習性は、現在のウクライナ戦争に対する人々の反応にも通じるものがある。
真実が耐え難いとき、人々はそれを「慰めとなる神話で置き換えてしまう」。「真実が耐え難い時、私たちはそれを葬り去るか、慰めとなる神話で置き換えてしまう」。これが、バリー氏が語る「心理的置換」だ。
ロシアにおけるスターリン崇拝は、単なる歴史の歪曲ではなく、過去のトラウマや現代の政治的空白から生まれた、根深い心理的現象だ。はたしてロシアは、過去の幻想にすがり続ける「目を背ける文化」から脱却できるだろうか――



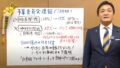
コメント