チームみらい党首の安野貴博氏が、AIが科学研究にもたらす変革について語る。AIが単なる補助ツールから、自律的に科学を発展させる「AI駆動科学」へと移行しつつある現状を解説。AlphaFoldやAlphaEvolveといった具体例を挙げながら、人間の脳の制約を超えた科学的発見の可能性と、日本が取るべき政策について提言する。
AIが科学を変える:「AlphaFold」の衝撃と「AI駆動科学」の幕開け
チームみらい党首の安野貴博氏によると、AIはすでに科学の進歩に大きく貢献し始めているという。特に、2024年にノーベル賞関連研究も出たことで知られるGoogle DeepMindの「AlphaFold」は、「もうまさにゲームチェンジャーです」と安野氏は語る。AlphaFoldはタンパク質の3次元構造を数十分から数時間で高精度に予測するAIだ。従来はX線結晶構造解析や電子顕微鏡、巨大加速器施設などを使い数年かかっていた作業が劇的に短縮されたという。2018年に最初のバージョンがリリースされ、2024年にはAlphaFold 3にアップデート。アプリケーションはGitHubで公開され、誰でも利用可能だ。安野氏は、「AlphaFoldによって生命科学の進展スピードがめちゃめちゃ上がった」と、その影響の大きさを強調する。
さらに、2025年5月にはGoogle DeepMindから新しいアルゴリズム「AlphaEvolve」が登場したという。AlphaFoldがタンパク質構造予測だったのに対し、AlphaEvolveは「アルゴリズム(計算のやり方自体)をAIが設計したり改良したりするエージェント」だ。Googleのデータセンター最適化やTPU(Googleが製造するAIチップ)の設計、1969年以降改善が見られなかったアルゴリズムの改良などに既に貢献しているという。50以上の未解決の数学問題に対し、20%でこれまでのベストな解法をさらに改良し、75%で既知の最高解にAIが自力で到達した実績があるのだ。数学、アルゴリズム、計算機科学の領域で成果を出しているという。
また、AIを使って実際の治療薬候補を選定する企業「Future House」のような事例も次々と現れている。3つのAIエージェントを組み合わせ、大量の論文を読み込み、疾患に対する有望な治療薬候補を特定しているという。
これらの事例から、AIが科学的発見をサポートする動きは、大企業から比較的小規模な企業まで多岐にわたり、AIが科学技術の発展を「駆動し、リードしていく」状態へと徐々に移行すると安野氏は予測する。科学研究の方法は以下の4つのレベルで変化する可能性があるという。
レベル1:人間の補助(現在すでに広く普及) AIが研究者の補助を行う段階だ。統計分析のためのコード生成、論文執筆におけるリサーチや執筆補助などが含まれる。「2025年でも当たり前のことになっている」。
レベル2:実験不要な研究におけるAIの自律的推進(現在始まりつつある) 物理空間での実験を必要としない研究分野で、AIが主導権を握るようになる段階だ。AlphaFoldやAlphaEvolve、Future Houseのような事例がこれに該当する。特にコンピュータサイエンスや情報科学の研究は、計算機内ですべてが完結するため、AIが人間を凌駕し始める可能性があるという。「AIのAI研究」が有望で、AIが自身の研究を行うことで、より優れたAIが生まれ、さらなる研究を進めるという好循環(フィードバックサイクル)が期待される。
レベル3:クラウドラボを通じた物理実験の自動化 AIが、全自動実験室「クラウドラボ」を介して物理的な実験を行うようになる段階だ。Emerald Cloud Labのような企業が既に存在する。「地球上のどこにいてもパソコン上でこういう実験をしてくれということを言うとその実験をやってくれる」。AIが指示を出すことで、化学や生物学などの実験室における研究が徐々にAIによって実行可能になる。
レベル4:ロボティクスによる実世界での研究 ロボティクス技術の発展により、AIが物理的に移動し、実世界で様々な研究活動を行うようになる段階だ。これにより、実験室の枠を超え、より広範な分野でのAIによる研究推進が可能になる。
「理解」から「成果」へ:AI駆動科学がもたらす根本的変化
AI駆動科学が進むことで、科学研究のあり方に根本的な変化が生じると安野氏は予測する。
これまでの科学研究は、人間の脳が「理解できる」という制約を受けていた。人間の直感や納得感が非常に重要視されてきたのだ。しかし、AIは人間の脳の制約を超越できる。「脳みそという制約を外せる」。AIは高次元(数百次元)の空間を扱うことができ、人間には直感的に理解できないような発見をもたらす可能性があるという。
これにより、「理解」と「成果」の分離が進むと安野氏は語る。従来は、人間が世界をうまくモデル化し、理解することで成果が出やすかった。しかし、AI駆動科学の進展により、「人間は分かっていないけれど、実際に成果は出る」という現象が多発するようになるのだ。
囲碁のAlphaGoが、人間には悪手にしか見えない手を打ちながら勝利した事例を引用し、「人間が理解はできないんだけれどもめっちゃ成果が出るような、そういうものがたくさん発見されてくるんじゃないか」と安野氏は述べる。この変化は、「人間が何かを理解しているということの価値自体がすごく変わる」ことを意味するという。
日本が取るべき道:AI駆動科学を支えるインフラ投資
このようなAI駆動科学の時代において、日本が取るべき政策としては、それを支える仕組みの構築が不可欠だと安野氏は提言する。
具体的には、インフラ投資の強化が必要だ。クラウドラボのような全自動実験施設への投資、研究室を支える物品への投資、そして科学計算のためのコンピュータ資源(GPUクラスターなど)への投資が求められるという。これらはこれまで関連性が薄かった分野でも必要となるのだ。
AIは科学研究のあり方を根本的に変え、人間の脳の制約を超えた新たな発見を可能にする「ゲームチェンジャー」となるだろう。従来の「人間が理解できること」を前提とした研究から、「成果を出すこと」を重視するAI駆動科学への移行は、科学だけでなく、人間の「理解」そのものの価値観に大きな変化をもたらす。日本は、この変革に対応するため、AI駆動科学を支えるためのインフラ投資と制度設計を積極的に進めるべきだ。


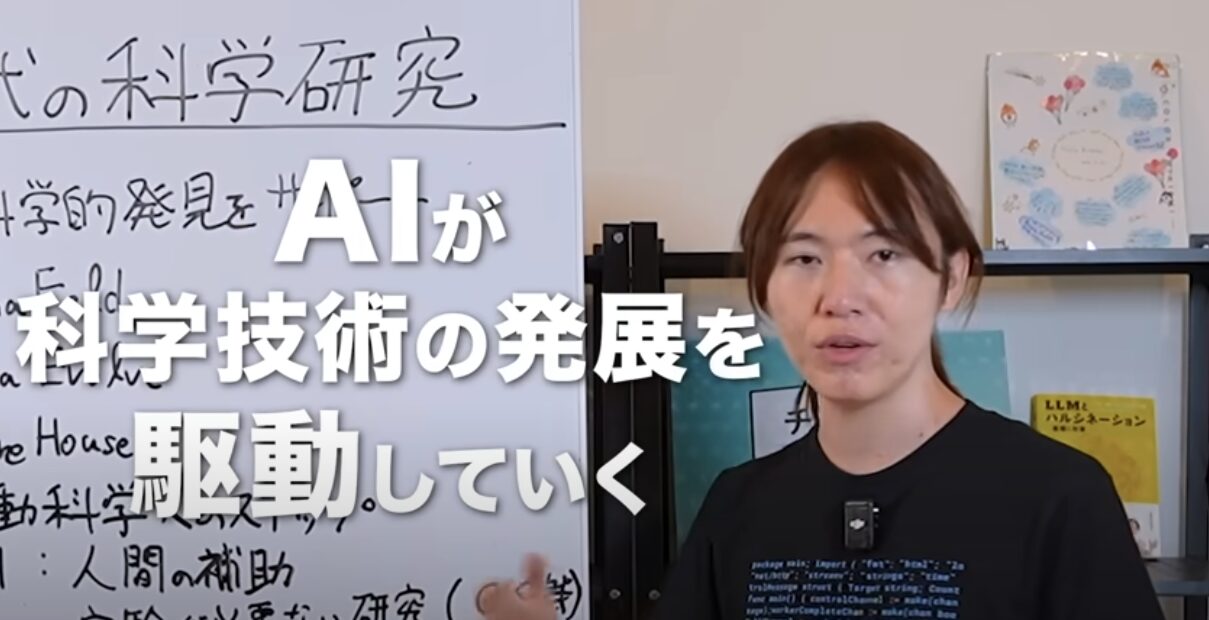


コメント