軍事ジャーナリストの黒井文太郎氏が、現代における「情報戦」と「認知戦」の現状について警鐘を鳴らす。SNSの普及により情報が武器化され、人々の認知や行動が誘導・操作されるメカニズムを解説。ロシア、中国、イランなどの先行事例から、日本が直面する脅威と対策の難しさ、そして個人の情報リテラシーの重要性を指摘する。
SNS時代の新たな戦い「認知戦」とは?
軍事ジャーナリストの黒井文太郎氏によると、情報を武器として利用する「情報戦」の概念は古くから存在するという。冷戦時代にはソ連のKGBが西側社会の分断を狙った情報操作を行っており、当時は「心理戦(サイコロジカルウォー)」と呼ばれ、プロパガンダや民衆の心をつかむ活動など、広範な分野にわたっていたのだ。
しかし、2010年代半ばからのSNSの爆発的な普及により、情報戦は大きく変貌したと黒井氏は指摘する。従来のメディア操作に代わり、SNSで偽情報(フェイクニュース)を直接拡散することで、人々の認識を誘導し、投票行動などをコントロールする手法が確立されたのだ。これが「インフルエンスオペレーション(影響工作)」または「誘導工作」と呼ばれ、軍事用語では「認知戦」という新しい言葉で表現されるという。
認知戦の特徴は、大砲や戦闘機のような物理的な兵器とは異なり、ネットを通じてフェイクニュースを流すことで人々の認知を操作する点だ。これは「ピュアな軍事」とは異なるが、広義の安全保障において「喫緊のホットなテーマ」になっていると黒井氏は語る。
国際社会で激化する情報戦のプレイヤーたち
アメリカでは、90年代にネット媒体やケーブルテレビ、特にFox Newsが発達し、フェイクニュースが浸透しやすい土壌が形成されたと黒井氏は解説する。Newsmaxや地元ラジオの過激なパーソナリティ、陰謀論サイト(Infowarsなど)が影響力を持ち、YouTubeやポッドキャストもその拡散を加速させたのだ。2013年頃にはOne America Newsのような陰謀論的なケーブルチャンネルも登場し、2015年のトランプ大統領登場の素地を作ったという。
情報戦の「トップランナー」とされるのはロシアだ。冷戦時代から心理戦のノウハウを持つプーチン政権は、2003年頃からの経済復活を背景に情報工作を再開したという。
その代表例が、2013年にサンクトペテルブルクに設立されたインターネット・リサーチ・エージェンシー(IRA)だ。エフゲニー・プリゴジンが関与していたこの組織は、アメリカ国内の分断(人種差別、銃規制反対など)を煽るネット活動を展開したと黒井氏は明かす。特定の誰かを褒めるよりも、非難する方が「バズる」というSNSの特性を巧みに利用したのだ。
2016年の米大統領選では、IRAがFacebook広告枠などを利用し、ヒラリー・クリントンへのネガティブキャンペーンを実施したという。「Qアノン」のような陰謀論(「世界を牛耳る民主党は児童売春集団で、トランプは光の戦士」といった主張)がネット上で拡散され、投票行動に影響を与えたとされている。
2016年の大統領選で流行した「ポストトゥルース」という言葉は、メディアが真実かどうかを競うのではなく、人々の気持ちをくんで扇動するメディアが力を持ち、真実よりも個人の感情や意見が優先される状況を指す。これは一過性のものではなく、欧州や日本にも波及していると黒井氏は指摘する。
ロシアの軍事情報機関のハッカー(例:Guccifer 2.0)が民主党サーバーに侵入し、盗んだ情報を意図的に誘導的な形で公開することも行われたという。イギリスのEU離脱(ブレグジット)では、ロシアの情報機関がネットで国民投票を扇動したとされ、欧州各国でも外国人排斥を煽る極右勢力がネットを通じて台頭。プーチン政権からの資金提供も確認されているという。
ロシアの成功を見て、中国やイランも情報戦を強化していると黒井氏は語る。中国は以前「戦狼外交」のような直接的なプロパガンダが中心だったが、ここ7~8年で裏で身元を隠してアメリカの分断を煽るようなフェイクニュース工作を開始。香港の民主化運動時にも同様の工作を行い、沖縄の基地反対運動への接触なども見られるという。イランも最近までペルシャ語が中心だったネット活動が、英語やアラブ語に広がり、海外のネットサイトを通じてイスラエルやアメリカへのネガティブキャンペーンを行っているのだ。
情報戦は戦車や航空機のような高額なコストがかからず、SNSへの書き込みは「お金がかからない」ため、多くの国が模倣し始めていると黒井氏は分析する。
知らぬ間に加担する「無意識のエージェント」の脅威
黒井氏が特に警鐘を鳴らすのは、「無意識のエージェント」の脅威だ。これは、本人が情報機関のエージェントであると認識していないにもかかわらず、仕組まれた情報によって踊らされている状態を指す。冷戦時代にもマスコミ関係者などが情報提供をする中で、KGBのファイル上でエージェントとして扱われる事例があったという。
ネット社会では、フォロワー数の多いインフルエンサーなどが、自覚なくロシアなどの発信する偽情報に引っかかり、その情報を加速・拡散させてしまうケースが急増していると黒井氏は語る。
日本への影響と対策の難しさ
日本は情報戦においてアメリカや欧州に比べて「後発」だが、近年同様の事象が起こり始めていると黒井氏は指摘する。国内選挙においてもネットで「バズる」ことで支持率が上昇する現象が見られるという。
日本は国際政治において発言力が弱いため、欧米に比べ後回しにされてきたが、担当者が存在し、工作は行われているのだ。技術窃取では中国などが日本の防衛企業などから技術を盗む活動が活発だ。世論工作では、中国の統一戦線部が沖縄の基地反対運動に影響を与えようとしたり、ロシアの情報機関系メディアが沖縄のメディアに接近したりしているという。
日本はG7の中でプーチンに対して比較的甘いと見られており、「プーチンは悪くない」という情報が受け入れられやすい土壌があると認識されていると黒井氏は語る。これは北方領土問題が絡み、ロシアの情報戦の「ちょろい国」と見られている側面があるという。さらに、日本国内でも、アメリカや欧州で成功した「外国人差別」をテーマとした情報操作が展開され、「日本人を大切にしている」という形で共感を呼び、票につながる手法が使われていると指摘する。
情報戦への対策は容易ではない。SNSのアルゴリズムは、ユーザーの興味関心に合わせて情報を最適化するため、バズりやすい陰謀論などが表示されやすくなる。一度陰謀論に引っかかると、同じような情報ばかりが表示される「フィルターバブル」や「エコーチェンバー」と呼ばれる情報閉鎖空間に陥り、抜け出すのが困難になるという。
ファクトチェックの限界も指摘されている。フェイクニュースの拡散力は非常に強く、ファクトチェックによって偽情報だと指摘された検証記事は、煽るような情報に比べて読まれにくい傾向があるのだ。
個人レベルでの対策としては、「常に疑いの目を持つ」ことが重要だと黒井氏は強調する。情報源の確認、例えばニュース検索機能を活用し、大手メディアの報道内容と比較することで、情報の信頼性を判断するべきだ。一般検索では陰謀論が上位に来やすいという。また、キャッチーな情報や過激な情報に「即座に反応しない」ことも重要だ。一旦冷静になり、他の情報源と比較検討することが求められる。
国際的な安全保障の観点からは、「暗い未来しか見えない」と黒井氏は述べている。アメリカが情報機関のトップをトランプ政権内で排斥したことなどにより、情報戦を止めるべき民主主義陣営の機能が低下しているからだ。SNSによる情報拡散の流れは止めることが難しく、今後も各国で情報戦が激化する可能性が高いだろう。
情報戦は、既存の軍事力とは異なる形で国際政治・国内政治を揺るがす強力な武器だ。特にSNSの普及は、偽情報の拡散と認知の操作を容易にし、「無意識のエージェント」を生み出すことで社会の分断を加速させている。日本もその例外ではなく、今後、その脅威は増大する可能性がある。個人レベルでの情報リテラシーの向上と、社会全体での情報環境への意識が喫緊の課題だろう。


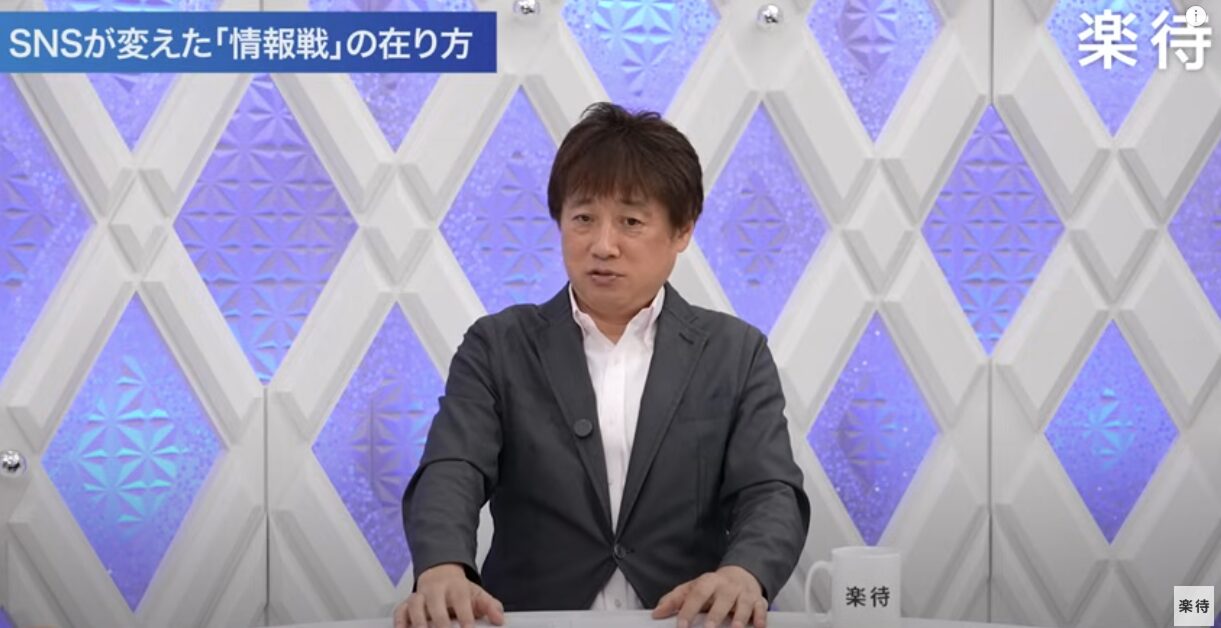


コメント